司法試験の大学別合格率や合格者数について知りたいあなたへ。「どの法科大学院を選べば合格しやすいのか」という疑問は、最新のデータを確認することで解決できます。
本記事では、令和6年度の司法試験における法科大学院別の合格率ランキング、予備試験の大学別合格実績、過去5年間の合格者数の推移について、法務省の公式データを交えて詳しく解説します。この情報をもとに、司法試験合格に向けた法科大学院選びの参考にしましょう。
- 令和6年度の法科大学院別合格率・合格者数ランキング
- 予備試験の大学別合格実績と東京大学が強い理由
- 司法試験合格者数の過去5年間の推移と変動要因
- 法科大学院選びで合格率以外に考慮すべきポイント
- 慶應義塾大学が2冠達成:令和6年度の司法試験において、慶應義塾大法科大学院は合格者数146人、合格率59.35%でともに全国第1位を獲得しました。予備試験合格者を除く法科大学院では圧倒的な実績を誇ります。
- 予備試験ルートの圧倒的合格率:令和6年度の予備試験合格者による司法試験合格率は92.84%と極めて高い水準です。ただし、予備試験そのものの合格率は3.6%程度であり、狭き門であることに変わりはありません。
- 在学中受験制度の影響:令和5年度から法科大学院在学中の司法試験受験が可能となり、在学中受験者の合格率は55.19%と高水準です。法科大学院ルートでも早期合格を目指せる環境が整いつつあります。
-
 スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら
スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら -
 司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら
司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら -
 合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
司法試験の法科大学院別合格率ランキング(令和6年度)
令和6年度の司法試験では、合格者数1,592人、合格率42.13%という結果となりました。法科大学院別の合格率には大きな差があり、トップ校では50%を超える高い合格率を維持しています。このセクションでは、令和6年度の最新データに基づいて、法科大学院別の合格率ランキングを詳しく見ていきましょう。
司法試験合格率トップ10の法科大学院一覧
令和6年度の司法試験における法科大学院別合格率のトップ10は以下の通りです。予備試験合格者を除く法科大学院の中で、特に高い合格率を記録した大学院をランキング形式で紹介します。
| 順位 | 法科大学院名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 慶應義塾大学 | 246人 | 146人 | 59.35% |
| 2位 | 愛知大学 | 9人 | 5人 | 55.56% |
| 3位 | 京都大学 | 205人 | 101人 | 49.31% |
| 4位 | 一橋大学 | 82人 | 40人 | 48.78% |
| 5位 | 東京大学 | 255人 | 121人 | 47.45% |
| 6位 | 中央大学 | 290人 | 133人 | 45.86% |
| 7位 | 早稲田大学 | 330人 | 139人 | 42.12% |
| 8位 | 大阪大学 | 59人 | 24人 | 40.68% |
| 9位 | 神戸大学 | 96人 | 36人 | 37.50% |
| 10位 | 北海道大学 | 44人 | 16人 | 36.36% |
慶應義塾大法科大学院は合格率59.35%で、受験者の約6割が合格するという驚異的な実績を示しています。上位校では概ね40%以上の合格率を維持しており、全体の合格率42.13%を上回る結果となっています。
参考までに、予備試験合格者による司法試験合格率は92.84%(受験者475人、合格者441人)であり、法科大学院ルートを大きく上回る合格率となっています。予備試験に合格できれば、司法試験合格はほぼ確実と言える状況です。
司法試験の法科大学院別合格率の読み方と注意点
法科大学院別の合格率を見る際には、いくつかの注意点があります。単純に合格率だけで法科大学院の優劣を判断することは適切ではありません。
まず、受験者数の規模を考慮する必要があります。慶應義塾大、早稲田大、中央大、東京大などの大規模校は、200人以上の受験者を抱えながら高い合格率を維持していることが特筆すべき点です。一方で、受験者数が10人未満の小規模校の合格率は、少数のデータであるため変動しやすい傾向があります。
次に、既修コース(法学既修者向け2年制)と未修コース(法学未修者向け3年制)では合格率に大きな差があります。多くの法科大学院では、既修コース修了者の合格率が未修コース修了者を大きく上回っています。そのため、法科大学院全体の合格率だけでなく、コース別の合格率も確認することが重要です。
さらに、在学中受験と修了者受験でも合格率が異なります。令和6年度では、法科大学院在学中受験者の合格率が55.19%であるのに対し、修了者の合格率は22.73%と大きな開きがあります。在学中に高い実力を身につけて受験する学生の方が、合格率が高い傾向にあるのです。
司法試験における私立・国立法科大学院の合格率比較
私立法科大学院と国立法科大学院の合格率を比較すると、両者にそれぞれ特徴が見られます。
私立法科大学院では、慶應義塾大(59.35%)と早稲田大(42.12%)が高い合格率を維持しています。特に慶應義塾大は合格者数146人と最も多く、質・量ともにトップクラスの実績を誇ります。中央大も合格者数133人、合格率45.86%と健闘しており、私立大学の中で存在感を示しています。
一方、国立法科大学院では、京都大(49.31%)、一橋大(48.78%)、東京大(47.45%)がトップ3を形成しています。これらの大学は受験者数も多く、安定して高い合格率を維持している点が特徴です。地方の国立大学でも、大阪大(40.68%)、神戸大(37.50%)、北海道大(36.36%)などが堅実な実績を残しています。
私立と国立を比較すると、トップ校の合格率に大きな差はありません。むしろ、個々の法科大学院の教育体制や学習環境、学生の質が合格率を左右していると言えるでしょう。私立は規模が大きく多様な学生を受け入れている傾向があり、国立は少数精鋭で質の高い教育を提供している傾向があります。
司法試験の合格率に関してもっと詳しい記事はこちら
司法試験の合格率推移|法科大学院別・予備試験組の傾向分析
司法試験の法科大学院別合格者数ランキング(令和6年度)
合格率だけでなく、合格者数も法科大学院選びの重要な指標です。合格者数が多い法科大学院は、それだけ多くの法曹を輩出しており、卒業生ネットワークや就職支援体制が充実している傾向があります。
司法試験合格者数トップ10の法科大学院
令和6年度の司法試験における法科大学院別合格者数のトップ10は以下の通りです。
| 順位 | 法科大学院名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 慶應義塾大学 | 246人 | 146人 | 59.35% |
| 2位 | 早稲田大学 | 330人 | 139人 | 42.12% |
| 3位 | 中央大学 | 290人 | 133人 | 45.86% |
| 4位 | 東京大学 | 255人 | 121人 | 47.45% |
| 5位 | 京都大学 | 205人 | 101人 | 49.31% |
| 6位 | 一橋大学 | 82人 | 40人 | 48.78% |
| 7位 | 神戸大学 | 96人 | 36人 | 37.50% |
| 8位 | 明治大学 | 95人 | 30人 | 31.58% |
| 9位 | 同志社大学 | 91人 | 27人 | 29.67% |
| 10位 | 大阪大学 | 59人 | 24人 | 40.68% |
慶應義塾大が146人で1位、早稲田大が139人で2位、中央大が133人で3位と、私立大学の上位3校が100人以上の合格者を輩出しています。東京大と京都大も100人以上の合格者を出しており、名門国立大学の存在感も示されています。
なお、予備試験合格者による司法試験合格者数は441人であり、法科大学院別では最多となっています。予備試験ルートからの合格者数は年々増加しており、令和6年度は過去最高を記録しました。
司法試験の合格者数が多い法科大学院の特徴
合格者数が多い法科大学院には、いくつかの共通する特徴があります。
第一に、充実したカリキュラムと指導体制です。慶應義塾大、早稲田大、中央大などの大規模校は、多様な選択科目を提供し、学生のニーズに応じた柔軟な学習環境を整えています。また、専任教員の数も多く、きめ細かな指導を受けられる体制が整っています。
第二に、受験生同士の切磋琢磨の環境です。受験者数が多い法科大学院では、学生同士で議論したり、勉強会を開いたりする機会が豊富にあります。優秀な学生が多く集まることで、互いに刺激し合い、学習意欲を高め合うことができます。
第三に、充実した司法試験対策です。合格者を多く輩出している法科大学院は、過去の合格者のデータを蓄積し、効果的な試験対策を提供しています。答案練習会や模擬試験の実施、過去問の分析など、実践的なサポート体制が整っています。
第四に、卒業生ネットワークの強さです。多くの合格者を輩出している法科大学院は、法曹界に多数の卒業生を送り出しており、就職活動や実務修習の際に有利に働くことがあります。
司法試験における合格率と合格者数の関係
合格率と合格者数には、一定の相関関係がありますが、必ずしも比例するわけではありません。両者のバランスを理解することが、法科大学院選びには重要です。
慶應義塾大は合格率59.35%で1位、合格者数146人でも1位という、質・量ともに優れた実績を示しています。これは、受験者数246人という規模を維持しながら、高い教育水準を保っていることを意味します。
一方、京都大や東京大は、合格率では慶應義塾大に劣るものの、100人以上の合格者を安定して輩出しています。受験者数が多い中で、一定の合格率を維持できていることは評価に値します。
愛知大のように、合格率は55.56%と高いものの、受験者数が9人と少なく、合格者数は5人にとどまる例もあります。小規模校では、少数精鋭の教育を行っている反面、受験者の実力にばらつきがあると合格率が大きく変動する可能性があります。
合格率が高くても合格者数が少ない法科大学院と、合格率はやや低くても多数の合格者を輩出している法科大学院のどちらを選ぶかは、個人の状況や目標によって異なります。大規模校では多様な学習リソースと人的ネットワークが得られ、小規模校では手厚い個別指導を受けられる可能性があります。
司法試験と法科大学院の詳細に関してもっと詳しい記事はこちら
司法試験と法科大学院(ロースクール)|受験資格と選び方を解説
-
 スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら
スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら -
 司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら
司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら -
 合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
司法試験予備試験の大学別合格率ランキング(令和6年度)
司法試験の受験資格を得る方法の一つに、予備試験があります。予備試験は法科大学院に進学せずとも司法試験の受験資格を得られる制度であり、特に経済的・時間的負担を避けたい受験生に人気があります。令和6年度の予備試験では、大学別でどのような実績が出ているのでしょうか。
司法試験予備試験合格率トップ10の大学
令和6年度の司法試験予備試験における大学別合格率・合格者数のトップ10は以下の通りです。
| 順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 | 821人 | 97人 | 11.81% |
| 2位 | 一橋大学 | 200人 | 20人 | 10.00% |
| 3位 | 京都大学 | 336人 | 30人 | 8.93% |
| 4位 | 慶應義塾大学 | 857人 | 66人 | 7.70% |
| 5位 | 早稲田大学 | 844人 | 54人 | 6.40% |
| 6位 | 大阪大学 | 133人 | 7人 | 5.26% |
| 7位 | 神戸大学 | 115人 | 6人 | 5.22% |
| 8位 | 上智大学 | 120人 | 6人 | 5.00% |
| 9位 | 名古屋大学 | 84人 | 4人 | 4.76% |
| 10位 | 九州大学 | 84人 | 4人 | 4.76% |
東京大学が合格者数97人、合格率11.81%で圧倒的な1位となっています。予備試験全体の最終合格率が3.6%であることを考えると、東京大学の合格率は全体の約3.3倍と極めて高い水準です。
受験者数では中央大学が934人で最も多く、次いで慶應義塾大学857人、早稲田大学844人、東京大学821人と続いています。ただし、中央大学の合格者数は26人、合格率は2.78%と、受験者数の多さに比べて合格率は低めとなっています。
司法試験予備試験で東京大学が圧倒的に強い理由
東京大学が予備試験で圧倒的な実績を誇る理由は、複数の要因が考えられます。
第一に、入学時点での学力の高さです。東京大学に入学する学生は、高校時代から高い学力を持っており、法律学習においても高い理解力と論理的思考力を発揮します。予備試験は法律の専門知識だけでなく、論理的な思考力や文章力が問われるため、東京大学生の素地が活かされやすいのです。
第二に、充実した学習環境です。東京大学には法学部があり、法律学の専門教育を受けることができます。また、図書館や自習室などの学習施設が充実しており、司法試験や予備試験の受験生が集中して学習できる環境が整っています。
第三に、予備試験受験生コミュニティの存在です。東京大学には予備試験を目指す学生が多く、情報交換や勉強会が活発に行われています。先輩合格者からのアドバイスを受けやすく、効率的な学習方法を共有できる環境があります。
第四に、予備校との併用です。多くの東京大学生は、予備試験対策として専門の予備校を活用しています。大学での学習と予備校での実践的なトレーニングを組み合わせることで、高い合格率を実現しているのです。
ただし、東京大学生であっても予備試験の合格率は11.81%と決して高くはありません。予備試験は誰にとっても難関試験であり、継続的な努力が必要であることに変わりはありません。
司法試験予備試験の合格率と受験者数のバランス
予備試験の合格率を見る際には、受験者数とのバランスを考慮することが重要です。
東京大学、慶應義塾大学、早稲田大学は、いずれも800人以上の受験者を抱えており、その中で一定数の合格者を輩出しています。これらの大学では、予備試験を目指す学生層が厚く、切磋琢磨する環境が整っていると言えます。
一方、中央大学のように受験者数は多い(934人)ものの、合格率が2.78%と低い例もあります。これは、予備試験に挑戦する学生の裾野が広い反面、合格レベルに到達する学生の割合が相対的に少ないことを示しています。
一橋大学のように、受験者数200人で合格者20人、合格率10.00%という高い合格率を維持している例もあります。少数精鋭型の法学教育を行っている大学では、予備試験対策に集中できる環境が整っている可能性があります。
重要なのは、予備試験の合格率は大学だけでなく、個人の努力と学習方法に大きく左右されるという点です。難関大学に在籍していても、適切な学習計画を立て、継続的に努力しなければ合格は難しいのです。
司法試験の受験資格に関してもっと詳しい記事はこちら
司法試験の受験資格とは?法科大学院・予備試験ルートを解説
司法試験予備試験の大学別合格者数ランキング(令和6年度)
予備試験の合格者数は、各大学が法曹養成にどれだけ力を入れているかを示す指標の一つです。合格者数が多い大学では、予備試験対策のための情報やリソースが豊富にあり、受験生同士のネットワークも強固です。
司法試験予備試験合格者数トップ10の大学
令和6年度の司法試験予備試験における大学別合格者数のトップ10は以下の通りです。
| 順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 | 821人 | 97人 | 11.81% |
| 2位 | 慶應義塾大学 | 857人 | 66人 | 7.70% |
| 3位 | 早稲田大学 | 844人 | 54人 | 6.40% |
| 4位 | 京都大学 | 336人 | 30人 | 8.93% |
| 5位 | 中央大学 | 934人 | 26人 | 2.78% |
| 6位 | 一橋大学 | 200人 | 20人 | 10.00% |
| 7位 | 大阪大学 | 133人 | 7人 | 5.26% |
| 8位 | 上智大学 | 120人 | 6人 | 5.00% |
| 9位 | 神戸大学 | 115人 | 6人 | 5.22% |
| 10位 | 明治大学 | 272人 | 5人 | 1.84% |
東京大学が97人で圧倒的な1位、慶應義塾大学が66人で2位、早稲田大学が54人で3位と続いています。これらの大学は司法試験の法科大学院別でも上位にランクインしており、法曹養成において強い存在感を示しています。
令和6年度の予備試験全体の最終合格者数は449人ですから、上位3校だけで217人、全体の約48%を占めていることになります。難関大学に予備試験合格者が集中している傾向が明確です。
司法試験予備試験で合格者を多く輩出する大学の環境
予備試験で多くの合格者を輩出する大学には、共通する環境的特徴があります。
第一に、予備試験対策ゼミやサークルの存在です。東京大学、慶應義塾大学、早稲田大学などでは、予備試験を目指す学生同士が集まり、勉強会や答案練習会を開催しています。先輩合格者が後輩を指導する文化も根付いており、効率的な学習方法やノウハウが継承されています。
第二に、法学教育の質の高さです。これらの大学の法学部では、優秀な教員による質の高い講義が提供されています。基礎的な法律知識から応用的な論点まで、体系的に学ぶことができる環境が整っています。
第三に、予備校へのアクセスの良さです。東京や京都、大阪などの都市部にある大学では、司法試験予備校に通いやすい立地条件があります。大学での学習と予備校での実践的なトレーニングを両立しやすい環境が、合格率の向上につながっています。
第四に、法曹を目指す学生の多さです。予備試験を目指す学生が多い大学では、互いに刺激し合い、高いモチベーションを維持しやすい雰囲気があります。競争心と協力の精神が両立する環境が、合格者を生み出す土壌となっています。
司法試験予備試験における難関大学の優位性
予備試験において難関大学の学生が優位に立つ理由は、単に入学時の学力だけではありません。
まず、学習習慣と自己管理能力の高さが挙げられます。難関大学に合格するためには、高校時代から計画的な学習と自己管理が必要です。この能力は予備試験の学習においても活かされ、長期的な学習計画を立て、継続的に努力することができます。
次に、情報収集能力と分析力です。難関大学の学生は、膨大な情報の中から必要なものを選び取り、効率的に学習する能力に優れています。予備試験では多くの科目を学習する必要があるため、この能力が重要になります。
さらに、論理的思考力と文章表現力の高さも重要な要因です。予備試験の論文式試験では、法律知識だけでなく、論理的に思考し、それを明確に文章で表現する能力が求められます。難関大学の入試で培われたこれらの能力が、予備試験でも活かされるのです。
ただし、難関大学に在籍していることが予備試験合格を保証するわけではありません。東京大学でも合格率は11.81%であり、9割近くの受験者は不合格となっています。大学に関わらず、適切な学習方法と継続的な努力が合格には不可欠です。
司法試験予備校の活用に関してもっと詳しい記事はこちら
司法試験予備校の選び方|おすすめ予備校の費用・合格実績を比較
司法試験のトップ校詳細分析(慶應・東大・京大・早稲田)
司法試験において長年にわたり多数の合格者を輩出してきた名門校として、慶應義塾大学、東京大学、京都大学、早稲田大学の4校があります。これらの大学は法曹養成において中心的な役割を果たしており、それぞれに特徴的な強みがあります。
司法試験における慶應義塾大学の合格実績と強み
慶應義塾大学は、令和6年度の司法試験において合格者数146人、合格率59.35%で、法科大学院別のランキングで2冠を達成しました。過去5年間を見ても、常に合格者数・合格率ともにトップクラスの実績を維持しています。
慶應義塾大法科大学院の強みは、まず充実した教育体制にあります。実務家教員と研究者教員のバランスが良く、理論と実務の両面から法律を学ぶことができます。また、少人数教育を重視しており、学生一人ひとりに対するきめ細かな指導が行われています。
次に、予備試験ルートでも強い実績を示しています。令和6年度の予備試験では、慶應義塾大学から66人が合格しており、東京大学に次ぐ2位の合格者数です。法科大学院ルートと予備試験ルートの両方で優れた実績を持つことは、大学全体の法学教育の質の高さを示しています。
さらに、卒業生ネットワークの強さも特筆すべき点です。慶應義塾大学は長年にわたり多数の法曹を輩出しており、法曹界に強固なネットワークを持っています。司法修習や就職活動の際に、このネットワークが大きな力となります。
また、在学中受験制度を積極的に活用しており、令和6年度では在学中受験者からも多数の合格者を出しています。早期合格を目指す学生に対するサポート体制が充実していることがうかがえます。
司法試験における東京大学の合格実績と特徴
東京大学は、令和6年度の司法試験において法科大学院から121人の合格者を輩出し、合格率は47.45%でした。また、予備試験では97人が合格し、合格者数・合格率ともに全国1位という圧倒的な実績を示しています。
東京大学の特徴は、予備試験ルートでの強さです。予備試験合格者数97人は、2位の慶應義塾大学(66人)を大きく引き離しています。東京大学の学生は、法科大学院に進学せず予備試験ルートで司法試験を目指す傾向が強く、その多くが成功を収めています。
東京大学法学部の教育水準の高さも、合格実績を支える要因です。日本の法学教育の最高峰として、理論的な深さと実践的な応用力を兼ね備えた法学教育を提供しています。また、優秀な学生が集まることで、学生同士の議論が活発であり、互いに高め合う環境が整っています。
さらに、東京大学には司法試験や予備試験に関する豊富な情報とノウハウが蓄積されています。過去の合格者からのアドバイスや、効果的な学習方法に関する情報を得やすい環境があります。
ただし、東京大学法科大学院の合格率47.45%は、慶應義塾大学の59.35%と比べるとやや低めです。これは、東京大学の学生の多くが予備試験ルートを選択し、法科大学院には相対的に少数が進学することが影響していると考えられます。
司法試験における京都大学・早稲田大学の実績
京都大学法科大学院は、令和6年度の司法試験において合格者数101人、合格率49.31%という優れた実績を示しました。関西地区では最も高い合格実績を持ち、全国でも上位に位置しています。
京都大学の強みは、理論と実務のバランスの取れた教育です。研究者教員による深い理論教育と、実務家教員による実践的な指導が組み合わされ、法律家として必要な能力を総合的に養成しています。また、少人数教育を重視しており、教員と学生の距離が近い環境が特徴です。
予備試験でも、京都大学は合格者30人、合格率8.93%と健闘しています。関西地区の大学の中では最も高い実績であり、京都大学全体の法学教育の質の高さがうかがえます。
早稲田大学法科大学院は、令和6年度の司法試験において合格者数139人、合格率42.12%という実績を残しました。合格者数では全国2位であり、多数の法曹を輩出し続けています。
早稲田大学の特徴は、大規模校ならではの多様性と充実した教育リソースです。学生数が多いため、様々なバックグラウンドを持つ学生が集まり、多角的な議論が行われます。また、選択科目が豊富であり、学生の関心に応じた専門的な学習が可能です。
予備試験でも、早稲田大学は合格者54人、合格率6.40%と一定の実績を維持しています。私立大学の中では慶應義塾大学に次ぐ実績であり、予備試験を目指す学生も多数在籍しています。
司法試験の大学別合格者数の推移(過去5年間)
司法試験の合格者数は、制度改正や社会情勢の影響を受けて変動してきました。過去5年間の推移を見ることで、司法試験を取り巻く環境の変化を理解することができます。
司法試験における法科大学院別合格者数の変動
過去5年間の司法試験全体の合格者数と合格率の推移は以下の通りです。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2020年(令和2年) | 3,703人 | 1,450人 | 39.2% |
| 2021年(令和3年) | 3,424人 | 1,421人 | 41.5% |
| 2022年(令和4年) | 3,082人 | 1,403人 | 45.5% |
| 2023年(令和5年) | 3,928人 | 1,781人 | 45.3% |
| 2024年(令和6年) | 3,779人 | 1,592人 | 42.1% |
令和2年から令和4年にかけて、受験者数は減少傾向にありました。これは法科大学院への進学者数の減少や、司法試験の受験回数制限(5年5回)により受験資格を失う者が増えたことが影響しています。
しかし、令和5年には受験者数が3,928人と大幅に増加しました。これは在学中受験制度の導入により、法科大学院の在学生も司法試験を受験できるようになったためです。令和6年は3,779人とやや減少しましたが、在学中受験制度導入前の水準よりは高い受験者数を維持しています。
合格者数は、令和5年に1,781人と大きく増加しましたが、令和6年は1,592人と減少しました。これは、在学中受験制度導入初年度の令和5年に一時的に受験者数が増えた影響が落ち着いたためと考えられます。
法科大学院別で見ると、慶應義塾大学、早稲田大学、中央大学、東京大学、京都大学などの上位校は、毎年安定して多数の合格者を輩出しています。これらの大学は、制度改正や受験者数の変動にかかわらず、高い教育水準を維持していることがわかります。
司法試験の在学中受験制度導入による影響
令和5年度から導入された在学中受験制度は、司法試験に大きな影響を与えています。
在学中受験制度とは、法科大学院の最終学年に在籍する学生が、修了前に司法試験を受験できる制度です。従来は法科大学院を修了してから受験する必要がありましたが、この制度により早期合格が可能になりました。
令和6年度の在学中受験者の実績は以下の通りです。
- 受験者数:1,232人
- 合格者数:680人
- 合格率:55.19%
一方、法科大学院修了者の実績は以下の通りです。
- 受験者数:2,072人
- 合格者数:471人
- 合格率:22.73%
在学中受験者の合格率55.19%は、修了者の合格率22.73%を大きく上回っています。これは、在学中受験者が法科大学院での学習が新鮮なうちに受験し、高い実力を発揮できていることを示しています。
この制度導入により、法科大学院生は早期に司法試験に合格できるチャンスを得ることができるようになりました。合格すれば、法科大学院修了後すぐに司法修習に進むことができ、法曹としてのキャリアを早期にスタートできます。
ただし、在学中受験に失敗した場合、法科大学院修了後に再度受験することになります。在学中受験を選択するかどうかは、個人の実力や学習の進捗状況を見極めて判断する必要があります。
司法試験の予備試験合格者数の増加傾向
予備試験合格者による司法試験合格者数は、年々増加しています。
| 年度 | 予備試験経由の司法試験受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2020年(令和2年) | 385人 | 353人 | 91.7% |
| 2021年(令和3年) | 406人 | 374人 | 92.1% |
| 2022年(令和4年) | 367人 | 331人 | 90.2% |
| 2023年(令和5年) | 353人 | 327人 | 92.6% |
| 2024年(令和6年) | 475人 | 441人 | 92.8% |
令和6年度の予備試験経由の司法試験合格者数は441人で、過去最高を記録しました。受験者数も475人と増加しており、予備試験ルートの人気が高まっていることがわかります。
予備試験ルートの合格率は常に90%以上を維持しており、予備試験に合格できれば司法試験もほぼ確実に合格できることを示しています。このため、法科大学院に進学せず、予備試験ルートで司法試験を目指す学生が増えています。
予備試験合格者が増加している背景には、いくつかの要因があります。第一に、法科大学院に進学するには時間的・経済的コストがかかるため、予備試験ルートを選択する学生が増えています。第二に、予備試験専門の予備校が充実し、効率的な学習方法が確立されてきたことも影響しています。第三に、予備試験合格者は就職市場で高く評価される傾向があり、そのメリットを狙う学生も増えています。
ただし、予備試験そのものの合格率は3〜4%程度と極めて低く、合格するには相当の努力が必要です。予備試験の短答式試験、論文式試験、口述試験のすべてに合格する必要があり、長期的な学習計画と継続的な努力が求められます。
司法試験の法科大学院における既修・未修コース別合格率
法科大学院には、既修コース(法学既修者向け2年制)と未修コース(法学未修者向け3年制)の2つのコースがあります。両コースでは、司法試験の合格率に大きな差が見られます。
司法試験の既修コースと未修コースの合格率差
既修コースと未修コースの合格率には、大きな開きがあります。令和6年度の具体的なデータは公表されていませんが、過去のデータから以下のような傾向が読み取れます。
既修コース修了者の累積合格率(5年以内の合格率)は、おおむね60〜75%程度です。一方、未修コース修了者の累積合格率は、30〜40%程度と、既修コースの半分程度にとどまっています。
この差が生じる主な理由は、法律学習のスタート地点の違いです。既修コースの学生は、法学部出身者が多く、すでに法律の基礎知識を持っています。そのため、法科大学院では応用的な学習に集中でき、司法試験に必要な実力を効率的に養成できます。
一方、未修コースの学生は、法学部以外の学部出身者が多く、法律学習は法科大学院入学後に始めます。3年間で基礎から応用まで学ぶ必要があるため、既修コースの学生と比べて学習の負担が大きくなります。
また、未修コースでは、1年次に法律の基礎を学ぶため、実践的な試験対策に割ける時間が既修コースより少なくなります。司法試験は応用力や論述力が求められる試験であるため、この時間の差が合格率の差につながっていると考えられます。
司法試験における既修コース選択のメリット
既修コースを選択することには、いくつかのメリットがあります。
第一に、学習期間が短いことです。既修コースは2年制であるため、未修コースの3年制と比べて1年早く修了できます。これにより、経済的負担を軽減できるだけでなく、法曹としてのキャリアを早期にスタートできます。
第二に、合格率が高いことです。前述の通り、既修コースの累積合格率は未修コースを大きく上回っています。法律の基礎知識を持った状態で入学するため、効率的に学習を進められ、司法試験合格に直結する実力を養成しやすいのです。
第三に、学習内容が充実していることです。既修コースでは基礎知識があることを前提に、より高度で実践的な内容を学ぶことができます。判例研究や実務演習など、司法試験や実務に直結する学習に多くの時間を割くことができます。
第四に、在学中受験制度を利用しやすいことです。既修コースは2年制であるため、2年次に在学中受験に挑戦することができます。合格すれば、修了後すぐに司法修習に進むことができ、最短ルートでの法曹資格取得が可能になります。
ただし、既修コースに入学するには、法科大学院入試で法律科目の試験に合格する必要があります。法学部出身者であっても、十分な準備をしないと合格は難しいでしょう。
司法試験で未修コースから合格する学習戦略
未修コースからの司法試験合格は難しいとされていますが、適切な学習戦略を立てることで合格は十分に可能です。
第一に、基礎固めを徹底することです。未修コースの1年次は、法律の基礎を学ぶ重要な時期です。この時期に基本的な法律知識をしっかりと身につけることが、その後の学習の土台となります。基本書を繰り返し読み、基礎的な概念や原則を完全に理解することが重要です。
第二に、早期から論文対策を始めることです。司法試験の論文式試験は、単なる知識の暗記では対応できません。法律的な思考力と論述力を養成するには、長期間の訓練が必要です。1年次から判例を読み込み、論文形式の答案を書く練習を始めることをおすすめします。
第三に、予備校の活用を検討することです。法科大学院のカリキュラムだけでは、司法試験合格に必要な実力を養成するのが難しい場合があります。司法試験専門の予備校を併用することで、効率的な学習方法や答案作成のテクニックを学ぶことができます。
第四に、学習時間を十分に確保することです。未修コースでは、既修コースの学生よりも多くの学習時間が必要です。アルバイトや課外活動を制限し、学習に集中できる環境を作ることが重要です。
第五に、在学中受験のタイミングを慎重に判断することです。未修コースの場合、3年次に在学中受験に挑戦するか、修了後に受験するか選択できます。実力が十分についていない状態で在学中受験に失敗すると、貴重な受験機会を1回失うことになります。自分の実力を客観的に評価し、適切なタイミングで受験することが重要です。
司法試験に強い大学・法科大学院を選ぶポイント
司法試験合格を目指す上で、どの大学や法科大学院を選ぶかは重要な決断です。ただし、単純に合格率や合格者数だけで選ぶのではなく、多角的な視点から検討することが必要です。
司法試験の合格率だけで法科大学院を選ぶべきではない理由
法科大学院を選ぶ際、合格率が高い大学院を選びたくなるのは自然なことです。しかし、合格率だけに注目することには、いくつかの問題があります。
第一に、受験者数が少ない法科大学院では、合格率が変動しやすい点です。受験者が10人未満の小規模校では、1人2人の合否で合格率が大きく変わります。そのため、ある年に高い合格率を記録しても、翌年は大きく下がる可能性があります。
第二に、合格率が高い法科大学院は競争が激しく、入学自体が難しい点です。慶應義塾大や東京大などの高合格率の法科大学院は、入試の難易度も非常に高く、合格するには相当の準備が必要です。入学できなければ、その合格率の恩恵を受けることはできません。
第三に、自分に合った学習環境かどうかは、合格率だけではわからない点です。大規模校と小規模校では、教育スタイルや学習環境が大きく異なります。合格率が高くても、自分の学習スタイルに合わなければ、十分な学習効果を得られない可能性があります。
第四に、立地や学費などの実際的な条件も重要である点です。合格率が高い法科大学院でも、自宅から通えない距離にあったり、学費が高額で経済的負担が大きかったりする場合、継続的な学習が困難になる可能性があります。
そのため、合格率は参考にしつつも、それだけで決めるのではなく、総合的に判断することが重要です。
司法試験合格に向けた法科大学院の学習環境と支援体制
法科大学院を選ぶ際には、学習環境と支援体制を詳しく確認することが重要です。
第一に、教員の質と数を確認しましょう。専任教員の数が多く、少人数教育が行われている法科大学院では、きめ細かな指導を受けられます。また、実務家教員と研究者教員のバランスも重要です。実務家教員からは実践的な知識を、研究者教員からは理論的な深さを学ぶことができます。
第二に、カリキュラムの充実度を確認しましょう。司法試験の科目をカバーするだけでなく、選択科目が豊富に用意されているか、実務演習や模擬裁判などの実践的なカリキュラムがあるかを確認することが重要です。
第三に、学習施設の充実度を確認しましょう。自習室や図書館が整備されており、長時間学習できる環境があるかどうかは重要なポイントです。また、法律データベースへのアクセスなど、学習に必要なリソースが十分に提供されているかも確認しましょう。
第四に、司法試験対策のサポート体制を確認しましょう。答案添削の機会が豊富にあるか、模擬試験が実施されているか、過去の合格者からのアドバイスを受けられる仕組みがあるかなどを確認することが重要です。
第五に、学生同士の交流やゼミ活動が活発かどうかを確認しましょう。優秀な学生同士で議論したり、勉強会を開いたりする文化がある法科大学院では、互いに高め合うことができます。
司法試験における立地・学費・カリキュラムの比較
法科大学院を選ぶ際には、実際的な条件も重要な判断材料となります。
立地について、都市部の法科大学院は予備校へのアクセスが良く、法律事務所でのアルバイトやインターンシップの機会も豊富です。一方、地方の法科大学院は生活費が安く、落ち着いた環境で学習に集中できるメリットがあります。自宅から通えるかどうかも重要なポイントです。下宿する場合は、家賃や生活費も考慮に入れる必要があります。
学費について、国立法科大学院は年間約80万円程度、私立法科大学院は年間100万円〜150万円程度が一般的です。既修コースなら2年間、未修コースなら3年間の学費が必要になるため、総額では200万円〜450万円程度の差が生じます。奨学金制度の有無や充実度も確認しましょう。多くの法科大学院では、成績優秀者に対する給付型奨学金を用意しています。
カリキュラムについて、法科大学院によって重点を置く分野や教育方法が異なります。実務重視のカリキュラムを組んでいる法科大学院もあれば、理論的な学習を重視する法科大学院もあります。また、在学中受験を積極的に推奨している法科大学院と、修了後の受験を推奨している法科大学院があります。自分の目標や学習スタイルに合ったカリキュラムを選ぶことが重要です。
これらの要素を総合的に比較し、自分にとって最適な法科大学院を選ぶことが、司法試験合格への第一歩となります。
司法試験の難関大学以外からの合格事例
司法試験は難関大学出身者が有利とされていますが、それ以外の大学からも多くの合格者が輩出されています。適切な学習方法と強い意志があれば、どの大学からでも合格は可能です。
司法試験は大学の偏差値だけで決まらない理由
司法試験の合格は、大学の偏差値だけで決まるものではありません。いくつかの理由があります。
第一に、司法試験は大学入試とは異なる試験であることです。大学入試では幅広い科目の知識が問われますが、司法試験は法律の専門知識と応用力が中心です。大学入試の成績が良くても、法律学習に向いていない人もいれば、逆に大学入試では目立たなくても、法律学習で才能を発揮する人もいます。
第二に、努力の積み重ねが結果を左右することです。司法試験に合格するには、長期間にわたる継続的な学習が必要です。難関大学に入学した後に油断して学習を怠れば合格できませんし、中堅大学でも真摯に学習を続ければ合格できます。
第三に、法科大学院での学習が重要であることです。法科大学院に入学してからの2〜3年間の学習が、司法試験合格の可否を大きく左右します。出身大学にかかわらず、法科大学院で真剣に学習すれば、司法試験に必要な実力を身につけることができます。
第四に、予備校の活用で学習効率を高められることです。司法試験専門の予備校では、効率的な学習方法や答案作成のテクニックを学ぶことができます。大学のブランドよりも、適切な学習方法を身につけることの方が重要です。
実際、中堅法科大学院からも毎年一定数の合格者が輩出されています。大学のブランドに過度にこだわるのではなく、自分の実力向上に集中することが重要です。
司法試験で中堅法科大学院から合格するための戦略
中堅法科大学院から司法試験に合格するには、トップ校の学生以上の努力と工夫が必要です。
第一に、基礎の徹底です。難関法科大学院の学生は、すでに高い法律知識を持っていることが多いですが、中堅校の学生は基礎から丁寧に学ぶ必要があります。焦らず、一つひとつの概念を完全に理解することが重要です。
第二に、予備校の積極的な活用です。法科大学院の授業だけでは不十分な場合、予備校の講座を受講することで学習効率を高めることができます。特に、答案作成のテクニックや出題傾向の分析など、予備校が得意とする分野は積極的に活用しましょう。
第三に、学習時間の確保です。トップ校の学生と同等以上の実力をつけるには、より多くの学習時間が必要です。アルバイトや課外活動を最小限に抑え、学習に集中できる環境を作ることが重要です。
第四に、外部の勉強会やゼミへの参加です。中堅法科大学院では、学生同士の議論の機会が限られている場合があります。他の法科大学院の学生と交流したり、外部の勉強会に参加したりすることで、多様な視点を得ることができます。
第五に、過去問の徹底的な分析です。司法試験の過去問を繰り返し解き、出題傾向や求められる答案のレベルを把握することが重要です。模範解答を研究し、自分の答案と比較することで、改善点を見つけることができます。
第六に、メンタル面の強化です。周囲に合格者が少ない環境では、孤独を感じたり、自信を失ったりすることがあります。しかし、自分を信じて学習を続けることが、最終的な合格につながります。
司法試験予備校の活用が合否を分ける要因
司法試験において、予備校の活用は合否を大きく左右する要因の一つです。
予備校のメリットは、まず効率的な学習方法を学べることです。司法試験専門の講師は、合格に必要な知識とスキルを熟知しており、短期間で効率的に学習する方法を教えてくれます。独学では気づきにくい学習のポイントや、答案作成のテクニックを学ぶことができます。
次に、充実した教材とカリキュラムです。予備校では、司法試験に特化した教材を提供しており、体系的に学習を進めることができます。また、答案練習会や模擬試験など、実践的なトレーニングの機会も豊富です。
さらに、答案添削サービスも重要です。自分の答案を専門家に添削してもらうことで、改善点を具体的に把握することができます。法科大学院でも答案添削は行われますが、予備校では司法試験に特化した視点から添削を受けられます。
また、最新の出題傾向の分析も予備校の強みです。司法試験の出題傾向は年々変化しており、最新の情報をキャッチアップすることが重要です。予備校では、過去の試験を詳細に分析し、今後の出題傾向を予測しています。
ただし、予備校に通えば自動的に合格できるわけではありません。予備校はあくまでも学習をサポートするツールであり、最終的には自分自身の努力が合否を決めます。予備校の講座を受講するだけでなく、自分で復習し、理解を深めることが重要です。
また、予備校の費用も考慮する必要があります。司法試験対策の予備校講座は、数十万円から100万円以上かかることもあります。経済的な負担を考慮しながら、自分に必要な講座を選択することが重要です。
司法試験予備校の選び方に関してもっと詳しい記事はこちら
司法試験予備校の選び方|おすすめ予備校の費用・合格実績を比較
司法試験の大学別ランキングに関連するよくある質問(FAQ)
司法試験の大学別ランキングについて、受験生からよく寄せられる質問をまとめました。
Q. 司法試験に強い大学はどこですか?
司法試験に強い大学は、法科大学院ルートと予備試験ルートで異なります。
法科大学院ルートでは、令和6年度の実績において、慶應義塾大法科大学院が合格者数146人、合格率59.35%で最も優れた実績を示しています。次いで、早稲田大法科大学院が合格者数139人、東京大法科大学院が121人、中央大法科大学院が133人と続いています。合格率では、京都大法科大学院(49.31%)、一橋大法科大学院(48.78%)も高い水準を維持しています。
予備試験ルートでは、東京大学が合格者数97人、合格率11.81%で圧倒的な実績を誇ります。次いで、慶應義塾大学が合格者数66人、早稲田大学が54人、京都大学が30人と続いています。
ただし、「強い大学」に入学すれば自動的に合格できるわけではありません。どの大学・法科大学院でも、継続的な努力が必要です。
Q. 司法試験の合格率が高い法科大学院に入れば合格しやすいですか?
合格率が高い法科大学院に入学することは、司法試験合格に有利に働く可能性がありますが、それだけで合格が保証されるわけではありません。
合格率が高い法科大学院には、いくつかの共通点があります。教育水準が高く、優秀な学生が集まっており、学習環境が整っています。こうした環境で学ぶことは、司法試験合格に向けた実力養成に役立ちます。
しかし、合格率が高い法科大学院でも、すべての学生が合格するわけではありません。慶應義塾大法科大学院の合格率59.35%は高水準ですが、逆に言えば約4割の学生は不合格となっています。
重要なのは、法科大学院に入学してからの学習態度です。合格率が高い法科大学院に入っても、油断して学習を怠れば合格できません。逆に、合格率がそれほど高くない法科大学院でも、真剣に学習すれば合格できます。
法科大学院選びは重要ですが、最終的には自分自身の努力が合否を決めることを忘れないでください。
Q. 司法試験予備試験は東大や早慶でないと合格できませんか?
予備試験の合格者は東京大学、慶應義塾大学、早稲田大学などの難関大学に集中していますが、それ以外の大学からも合格者は出ています。
令和6年度の予備試験では、東京大学から97人、慶應義塾大学から66人、早稲田大学から54人が合格していますが、京都大学、一橋大学、大阪大学、中央大学など、他の大学からも合格者が出ています。また、大学在学中ではなく、社会人や法科大学院生からの合格者もいます。
予備試験は確かに難関試験であり、難関大学の学生が有利であることは事実です。しかし、適切な学習方法と継続的な努力があれば、どの大学からでも合格は可能です。
重要なのは、早期から計画的に学習を始めることです。予備試験に合格するには、3,000時間以上の学習時間が必要とされています。大学1年生から学習を始め、3〜4年かけて実力をつけることで、合格の可能性を高めることができます。
また、予備校の活用も効果的です。独学では限界がある場合、予備試験専門の予備校を利用することで、効率的に学習を進めることができます。
Q. 司法試験の法科大学院は既修と未修どちらを選ぶべきですか?
既修コースと未修コースのどちらを選ぶべきかは、あなたのバックグラウンドと目標によって異なります。
法学部出身者は、既修コースを選択することをおすすめします。既修コースは2年制で、合格率も未修コースより高い傾向があります。法律の基礎知識を持っているため、効率的に学習を進め、早期に司法試験合格を目指すことができます。
法学部以外の学部出身者は、未修コースから始めることが一般的です。未修コースは3年制で、1年次に法律の基礎から学ぶことができます。法律学習が初めてでも、段階的に実力をつけることができます。
ただし、法学部以外の学部出身者でも、法科大学院入学前に独学や予備校で法律を学習し、既修コース入試に合格する人もいます。1年間の学習期間を短縮できるため、時間的・経済的なメリットがあります。
既修コースと未修コースの選択は、自分の現在の法律知識のレベル、経済的な状況、目標とする合格時期などを総合的に考慮して決めるべきです。法科大学院のオープンキャンパスや説明会に参加し、詳しい情報を収集することをおすすめします。
Q. 司法試験の大学別ランキングで地方大学の実績はどうですか?
地方大学の法科大学院も、着実に司法試験合格者を輩出しています。
令和6年度の実績を見ると、北海道大学法科大学院が合格者16人(合格率36.36%)、東北大学法科大学院が合格者13人(合格率28.89%)、名古屋大学法科大学院が合格者15人(合格率26.32%)、大阪大学法科大学院が合格者24人(合格率40.68%)、神戸大学法科大学院が合格者36人(合格率37.50%)、九州大学法科大学院が合格者15人(合格率31.25%)という実績を残しています。
これらの地方国立大学は、東京や京都の名門校と比べると合格者数は少ないものの、一定の合格率を維持しています。地方に住んでいる受験生にとって、地元の国立大学法科大学院は、経済的負担を抑えながら司法試験を目指せる有力な選択肢です。
地方大学の法科大学院のメリットは、生活費が安く、落ち着いた環境で学習に集中できることです。また、地域の法曹界とのつながりが強く、地元での就職を考えている場合には有利に働くこともあります。
ただし、地方大学では学生数が少なく、議論の機会や情報量が東京の大規模校と比べて限られる場合があります。そのため、外部の勉強会に参加したり、オンラインで情報を収集したりする努力が必要です。
Q. 司法試験の合格者数が多い大学を選ぶメリットは何ですか?
司法試験の合格者数が多い大学を選ぶことには、いくつかのメリットがあります。
第一に、充実した司法試験対策です。合格者を多く輩出している大学・法科大学院は、長年の経験とノウハウを蓄積しています。効果的な学習方法や答案作成のテクニックを学ぶ機会が豊富にあります。
第二に、学生同士の切磋琢磨の環境です。合格者数が多いということは、優秀な学生が多く集まっているということです。互いに議論したり、勉強会を開いたりすることで、実力を高め合うことができます。
第三に、卒業生ネットワークの強さです。多くの合格者を輩出している大学は、法曹界に多数の卒業生がいます。司法修習や就職活動の際に、先輩からアドバイスを受けたり、人脈を活用したりできる可能性があります。
第四に、豊富な学習リソースです。合格者数が多い大学・法科大学院は、規模が大きく、図書館や自習室などの学習施設が充実しています。また、多様な選択科目や実務演習の機会も豊富です。
ただし、合格者数が多い大学に入学すれば自動的に合格できるわけではありません。競争も激しく、努力を怠れば合格は難しくなります。これらのメリットを活かすには、自分自身の継続的な努力が不可欠です。
まとめ:司法試験の大学別ランキングと法科大学院選びの考え方
本記事では、司法試験の大学別合格率ランキングと合格者数について、令和6年度の最新データを詳しく解説しました。重要なポイントを改めて確認しましょう。
- 法科大学院別の実績格差:令和6年度の司法試験において、慶應義塾大法科大学院は合格者数146人、合格率59.35%で2冠を達成しました。一方で、合格者を出せなかった法科大学院も8校あり、法科大学院間の実績には大きな差があります。予備試験ルートの合格率92.84%は圧倒的に高く、法科大学院ルートとは大きく異なる特徴を持っています。
- 予備試験の大学別実績:予備試験では東京大学が合格者数97人、合格率11.81%で圧倒的な実績を示しています。難関大学に合格者が集中していますが、適切な学習方法と継続的な努力があれば、どの大学からでも合格は可能です。予備試験全体の合格率は3.6%と極めて低く、長期的な学習計画が必要です。
- 合格率以外の重要な要素:法科大学院選びでは、合格率だけでなく、立地、学費、カリキュラム、学習環境、支援体制など、多角的な要素を考慮することが重要です。自分に合った法科大学院を選び、継続的に努力することが、司法試験合格への近道となります。
司法試験の大学別ランキングを理解できたら、次は具体的な受験準備を始めましょう。司法試験の効果的な勉強法と司法試験に必要な勉強時間を参考に、計画的に学習を進めることをおすすめします。
本記事を通じて、司法試験における大学別・法科大学院別の合格実績と、法科大学院選びのポイントを理解いただけたはずです。これらの情報を活用して、司法試験合格に向けた確かな一歩を踏み出しましょう。
-
 スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら
スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら -
 司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら
司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら -
 合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
司法試験の関連記事

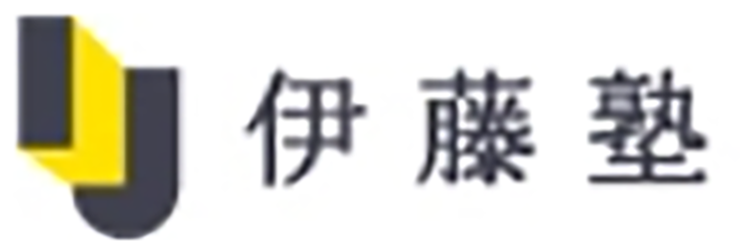


コメント