司法試験の日程について知りたいあなたへ。「いつ願書を入手すればいいのか」「試験はいつ実施されるのか」「合格発表はいつ確認できるのか」といった疑問は、年間スケジュールを正しく把握することで解決できます。
本記事では、司法試験の願書交付から出願、試験実施、合格発表までの詳細な日程、試験会場の選び方、合格後のスケジュールについて、2025年・2026年の最新情報を交えて詳しく解説します。この情報をもとに、司法試験合格に向けて、計画的な準備を進めましょう。
- 司法試験の年間スケジュール(願書交付・出願・試験実施・合格発表の時期)
- 願書の入手方法と出願に必要な書類の詳細
- 4日間の試験実施スケジュールと時間割
- 合格発表の確認方法と合格後の流れ
- 願書交付は3月上旬から:司法試験の願書交付期間は例年3月上旬から4月上旬で、郵送請求や法科大学院経由で入手できます。出願期間は3月下旬から4月上旬の約10日間と短いため、早めの準備が重要です。
- 試験は7月に4日間実施:司法試験は年1回、7月に4日間の日程で実施されます。1日目に選択科目と公法系、2日目に民事系、3日目に刑事系の論文式試験があり、4日目に短答式試験が行われます。中日(休息日)を含めた5日間のスケジュール管理が合格の鍵となります。
- 合格発表は11月中旬:短答式試験の合格発表は8月上旬、最終合格発表は11月中旬に法務省ホームページで公表されます。合格後は翌年12月から始まる司法修習の申し込み期限があるため、スケジュールを把握しておく必要があります。
-
 スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら
スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら -
 司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら
司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら -
 合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
司法試験の年間スケジュール|2025年・2026年の実施日程
司法試験の年間スケジュールを把握することは、計画的な受験準備の第一歩です。司法試験は年1回の実施で、願書交付から最終合格発表まで約8か月のスケジュールとなります。ここでは、2025年と2026年の具体的な日程を確認しましょう。
2025年(令和7年)司法試験の日程一覧
2025年の司法試験は、以下のスケジュールで実施されます。
- 願書交付期間:2025年3月7日(金)~4月7日(月)
- 出願期間:2025年3月28日(金)~4月7日(月)消印有効
- 受験票発送:2025年6月下旬
- 試験実施日:2025年7月9日(水)~7月12日(土)
- 1日目:7月9日(水)論文式試験(選択科目・公法系)
- 2日目:7月10日(木)論文式試験(民事系)
- 中日:7月11日(金)休息日
- 3日目:7月12日(土)論文式試験(刑事系)
- 4日目:7月13日(日)短答式試験
- 短答式試験合格発表:2025年8月6日(水)予定
- 最終合格発表:2025年11月12日(水)予定
2025年の試験日程は、例年通り7月上旬から中旬にかけて実施されます。願書交付から出願までの期間が約1か月と短いため、受験を検討している方は早めに準備を始めることをおすすめします。
2026年(令和8年)司法試験の日程一覧
2026年の司法試験は、以下のスケジュールで実施される見込みです。
- 願書交付期間:2026年3月上旬~4月上旬(予定)
- 出願期間:2026年3月下旬~4月上旬(予定)消印有効
- 受験票発送:2026年6月下旬(予定)
- 試験実施日:2026年7月上旬~中旬(予定)
- 4日間の日程(水曜日~土曜日を想定)
- 論文式試験3日間、短答式試験1日間
- 短答式試験合格発表:2026年8月上旬(予定)
- 最終合格発表:2026年11月中旬(予定)
2026年の具体的な日程は、2025年秋頃に法務省から正式に発表される予定です。例年、前年と同様のスケジュールで実施されるため、2025年の日程を参考にして計画を立てることができます。
司法試験は年1回・7月実施が基本
司法試験は年に1回のみ実施される試験です。他の国家試験と比較しても、受験機会が限られているため、1回の試験に向けて万全の準備が必要となります。
試験実施時期は例年7月上旬から中旬の水曜日から日曜日にかけて設定されています。これは、法科大学院の修了時期(3月)から試験までの準備期間を確保し、合格発表後に翌年12月から始まる司法修習への移行をスムーズにするためのスケジュールです。
また、司法試験には5年5回の受験回数制限があります。法科大学院修了または予備試験合格後5年以内に5回まで受験できる制度となっているため、年1回の試験機会を無駄にしないよう、計画的な準備が求められます。
司法試験の基本情報については、試験制度全体の詳細を解説していますので、あわせてご確認ください。
司法試験の制度に関してもっと詳しい記事はこちら
司法試験とは?試験制度・受験資格・合格後の流れを徹底解説
司法試験の願書交付期間と入手方法
司法試験の受験には、まず願書(受験願書)を入手する必要があります。願書交付期間は限られているため、早めの準備が重要です。ここでは、願書の交付期間と入手方法について詳しく解説します。
願書交付期間(3月上旬~4月上旬)
司法試験の願書交付期間は、例年3月上旬から4月上旬までの約1か月間です。2025年の場合、3月7日(金)から4月7日(月)までとなっています。
願書は無料で交付されますが、郵送で請求する場合は返信用の郵送料(切手代)が必要となります。願書の交付開始日は法務省のホームページで正式に発表されるため、受験を予定している方は2月下旬頃から法務省の情報をチェックしておくことをおすすめします。
願書交付期間と出願期間は重複していますが、出願期間は約10日間と非常に短いため、願書交付開始と同時に入手手続きを始めることが重要です。特に郵送で請求する場合は、往復の郵送日数を考慮して余裕を持って準備しましょう。
郵送で願書を請求する方法
郵送で願書を請求する場合は、以下の手順で手続きを行います。
まず、返信用封筒を準備します。角形2号(A4サイズが入る大きさ)の封筒に、自分の住所・氏名・郵便番号を明記し、140円分の切手を貼付します。次に、この返信用封筒を別の送付用封筒に入れ、表面に「司法試験受験願書請求」と朱書きして、法務省司法試験委員会宛に郵送します。
請求から受け取りまでに1週間程度かかる場合があるため、願書交付開始日から余裕を持って請求することが大切です。特に出願期限が近づくと郵便の遅延リスクもあるため、早めの行動を心がけましょう。
法科大学院経由で願書を入手する方法
法科大学院に在籍している学生や修了生は、所属する法科大学院を通じて願書を入手することができます。多くの法科大学院では、願書交付開始と同時に学生向けに願書を配布する体制を整えています。
法科大学院経由での入手は、郵送の手間や時間がかからないため、最も確実で便利な方法です。所属する法科大学院の教務課や学生支援課に問い合わせて、配布スケジュールと受け取り方法を確認しましょう。
修了生の場合でも、一定期間は法科大学院から願書を受け取れる場合があります。修了後の支援体制は各法科大学院によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
法務省で直接受け取る方法
東京近郊に在住している方は、法務省で直接願書を受け取ることも可能です。法務省司法試験委員会の窓口で、願書交付期間中に受け取ることができます。
直接受け取りの場合は、郵送の日数を気にする必要がなく、その場で願書の内容を確認できるメリットがあります。ただし、受付時間が平日の日中に限られているため、仕事をしている方や遠方に住んでいる方には郵送または法科大学院経由での入手が現実的です。
受け取りの際は、念のため身分証明書を持参すると安心です。また、窓口の混雑状況によっては待ち時間が発生する可能性もあるため、時間に余裕を持って訪問しましょう。
司法試験の出願期間と必要書類
願書を入手したら、次は出願手続きを行います。出願期間は非常に短く、不備があると受験できなくなるため、必要書類を確実に準備することが重要です。
出願期間(3月下旬~4月上旬・消印有効)
司法試験の出願期間は、例年3月下旬から4月上旬の約10日間です。2025年の場合、3月28日(金)から4月7日(月)までの消印有効となっています。
消印有効とは、出願期限最終日の消印があれば有効とみなされることを意味します。ただし、郵便事情によっては当日投函でも翌日消印になる場合があるため、出願期限の数日前までに投函することを強くおすすめします。
出願書類に不備があった場合、法務省から補正を求められることがありますが、出願期間を過ぎてしまうと一切の受理が認められません。1年に1回しかない受験機会を逃さないためにも、余裕を持った出願を心がけましょう。
出願に必要なもの(願書・写真・収入印紙・住民票コード)
司法試験の出願には、以下の書類が必要です。
必要書類一覧:
- 受験願書(記入済み)
- 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm、無帽・正面・上半身、最近6か月以内に撮影したもの)
- 収入印紙28,000円分(願書に貼付)
- 住民票コード(任意だが記入を推奨)
- 法科大学院修了(見込み)証明書または予備試験合格証書の写し
- 返信用封筒(受験票送付用、長形3号封筒に84円切手貼付)
写真は、証明写真機やスピード写真ではなく、写真店で撮影したものが推奨されます。受験票や合格証書にも使用されるため、きちんとした写真を準備しましょう。
収入印紙は郵便局や法務局で購入できます。28,000円分と高額なため、願書に貼付する際は慎重に扱ってください。一度貼付すると訂正が困難なため、位置を確認してから貼りましょう。
願書の書き方と注意点
願書の記入は、黒色のボールペンまたは万年筆で丁寧に記入します。修正液や修正テープの使用は認められないため、間違えた場合は新しい願書で書き直す必要があります。
記入項目には、氏名、生年月日、住所、受験地、法科大学院修了年月または予備試験合格年月などがあります。特に受験地(試験会場)の選択は重要です。一度選択した受験地は原則として変更できないため、慎重に選びましょう。
住民票コードの記入は任意ですが、記入することで受験資格の確認がスムーズになります。住民票コードは住民票に記載されているため、事前に確認しておくとよいでしょう。
記入内容に誤りがあると、出願が受理されない場合や、受験票が届かない場合があります。記入後は、複数回見直して誤りがないことを確認してから郵送しましょう。
出願期間を過ぎると受験不可|早めの準備が重要
出願期間を1日でも過ぎてしまうと、いかなる理由があっても受験は認められません。「郵便が遅れた」「書類の不備に気づかなかった」という事情も一切考慮されないため、出願期間には絶対的な注意が必要です。
出願期間が約10日間と短いため、願書を入手したらすぐに記入を始めることをおすすめします。必要書類をチェックリスト化して、不足がないか確認しましょう。特に法科大学院の証明書発行には数日かかる場合があるため、早めに申請しておくことが大切です。
また、出願直前に慌てて準備すると、記入ミスや書類の不備が発生しやすくなります。余裕を持って準備し、出願期限の3日前までには投函できるようにスケジュールを組むことをおすすめします。
司法試験の受験資格については、法科大学院ルートと予備試験ルートの詳細を解説していますので、受験資格の確認にご活用ください。
司法試験の受験資格に関してもっと詳しい記事はこちら
司法試験の受験資格とは?法科大学院・予備試験ルートを解説
司法試験の試験実施日|4日間のスケジュール
司法試験は、論文式試験3日間と短答式試験1日間の合計4日間で実施されます。さらに、論文式試験の2日目と3日目の間には中日(休息日)が設けられているため、実質的には5日間のスケジュールとなります。ここでは、各日の試験内容と重要なポイントを解説します。
1日目:論文式試験(選択科目・公法系)
試験初日は、午前中に選択科目、午後に公法系科目(憲法・行政法)の論文式試験が行われます。
選択科目は、倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法(公法系)、国際関係法(私法系)の8科目から1科目を選択します。選択科目は2時間の試験時間で、専門的な知識と論述力が求められます。
午後の公法系科目は、憲法と行政法を合わせて4時間の試験となります。憲法が2時間程度、行政法が2時間程度の配分で出題されることが一般的です。4時間という長丁場の試験となるため、体力と集中力の維持が重要です。
初日は緊張と疲労が最も大きい日となります。試験開始前に会場の雰囲気に慣れておくため、前日に会場の下見をしておくことをおすすめします。
2日目:論文式試験(民事系3科目)
2日目は、民事系科目(民法・商法・民事訴訟法)の論文式試験が行われます。試験時間は合計6時間で、司法試験の中で最も長い1日となります。
民法は2時間30分程度、商法は1時間30分程度、民事訴訟法は2時間程度の時間配分が一般的です。民事系は出題範囲が広く、条文や判例の正確な理解が求められます。
6時間の長時間試験となるため、昼食時間の過ごし方も重要です。重い食事は眠気を誘うため、軽めの食事を心がけましょう。また、トイレの時間も考慮して、時間配分を計画することが大切です。
2日目が終わると翌日は中日(休息日)となるため、試験後は十分な休息を取って、残りの試験に備えることができます。
中日(休息日)の過ごし方と重要性
中日は、論文式試験の2日目と3日目の間に設けられる休息日です。この1日の休みは、体力と精神力を回復させるための重要な時間となります。
中日の過ごし方は人それぞれですが、多くの受験生は以下のような方法で過ごしています。
- 午前中は軽く復習をする程度にとどめる
- 午後は体を休めて、早めに就寝する
- 刑事系科目の重要論点を最終確認する
- 外出は最小限にして、体力を温存する
中日に無理な詰め込み学習をすると、3日目と4日目の試験に悪影響が出る可能性があります。むしろ、心身をリフレッシュさせて、残りの試験に最高の状態で臨めるよう調整することが重要です。
また、中日は試験会場に行く必要がないため、宿泊先で静かに過ごすことができます。遠方から受験している方は、この日を利用して翌日以降の準備を整えましょう。
3日目:論文式試験(刑事系2科目)
3日目は、刑事系科目(刑法・刑事訴訟法)の論文式試験が行われます。試験時間は合計4時間で、刑法が2時間程度、刑事訴訟法が2時間程度の配分となります。
刑事系は、事例問題を通じて論理的な思考力と論述力が問われます。特に刑法では、構成要件該当性、違法性、有責性の三段階の検討を丁寧に論述する必要があります。
中日の休息が功を奏し、3日目は比較的集中力を維持しやすい日となります。ただし、ここまで3日間の試験を経ているため、疲労の蓄積には注意が必要です。
3日目が終わると、論文式試験は終了です。翌日の短答式試験に備えて、この日も早めに休息を取ることをおすすめします。
4日目:短答式試験(憲法・民法・刑法)
最終日は、短答式試験が行われます。短答式試験は、憲法、民法、刑法の3科目で、合計3時間30分の試験となります。
短答式試験は択一式のマークシート方式で、知識の正確さとスピードが求められます。各科目の時間配分は、憲法が1時間、民法が1時間15分、刑法が1時間15分程度が一般的です。
短答式試験には足切り点が設定されており、一定の点数に達しないと論文式試験が採点されません。そのため、論文式試験だけでなく、短答式試験も十分な対策が必要です。
4日間の試験スケジュールを乗り切るには、体力と精神力の管理が不可欠です。試験前から規則正しい生活を心がけ、本番で最高のパフォーマンスを発揮できるよう準備しましょう。
司法試験の短答式試験については、出題形式や対策方法を詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
司法試験の短答式試験に関してもっと詳しい記事はこちら
司法試験の短答式試験とは?科目・足切り点・対策方法を詳しく解説
-
 スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら
スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら -
 司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら
司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら -
 合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
司法試験の時間割|科目別の試験時間
司法試験の時間割を事前に把握しておくことは、試験当日のペース配分を考える上で重要です。ここでは、論文式試験と短答式試験の詳細な時間割を確認しましょう。
論文式試験の時間割(各科目2時間)
論文式試験は、各科目で2時間程度の時間が割り当てられています。具体的な時間割は以下の通りです。
1日目(選択科目・公法系):
- 9:30-11:30:選択科目(2時間)
- 13:00-17:00:公法系(憲法・行政法)(4時間)
2日目(民事系):
- 9:30-16:00:民事系(民法・商法・民事訴訟法)(6時間30分、昼休憩含む)
3日目(刑事系):
- 9:30-13:30:刑事系(刑法・刑事訴訟法)(4時間)
論文式試験では、各科目で求められる論述量が多く、時間配分が合否を左右します。過去問演習を通じて、各科目の最適な時間配分を体得しておくことが重要です。
また、試験時間中は退室が認められない時間帯があります。開始後30分間と終了前10分間は退室できないため、トイレなどは事前に済ませておきましょう。
短答式試験の時間割(科目別に異なる)
短答式試験は、憲法、民法、刑法の3科目で実施されます。時間割は以下の通りです。
4日目(短答式試験):
- 9:30-10:30:憲法(1時間)
- 10:50-12:05:民法(1時間15分)
- 13:15-14:30:刑法(1時間15分)
各科目の間には短い休憩時間があり、トイレや気分転換の時間として活用できます。憲法は問題数が比較的少ないため1時間、民法と刑法は問題数が多いため1時間15分の時間設定となっています。
短答式試験では、1問あたりに使える時間が限られているため、分からない問題は後回しにして、確実に解ける問題から解答していく戦略が有効です。時間配分の練習は、模擬試験を活用して行いましょう。
試験当日の持ち物と注意事項
試験当日は、以下の持ち物を必ず準備してください。
必須の持ち物:
- 受験票
- 写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 筆記用具(黒色ボールペン、鉛筆、消しゴム)
- 時計(時計機能のみのもの。スマートウォッチは不可)
あると便利な持ち物:
- 予備の筆記用具
- 昼食・飲み物
- 上着(冷房対策)
- タオル(暑さ対策)
- 常備薬
試験会場には、電卓、六法、参考書などの持ち込みは一切認められません。また、携帯電話・スマートフォンは電源を切ってカバンにしまうよう指示されます。
論文式試験では、大量の論述を行うため、手が疲れにくいボールペンを選ぶことをおすすめします。また、書き損じに備えて修正液や修正テープも持参しましょう(使用が認められている場合)。
司法試験の試験会場|全国9箇所の実施場所
司法試験は、全国9箇所の試験会場で実施されます。受験地の選択は出願時に行い、原則として変更はできません。ここでは、各試験会場の情報と選択時の注意点を解説します。
主要都市の試験会場一覧(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・沖縄)
司法試験の試験会場は、以下の9箇所に設置されています。
試験会場一覧:
- 札幌:北海道地区(主に北海道大学法科大学院周辺の会場)
- 仙台:東北地区(主に東北大学法科大学院周辺の会場)
- 東京:関東地区(主に都内の大学施設や会議場)
- 名古屋:中部地区(主に名古屋大学法科大学院周辺の会場)
- 大阪:近畿地区(主に大阪市内の大学施設や会議場)
- 広島:中国地区(主に広島大学法科大学院周辺の会場)
- 福岡:九州北部地区(主に九州大学法科大学院周辺の会場)
- 那覇:沖縄地区(主に琉球大学法科大学院周辺の会場)
- 金沢:北陸地区(主に金沢大学法科大学院周辺の会場)
具体的な試験会場は、受験票送付時に通知されます。多くの場合、法科大学院や大学の施設が使用されますが、受験者数によっては会議場などが使用される場合もあります。
東京会場は受験者数が最も多いため、複数の会場に分散して実施されることがあります。また、大阪会場も多くの受験者が集まるため、同様に複数会場での実施となる場合があります。
試験会場の選択方法と変更手続き
試験会場は、出願時に受験願書で選択します。原則として、一度選択した受験地の変更は認められません。やむを得ない事情(住所変更、災害など)がある場合でも、変更が認められるかは法務省の判断によります。
受験地を選択する際は、以下のポイントを考慮しましょう。
- 自宅からのアクセスの良さ
- 宿泊施設の確保のしやすさ
- 慣れ親しんだ土地かどうか
- 試験期間中の気候(特に真夏の暑さ)
遠方の試験会場を選択する場合は、試験前日から現地入りして宿泊することをおすすめします。4日間(中日を含めると5日間)の長期滞在となるため、宿泊施設の予約は早めに行いましょう。
また、法科大学院に在籍している方は、所属する法科大学院の最寄りの試験会場を選択するケースが多いです。慣れた環境で受験できるメリットがあるためです。
試験会場へのアクセスと下見の重要性
試験当日は、余裕を持って会場に到着できるよう、事前にアクセス方法を確認しておきましょう。公共交通機関の遅延や道路の渋滞を考慮して、通常よりも早めに出発することをおすすめします。
試験会場への下見で確認すべきポイント:
- 最寄り駅から試験会場までの道のり(所要時間)
- 試験会場の建物の入口と試験教室の位置
- 周辺のコンビニや飲食店の場所
- トイレの位置と数
- 休憩できるスペース
特に遠方から受験する方は、前日または当日午前中に会場の下見をしておくことを強くおすすめします。当日に会場を探して焦ることがないよう、事前に確認しておきましょう。
また、試験期間中の昼食についても計画を立てておくことが大切です。会場周辺の飲食店は混雑する可能性があるため、お弁当を持参するか、事前に購入できる場所を確認しておきましょう。
司法試験の短答式試験合格発表日
司法試験は、短答式試験と論文式試験の二段階選抜方式となっています。短答式試験の合格発表は、最終合格発表よりも早い時期に行われます。
短答式試験の合格発表は8月上旬
短答式試験の合格発表は、試験実施から約3週間後の8月上旬に行われます。2025年の場合、8月6日(水)に発表される予定です。
短答式試験には足切り点(最低基準点)が設定されており、この基準点を満たさないと論文式試験が採点されません。そのため、短答式試験の合格発表は、受験生にとって最初の重要な関門となります。
短答式試験に合格した受験者のみ、論文式試験の採点対象となります。論文式試験でどれだけ良い答案を書いても、短答式試験で足切りになっていれば不合格となるため、短答式試験の対策も十分に行う必要があります。
合格発表の確認方法(法務省ホームページ)
短答式試験の合格発表は、法務省のホームページで確認できます。発表当日の午後4時頃に、合格者の受験番号が一覧で公表されます。
確認方法は以下の通りです。
- 法務省ホームページにアクセス
- 「司法試験」のページを開く
- 「短答式試験合格者受験番号」のリンクをクリック
- PDF形式の合格者一覧から自分の受験番号を確認
受験番号は数字のみで公表され、氏名は公表されません。発表直後はアクセスが集中してページが開きにくくなる場合があるため、時間をずらして確認することも検討しましょう。
また、短答式試験の合格通知は郵送されません。不合格者には、後日、成績通知書が郵送されます。
短答式試験の合格基準と足切り点
短答式試験の合格基準は、毎年の試験の難易度に応じて調整されます。一般的には、満点の60-70%程度の得点が合格ラインとなることが多いです。
2023年度の短答式試験では、憲法50点満点、民法75点満点、刑法50点満点の合計175点満点で実施され、合格最低点は93点(53.1%)でした。年度によって難易度が変わるため、合格最低点も変動します。
短答式試験で高得点を取ることは、最終合格に向けて有利に働きます。短答式試験の得点は最終合格判定には含まれませんが、論文式試験の採点対象となるための重要な関門です。
短答式試験の対策としては、過去問演習を繰り返し行い、条文と判例の正確な知識を身につけることが重要です。また、時間配分の練習も欠かせません。
司法試験の合格発表については、短答式試験と最終合格発表の詳細を解説していますので、あわせてご確認ください。
司法試験の合格発表に関してもっと詳しい記事はこちら
司法試験の合格発表日程と確認方法|結果通知の流れを解説
司法試験の最終合格発表日
短答式試験に合格すると、次は論文式試験の採点が行われ、最終合格者が決定します。最終合格発表は、短答式試験合格発表から約3か月後に行われます。
最終合格発表は11月中旬
最終合格発表は、例年11月中旬に行われます。2025年の場合、11月12日(水)に発表される予定です。
試験実施日(7月)から最終合格発表までは約4か月の期間があります。この間、受験生は結果を待ちながら、次年度の受験準備や就職活動を並行して進めることが一般的です。
最終合格発表は、短答式試験と論文式試験の総合評価で決定されます。ただし、短答式試験の得点は最終合格判定には含まれず、論文式試験の得点のみで合否が決まります。短答式試験は、あくまで論文式試験の採点対象となるための足切り試験という位置づけです。
合格者の受験番号・氏名の公表方法
最終合格発表では、法務省ホームページに合格者の受験番号と氏名が公表されます。発表当日の午後4時頃に公表されることが一般的です。
公表される情報は以下の通りです。
- 合格者の受験番号(数字)
- 合格者の氏名(氏名の公表を希望した者のみ)
- 合格者数と合格率
- 選択科目別の合格者数
- 法科大学院別の合格者数
合格者には、後日、合格証書が郵送されます。合格証書は、司法修習の申し込みや法曹資格の登録に必要となる重要な書類です。
また、不合格者には、成績通知書が郵送されます。成績通知書には、各科目の得点や順位が記載されており、次年度の受験に向けた分析材料となります。
合格発表後の手続き(司法修習の申し込み期限)
最終合格発表後は、司法修習の申し込み手続きを行う必要があります。申し込み期限は合格発表から約2週間後となるため、速やかに手続きを進めましょう。
合格後の主な手続き:
- 司法修習の申し込み(合格発表から2週間以内)
- 健康診断の受診
- 必要書類の提出(卒業証明書、住民票など)
- 修習地の希望調査
司法修習は、翌年12月頃から約1年間実施されます。修習地は全国8箇所(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、高松)から選択でき、希望調査に基づいて配属が決定されます。
また、合格後は法律事務所への就職活動も本格化します。多くの法律事務所では、合格発表直後から採用活動を開始するため、事前に情報収集を行っておくことをおすすめします。
司法試験合格後のスケジュール|司法修習までの流れ
司法試験に合格しても、すぐに弁護士や裁判官になれるわけではありません。合格後は司法修習を受け、二回試験に合格することで、初めて法曹資格を取得できます。
司法修習の開始時期(翌年12月頃)
司法試験合格後、司法修習が始まるまでには約1年間の期間があります。例えば、2025年11月に合格した場合、司法修習の開始は2026年12月頃となります。
この約1年間は、「修習待期間」と呼ばれ、多くの合格者は法律事務所でアルバイトをしたり、語学研修を受けたり、自己研鑽の時間として活用しています。
司法修習の期間は約1年間で、前期修習(集合修習)、実務修習(配属先での実務研修)、後期修習(集合修習)の3段階で構成されています。修習期間中は、裁判所、検察庁、法律事務所でのローテーション研修を通じて、実務能力を身につけます。
司法修習生考試(二回試験)の実施時期
司法修習の最後には、司法修習生考試(通称:二回試験)が実施されます。二回試験は、修習修了の約1か月前に行われ、この試験に合格することで初めて法曹資格を取得できます。
二回試験は、民事裁判、刑事裁判、検察、民事弁護、刑事弁護の5科目で実施されます。合格率は98-99%と非常に高いですが、不合格になると再修習が必要となるため、修習生は真剣に取り組みます。
二回試験に合格すると、弁護士、裁判官、検察官のいずれかの道に進むことができます。多くの修習生は弁護士を選択し、法律事務所に就職します。
法曹資格取得までのタイムライン
司法試験受験から法曹資格取得までの全体的なタイムラインを確認しましょう。
タイムライン例(2025年受験の場合):
- 2025年3月:願書交付開始
- 2025年4月:出願期間
- 2025年7月:試験実施(4日間)
- 2025年8月:短答式試験合格発表
- 2025年11月:最終合格発表
- 2025年11月~2026年12月:修習待期間(約1年)
- 2026年12月:司法修習開始
- 2027年11月:二回試験実施
- 2027年12月:司法修習修了・法曹資格取得
司法試験受験から法曹資格取得までには、最短でも約2年半の期間が必要です。さらに、法科大学院や予備試験の受験期間を含めると、法曹を目指してから資格取得までには5-10年程度かかることが一般的です。
長期的な視点でキャリアプランを考え、計画的に準備を進めることが重要です。
司法試験合格後の流れについては、司法修習や法曹資格の詳細を解説していますので、あわせてご確認ください。
司法試験合格後の流れに関してもっと詳しい記事はこちら
司法試験合格後の資格登録|司法修習と弁護士・裁判官・検察官への道
2026年から導入されるCBT方式とは
2026年の司法試験から、短答式試験にCBT方式(Computer Based Testing)が導入される予定です。ここでは、CBT方式の概要と従来の試験との違いを解説します。
CBT方式の概要(コンピュータによる試験)
CBT方式とは、コンピュータを使用して試験を実施する方式です。受験者はパソコンの画面に表示される問題を読み、マウスやキーボードを使って解答を入力します。
司法試験では、2026年から短答式試験にCBT方式が導入される予定です。論文式試験は引き続き手書きの形式が維持されます。
CBT方式の主なメリットは以下の通りです。
- 採点の迅速化(結果発表の早期化)
- 試験会場の柔軟な設定
- 受験者のアクセシビリティ向上(文字サイズの調整など)
- 不正行為の防止
一方で、コンピュータ操作に不慣れな受験者にとっては、新たな課題となる可能性もあります。
従来の手書き試験との違い
従来の短答式試験は、問題冊子とマークシートを使用する紙ベースの試験でした。CBT方式では、これがコンピュータ画面上での操作に変わります。
主な違い:
- 問題の提示方法:紙の問題冊子 → コンピュータ画面
- 解答方法:マークシート塗りつぶし → マウスクリックまたはキーボード入力
- 問題の読み方:問題冊子をめくる → 画面をスクロールまたはページ切り替え
- メモの取り方:問題冊子に書き込み → メモ用紙の使用またはメモ機能
CBT方式では、問題文を紙に印刷して確認することができないため、長文問題を読む際には画面での読解力が求められます。また、試験時間中はコンピュータ画面を見続けることになるため、目の疲労にも注意が必要です。
CBT方式導入に向けた準備と練習
2026年以降に受験を予定している方は、CBT方式に慣れておく必要があります。以下の準備を行いましょう。
準備のポイント:
- パソコンでの文章読解に慣れる
- マウスやキーボード操作の練習をする
- 長時間の画面使用に備えて目の健康管理をする
- CBT方式の模擬試験を受験する(実施される場合)
法務省は、CBT方式の導入に先立って、受験者向けの練習用システムを提供する予定です。正式な情報が発表されたら、必ず練習用システムを利用して、操作方法に慣れておきましょう。
また、予備試験のCBT化も検討されているため、予備試験ルートで司法試験を目指す方も、早い段階からCBT方式に対応できるよう準備を進めることをおすすめします。
-
 スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら
スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら -
 司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら
司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら -
 合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
司法試験の日程に関連するよくある質問(FAQ)
司法試験の日程に関して、受験生からよく寄せられる質問をまとめました。
Q. 司法試験の願書はいつから入手できますか?
司法試験の願書は、例年3月上旬から4月上旬まで交付されます。2025年の場合、3月7日(金)から4月7日(月)までが願書交付期間となっています。
願書の入手方法は、郵送請求、法科大学院経由での受け取り、法務省での直接受け取りの3つがあります。郵送請求の場合は往復の郵送日数がかかるため、早めに手続きを開始することをおすすめします。願書交付期間と出願期間は重複していますが、出願期限は約10日間と短いため、願書を入手したらすぐに記入を始めましょう。
Q. 司法試験の出願期限を過ぎたらどうなりますか?
司法試験の出願期限を1日でも過ぎると、いかなる理由があっても受験は認められません。郵便の遅延や書類の不備といった事情も一切考慮されないため、絶対に期限を守る必要があります。
出願期間は例年3月下旬から4月上旬の約10日間で、消印有効となっています。ただし、当日投函でも翌日消印になる場合があるため、出願期限の数日前までに投函することを強くおすすめします。年に1回しかない受験機会を逃さないよう、余裕を持った出願を心がけましょう。
Q. 司法試験は年に何回実施されますか?
司法試験は年に1回のみ実施されます。例年7月上旬から中旬にかけて、4日間の日程で行われます。
他の国家試験の中には年2回実施されるものもありますが、司法試験は年1回のみのため、受験機会が非常に限られています。また、法科大学院修了または予備試験合格後5年以内に5回まで受験できる回数制限があるため、1回の試験に向けて万全の準備を行うことが重要です。
Q. 司法試験の試験会場は変更できますか?
司法試験の試験会場は、出願時に選択した受験地で固定され、原則として変更はできません。やむを得ない事情(住所変更、災害など)がある場合でも、変更が認められるかは法務省の判断によります。
受験地は全国9箇所(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇、金沢)から選択できます。自宅からのアクセス、宿泊施設の確保しやすさ、慣れ親しんだ土地かどうかを考慮して慎重に選択しましょう。特に遠方の会場を選択する場合は、4日間(中日を含めると5日間)の長期滞在となるため、宿泊計画も含めて検討することが大切です。
Q. 司法試験の合格発表はいつ確認できますか?
司法試験には2段階の合格発表があります。短答式試験の合格発表は試験実施から約3週間後の8月上旬に行われ、最終合格発表は11月中旬に行われます。
2025年の場合、短答式試験の合格発表は8月6日(水)、最終合格発表は11月12日(水)に予定されています。いずれも法務省ホームページで午後4時頃に公表され、合格者の受験番号が一覧で確認できます。最終合格発表では、受験番号に加えて氏名も公表されます(氏名公表を希望した者のみ)。
Q. 司法試験合格後、すぐに司法修習が始まりますか?
司法試験合格後、司法修習が始まるまでには約1年間の期間があります。例えば、2025年11月に合格した場合、司法修習の開始は2026年12月頃となります。
この約1年間は「修習待期間」と呼ばれ、多くの合格者は法律事務所でアルバイトをしたり、語学研修を受けたり、自己研鑽の時間として活用しています。司法修習は約1年間で、修習修了時の二回試験に合格することで、初めて弁護士、裁判官、検察官としての法曹資格を取得できます。
まとめ:司法試験の日程を把握して計画的に準備しよう
本記事では、司法試験の日程について、願書交付から合格発表、そして司法修習開始までの詳細なスケジュールを解説しました。重要なポイントを改めて確認しましょう。
- 願書交付と出願は早めの行動が重要:願書交付期間は3月上旬から4月上旬、出願期間は3月下旬から4月上旬の約10日間です。出願期限を過ぎると一切の受験が認められないため、余裕を持った準備が必須です。郵送請求の場合は往復の日数を考慮し、出願期限の数日前までに投函しましょう。
- 試験は7月に4日間実施・中日の活用が鍵:司法試験は年1回、7月に論文式試験3日間と短答式試験1日間の計4日間で実施されます。論文式試験の2日目と3日目の間には中日(休息日)があり、この日をどう過ごすかが残りの試験のパフォーマンスを左右します。体力と精神力を温存し、最高の状態で全日程を乗り切りましょう。
- 合格発表は8月と11月の2回・合格後の手続きも迅速に:短答式試験の合格発表は8月上旬、最終合格発表は11月中旬に行われます。最終合格後は司法修習の申し込み期限が約2週間後となるため、速やかに手続きを進める必要があります。合格から司法修習開始までは約1年、法曹資格取得までは約2年半のスケジュールを把握しておきましょう。
司法試験の日程を正確に把握できたら、次は受験資格の確認と試験対策を始めましょう。司法試験の受験資格と司法試験の勉強法を参考に、計画的に学習を進めることをおすすめします。
本記事を通じて、司法試験の年間スケジュールと各段階で必要な準備を理解いただけたはずです。これらの情報を活用して、司法試験合格と法曹資格取得の実現に向けて着実に歩を進めましょう。
-
 スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら
スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら -
 司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら
司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら -
 合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
司法試験の関連記事

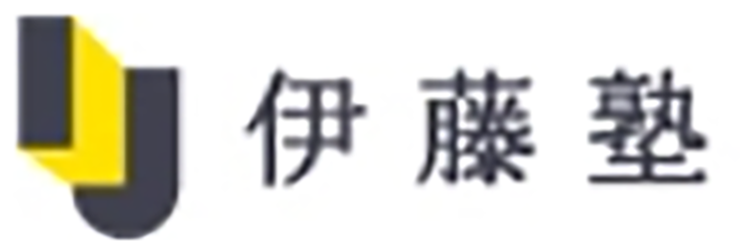


コメント