司法試験の合格発表日程について調べているあなたへ。「いつ結果が分かるのか」「どうやって確認するのか」という疑問は、正確な発表スケジュールと確認方法を知ることで解決できます。
本記事では、司法試験の短答式試験と最終合格の発表日程、法務省ホームページでの確認方法、成績通知書や合格証書の送付時期について、最新の情報を交えて詳しく解説します。この情報をもとに、司法試験合格発表に向けて、適切な準備を進めましょう。
- 司法試験の短答式試験と最終合格の具体的な発表日程と時刻
- 法務省ホームページや掲示板での結果確認方法
- 成績通知書・合格証書の送付時期と内容
- 合格後の司法修習までの具体的なスケジュール
- 短答式試験と最終合格の発表日程:短答式試験の合格発表は6月上旬、最終合格発表は9月中旬に行われ、それぞれ午後4時に法務省ホームページで公開されます。
- 複数の確認方法を用意:法務省ホームページでの受験番号確認、試験地の掲示板での確認、官報での氏名公表など、複数の方法で結果を確認できます。
- 合格後のスケジュール管理:合格発表から司法修習開始までは約3-4ヶ月あり、採用選考や修習地発表などの重要なイベントが続くため、事前にスケジュールを把握しておくことが大切です。
-
 スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら
スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら -
 司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら
司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら -
 合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
司法試験の合格発表日程(令和7年・令和6年)
司法試験の合格発表日程を正確に把握することは、受験生にとって非常に重要です。短答式試験と最終合格の2段階で発表が行われるため、それぞれの日程と時刻を確認しておきましょう。
司法試験の短答式試験合格発表日
司法試験の短答式試験合格発表は、例年6月上旬に行われます。令和6年度の短答式試験合格発表は6月6日(木)午後4時に実施されました。令和7年度についても、同様に6月上旬の平日午後4時に発表される予定です。
短答式試験は憲法、民法、刑法の3科目で実施される択一式マークシート試験で、この合格者のみが論文式試験に進むことができます。発表当日は法務省ホームページへのアクセスが集中するため、時間に余裕を持って確認することをおすすめします。
短答式試験の合格最低点は年度によって変動しますが、近年は114点から132点の範囲で推移しています。自己採点で合格最低点付近の得点だった受験生は、発表当日まで不安な時間を過ごすことになりますが、論文式試験の準備は継続しておくことが重要です。
司法試験の最終合格発表日と発表時刻
司法試験の最終合格発表は、例年9月中旬に行われます。令和6年度の最終合格発表は9月10日(火)午後4時に実施されました。令和7年度についても、9月中旬の平日午後4時に発表される予定です。
最終合格発表では、短答式試験と論文式試験の総合成績による合格者が決定されます。発表時刻の午後4時には、法務省ホームページに合格者受験番号が掲載されるとともに、各試験地の法務局または地方法務局にも掲示板で合格者受験番号が掲示されます。
発表当日は多くの受験生や関係者が結果を確認するため、法務省ホームページへのアクセスが非常に集中します。確実に結果を確認したい場合は、複数の確認方法を用意しておくことをおすすめします。
司法試験の合格発表日程の年間スケジュール
司法試験の年間スケジュールを把握しておくことで、受験準備や合格後の予定を立てやすくなります。標準的な年間スケジュールは以下のとおりです。
1月中旬:司法試験の受験願書配布開始
2月上旬:受験願書受付期間(約10日間)
5月中旬:短答式試験実施(1日)
5月下旬:論文式試験実施(3日間)
6月上旬:短答式試験合格発表(午後4時)
9月中旬:最終合格発表(午後4時)
9月下旬:成績通知書兼合格通知書の送付
10月上旬:司法修習生採用選考(面接)
10月下旬:修習地発表
12月上旬:司法修習開始
このスケジュールは年度によって若干の変動がありますが、大きな流れは毎年ほぼ同じです。司法試験の日程では、出願から合格発表までの詳細なスケジュールを解説していますので、併せて確認しておくことをおすすめします。
司法試験の日程に関してもっと詳しい記事はこちら
司法試験の日程|出願から合格発表までのスケジュール完全ガイド
司法試験の短答式試験合格発表の確認方法
短答式試験の合格発表を確認する方法は複数あります。それぞれの方法の特徴を理解し、自分に合った確認方法を選びましょう。
司法試験短答式試験の法務省ホームページでの確認方法
最も一般的な確認方法は、法務省ホームページでの確認です。発表日の午後4時になると、法務省のウェブサイトに「令和○年司法試験短答式試験結果について」というページが公開され、合格者の受験番号一覧がPDF形式で掲載されます。
法務省ホームページでの確認手順は次のとおりです。まず、法務省のトップページにアクセスし、「司法試験」または「試験・資格」のセクションを探します。次に、「令和○年司法試験短答式試験結果について」のリンクをクリックし、PDF形式の合格者受験番号一覧を開きます。
受験番号は数字4桁で表示されており、受験地ごとに分類されています。自分の受験番号を探す際は、受験地を確認した上で該当する番号リストを確認しましょう。発表直後はアクセスが集中してページの読み込みに時間がかかることがあるため、時間に余裕を持って確認することをおすすめします。
司法試験短答式試験の自己採点が必要な理由
司法試験の短答式試験では、合格発表前に自己採点を行うことが非常に重要です。短答式試験の解答は試験終了後に法務省ホームページで公表されるため、自分の解答と照らし合わせて得点を計算できます。
自己採点が必要な理由は、論文式試験の準備を効率的に進めるためです。短答式試験の合格発表は6月上旬、論文式試験の実施は5月下旬のため、短答式試験の結果が分かる頃には論文式試験が終了しています。しかし、自己採点で合格の可能性が高いと判断できれば、短答式試験終了直後から論文式試験の振り返りや次年度の準備に集中できます。
逆に、自己採点で合格最低点に届かない場合は、来年度に向けた短答式試験対策の見直しを早期に開始できます。自己採点の結果を冷静に分析し、次のステップを計画的に進めることが、司法試験合格への近道となります。
司法試験短答式試験の成績通知書の送付時期と内容
短答式試験の成績通知書は、合格発表から約2週間後に受験生全員に郵送されます。令和6年度の場合、6月6日に合格発表があり、6月下旬に成績通知書が届きました。
成績通知書には、各科目(憲法、民法、刑法)の得点、短答式試験の総合得点、合格最低点、そして合否の判定が記載されています。不合格だった場合でも、自分の得点と合格最低点との差を確認することで、次年度に向けた対策を立てやすくなります。
成績通知書は論文式試験の準備状況を見直す際にも参考になります。短答式試験で苦手科目があった場合、その科目の論文式試験対策を重点的に行う必要があるかもしれません。成績通知書の内容を丁寧に分析し、自分の実力を客観的に把握することが大切です。
司法試験の最終合格発表の確認方法
最終合格発表の確認方法も複数あります。自分の状況に合わせて、最適な確認方法を選択しましょう。
司法試験最終合格の法務省ホームページでの確認
最終合格発表も、短答式試験と同様に法務省ホームページで確認できます。発表日の午後4時に、「令和○年司法試験の結果について」というページが公開され、合格者の受験番号一覧がPDF形式で掲載されます。
最終合格発表のページには、合格者受験番号一覧に加えて、今年度の合格者数、合格率、短答式試験と論文式試験の合格最低点、採点基準などの重要な情報も掲載されます。これらの情報は、司法試験の全体像を理解する上で非常に参考になります。
法務省ホームページでの確認は、場所を問わずインターネット環境があればすぐに結果を知ることができる点が最大のメリットです。スマートフォンやパソコンから簡単にアクセスできるため、多くの受験生がこの方法を利用しています。
司法試験合格者の受験番号掲示板での確認
法務省ホームページでの確認以外に、各試験地の法務局または地方法務局に設置される掲示板でも合格者受験番号を確認できます。掲示板は発表日の午後4時に掲示され、一定期間(通常1週間程度)掲示されます。
掲示板での確認は、インターネット環境がない場合や、実際に掲示板を見て合格を実感したい受験生に適しています。発表当日は多くの受験生や関係者が掲示板の前に集まり、合格を喜び合う光景が見られることも少なくありません。
ただし、掲示板での確認は試験地の法務局まで足を運ぶ必要があるため、遠方に住んでいる場合や時間的制約がある場合には不便です。そのような場合は、法務省ホームページでの確認を優先することをおすすめします。
司法試験合格者名簿の新聞掲載とオンライン確認
司法試験の合格者氏名は、官報に掲載されるほか、一部の新聞でも掲載されることがあります。特に、主要な全国紙や法律専門誌では、合格者の氏名や出身法科大学院などの情報が掲載される場合があります。
新聞での確認は、合格発表の翌日以降に可能となります。ただし、すべての新聞が合格者名簿を掲載するわけではなく、また掲載される情報も新聞によって異なるため、正式な確認方法としては法務省ホームページや官報を優先することをおすすめします。
近年では、一部の法科大学院や予備校が、自校の合格者情報をウェブサイトで公開することもあります。ただし、これらの情報は二次的なものであり、公式な確認には法務省の発表を確認する必要があります。
司法試験の成績通知書と合格証書の送付
合格発表後には、成績通知書や合格証書が送付されます。これらの書類の内容と重要性を理解しておきましょう。
司法試験の成績通知書兼合格通知書の内容
最終合格者には、合格発表から約2週間後に「成績通知書兼合格通知書」が郵送されます。令和6年度の場合、9月10日に合格発表があり、9月下旬に成績通知書兼合格通知書が届きました。
この通知書には、短答式試験の各科目得点と総合得点、論文式試験の各科目得点と総合得点、選択科目の得点、そして最終的な総合得点と成績順位が記載されています。また、各科目の全国平均点や合格最低点も記載されているため、自分の実力を客観的に評価できます。
成績順位は、就職活動において重要な参考資料となります。特に上位の成績で合格した場合は、大手法律事務所や検察庁、裁判所への就職において有利になることがあります。一方、合格最低点付近で合格した場合でも、司法修習を経て二回試験(司法修習修了時に受験する試験)に合格すれば、法曹資格を取得できることに変わりはありません。
司法試験の合格証書の交付時期と受取方法
司法試験の合格証書は、司法修習開始後に最高裁判所から交付されます。具体的には、司法修習が始まる12月上旬頃に、司法研修所での入所式の際に合格証書が授与されることが一般的です。
合格証書は、司法試験に合格したことを公式に証明する重要な書類です。弁護士、裁判官、検察官のいずれの法曹になる場合でも、この合格証書が必要となります。合格証書は大切に保管し、紛失しないよう注意しましょう。
なお、合格証書の再発行は可能ですが、手続きには時間と費用がかかります。また、再発行された証書には「再交付」の記載が入るため、原本を大切に保管することが重要です。
司法試験の成績通知書が就職活動で重要な理由
司法試験の成績通知書は、就職活動において非常に重要な書類です。多くの法律事務所や企業法務部門では、採用選考の際に司法試験の成績を参考にします。
特に大手法律事務所では、成績上位者を優先的に採用する傾向があります。成績順位が上位100番以内、あるいは上位10%以内であれば、多くの事務所から内定を得やすくなります。一方、成績が平均的であっても、面接での印象や人柄、専門分野への関心などを総合的に評価されるため、成績だけがすべてではありません。
成績通知書は、司法修習中の就職活動で提出を求められることがあります。原本は大切に保管し、必要に応じてコピーを準備しておくことをおすすめします。また、成績が思わしくなかった場合でも、司法修習での実務研修や二回試験の成績でカバーできる可能性があるため、前向きに取り組むことが大切です。
-
 スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら
スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら -
 司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら
司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら -
 合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
司法試験の官報掲載について
司法試験の合格者情報は、官報に掲載されることで公式に公表されます。官報掲載の時期や確認方法を理解しておきましょう。
司法試験合格者の官報掲載時期
司法試験の合格者氏名は、合格発表の翌日または数日後に官報に掲載されます。令和6年度の場合、9月10日に合格発表があり、9月11日の官報に合格者氏名が掲載されました。
官報への掲載は、国家試験の合格者を公式に公表する手続きの一環です。司法試験以外にも、公認会計士試験、税理士試験、弁理士試験などの国家資格試験の合格者も官報に掲載されます。
官報は、独立行政法人国立印刷局が発行する国の公式の機関紙です。法令の公布、国や地方公共団体の人事異動、国家試験の合格者発表などが掲載されます。官報は毎日発行されており、インターネット版官報(無料)と紙版官報(有料)があります。
司法試験の官報での合格者氏名の確認方法
官報での合格者氏名の確認は、インターネット版官報を利用するのが便利です。インターネット版官報は、発行日から30日間無料で閲覧できます。官報のウェブサイトにアクセスし、発行日を指定して検索することで、司法試験の合格者情報を含むページを見ることができます。
合格者氏名は、受験地ごとに五十音順で掲載されます。氏名のみが掲載され、受験番号や出身法科大学院などの情報は含まれません。自分の氏名が正しく掲載されているか、必ず確認しておくことをおすすめします。
30日を過ぎた官報は、国立国会図書館や一部の公立図書館で閲覧できます。また、有料のデータベースサービスを利用すれば、過去の官報をいつでも検索・閲覧することが可能です。
司法試験の官報掲載の意義と歴史
官報への合格者氏名の掲載は、明治時代から続く伝統的な公表方法です。国家資格試験の合格者を公式に公表することで、社会的な信用性を高める役割を果たしてきました。
司法試験の場合、官報掲載には「法曹としての公的な責任を担う資格を得た」という意味合いがあります。弁護士、裁判官、検察官は、いずれも高い倫理性と専門性が求められる職業であり、その入口となる司法試験の合格者を公表することで、社会に対する透明性を確保しています。
近年では、個人情報保護の観点から、氏名の公表を望まない受験生もいます。しかし、現時点では司法試験の合格者氏名は官報に掲載されることが法令で定められており、これは変更されていません。法曹という公的な職務に就くための資格試験であることから、一定の公開性が求められていると言えるでしょう。
司法試験の最新合格者データ(令和6年度)
最新の合格者データを把握することで、司法試験の現状と傾向を理解できます。令和6年度のデータを詳しく見ていきましょう。
司法試験の最終合格者数と合格率
令和6年度の司法試験最終合格者数は1,832人で、合格率は45.3%でした。受験者数は4,045人で、前年度の4,170人から若干減少しています。合格率は前年度の45.7%とほぼ同水準を維持しており、近年は45%前後で安定している傾向にあります。
過去10年間の推移を見ると、合格率は2015年度の23.0%から徐々に上昇し、2020年度以降は40%台を維持しています。これは、法科大学院の教育の質の向上や、受験回数制限による実力者の集中などが要因と考えられます。
合格者数については、政府が目標としている「年間1,500人程度の合格者」を上回る状況が続いています。法曹人口の拡大と法曹の質の確保のバランスをどう取るかは、今後も議論が続く課題です。
司法試験の短答式試験合格率と通過率
令和6年度の短答式試験合格者数は3,169人で、短答式試験受験者4,045人に対する合格率は78.3%でした。短答式試験は論文式試験に進むための足切り試験という性格があり、例年70-80%程度の合格率となっています。
短答式試験の合格最低点は、令和6年度は114点(165点満点)でした。これは得点率で約69%に相当します。合格最低点は年度によって変動しますが、近年は110点から135点の範囲で推移しています。
短答式試験の科目別平均点を見ると、憲法が最も高く、次いで民法、刑法の順となっています。ただし、この順序は年度によって変わることがあり、出題傾向や難易度によって左右されます。短答式試験対策としては、基本的な知識の正確な理解と、過去問演習による出題パターンの把握が重要です。
司法試験の予備試験組と法科大学院組の合格状況
令和6年度の合格者を受験資格別に見ると、予備試験合格者(予備試験組)の合格率は約90%と非常に高い水準を維持しています。一方、法科大学院修了者(法科大学院組)の合格率は約40%となっており、両者の間には大きな差があります。
予備試験組の合格率が高い理由は、予備試験自体が非常に難関であり、予備試験に合格している時点で司法試験に必要な実力を備えていることが挙げられます。予備試験の合格率は約3-4%と極めて低く、予備試験合格者は司法試験でも高い実力を発揮します。
法科大学院別の合格率については、上位校と下位校の差が顕著です。東京大学法科大学院、京都大学法科大学院、一橋大学法科大学院などの上位校では、合格率が70-80%に達する一方、合格率が10%未満の法科大学院も存在します。司法試験の合格率推移では、法科大学院別の詳細なデータと傾向を分析していますので、志望校選びの参考にしてください。
司法試験の合格率に関してもっと詳しい記事はこちら
司法試験の合格率推移|法科大学院別・予備試験組の傾向分析
司法試験の合格者データに関してもっと詳しい記事はこちら
司法試験の合格者データ|合格者数・氏名公表・名簿の見方を解説
司法試験合格発表後の流れ
合格発表後は、司法修習開始までにいくつかの重要な手続きがあります。スケジュールを把握し、適切に対応しましょう。
司法試験合格後の司法修習生採用選考
司法試験に合格した後、司法修習生として採用されるためには、最高裁判所が実施する「司法修習生採用選考」を受ける必要があります。この選考は、合格発表から約1ヶ月後の10月上旬に実施されます。
採用選考では、面接と健康診断が行われます。面接では、法曹としての適性や意欲、司法修習への取り組み姿勢などが確認されます。形式的な面接であり、司法試験に合格している時点で採用されることがほとんどですが、欠席せずに必ず参加する必要があります。
健康診断では、司法修習を受けるために必要な健康状態が確認されます。重大な健康上の問題がない限り、健康診断が原因で採用が見送られることはありません。ただし、健康診断の結果によっては、司法修習中に配慮が必要な事項について相談する場合があります。
司法試験合格から司法修習開始までのスケジュール
司法試験合格から司法修習開始までの標準的なスケジュールは以下のとおりです。
9月中旬:最終合格発表
9月下旬:成績通知書兼合格通知書の送付
10月上旬:司法修習生採用選考(面接・健康診断)
10月中旬:採用決定通知
10月下旬:修習地発表
11月上旬:事前課題の配布
11月中旬:修習地への引越し準備開始
12月上旬:司法修習開始(司法研修所での入所式)
このスケジュールの間に、多くの合格者は就職活動を行います。大手法律事務所の採用面接は、合格発表直後から10月にかけて集中的に行われます。就職活動と司法修習の準備を並行して進める必要があるため、計画的にスケジュール管理を行うことが重要です。
また、修習地が遠方の場合は、引越しの準備も必要になります。修習地発表後は、住居探しや引越し業者の手配など、実務的な準備も進めなければなりません。特に、人気の修習地では住居が見つかりにくいこともあるため、早めの準備が推奨されます。
司法試験合格者の修習地発表と事前課題
司法修習の修習地は、10月下旬に発表されます。修習地は、全国の主要都市に設置された司法修習委員会の所在地に対応しており、東京、大阪、名古屋、福岡などの大都市圏に配属される場合もあれば、地方都市に配属される場合もあります。
修習地の希望は、司法修習生採用選考の際に提出しますが、希望どおりの修習地に配属されるとは限りません。特に東京や大阪などの人気の修習地は、希望者が多いため、必ずしも希望が通るわけではありません。修習地発表後は、配属された地域での生活や就職について、現実的な計画を立てる必要があります。
修習地発表後、11月上旬頃には事前課題が配布されます。事前課題は、司法修習開始前に取り組むべき予習課題であり、民事裁判、刑事裁判、検察、弁護の各分野について、基本的な知識や考え方を確認する内容となっています。事前課題にしっかり取り組むことで、司法修習をスムーズに開始できます。
司法試験不合格だった場合の対応
残念ながら司法試験に不合格だった場合でも、次のステップを考える選択肢は複数あります。冷静に状況を分析し、最適な道を選びましょう。
司法試験の受験回数制限と再挑戦
司法試験には、法科大学院修了または予備試験合格から5年以内に5回まで受験できるという回数制限があります。この制限は、法曹志望者の質を確保するために設けられています。
不合格だった場合、まず確認すべきは残りの受験回数です。まだ受験回数に余裕がある場合は、再挑戦を視野に入れることができます。成績通知書を丁寧に分析し、どの科目が弱点だったのか、どの部分の対策が不足していたのかを明確にすることが重要です。
再受験を決意した場合は、勉強方法や学習環境を見直すことが必要です。独学で不合格だった場合は予備校の利用を検討する、予備校を利用していた場合は別の予備校への変更やカリキュラムの見直しを検討するなど、前回とは異なるアプローチを取ることが成功への鍵となります。司法試験の回数制限では、5回の受験制限の詳細と再挑戦の戦略について詳しく解説しています。
司法試験不合格後の就職活動の選択肢
司法試験に不合格だった場合、法曹以外のキャリアを選択することも一つの選択肢です。法科大学院で学んだ法律知識や論理的思考力は、さまざまな職種で活かすことができます。
一般企業の法務部門は、司法試験受験経験者を積極的に採用しています。企業法務では、契約書の作成・審査、コンプライアンス対応、訴訟対応など、法律知識を活かした業務が多くあります。法科大学院修了者や司法試験受験経験者は、法律の専門知識と論理的思考力を持っているため、即戦力として期待されます。
公務員も有力な選択肢の一つです。国家公務員(総合職・一般職)、地方公務員、裁判所事務官などでは、法律知識を活かした業務に従事できます。特に裁判所事務官は、法廷での手続き補助や判決書作成の補助など、法律に密接に関わる業務を担当します。
司法試験受験経験を活かせる法務職・士業へのキャリアチェンジ
司法試験の勉強で培った法律知識は、他の士業資格の取得にも活かせます。行政書士、司法書士、社会保険労務士などの資格は、司法試験で学んだ民法や憲法、行政法の知識が大いに役立ちます。
行政書士は、官公署への許認可申請書類の作成や、契約書・遺言書の作成などを業務とする資格です。司法試験で学んだ民法、行政法の知識を直接活用できるため、比較的短期間で資格取得を目指せます。独立開業も可能であり、自分のペースで働けることが魅力です。
司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所での訴訟代理などを業務とする資格です。司法試験で学んだ民法の知識が基礎となり、追加で不動産登記法や商業登記法を学ぶことで合格を目指せます。司法書士も独立開業が可能であり、安定した需要があります。
司法試験不合格という結果は辛いものですが、それまでの努力が無駄になるわけではありません。法律知識は一生の財産であり、さまざまなキャリアで活かすことができます。自分の強みと希望を冷静に見極め、最適な進路を選択することが大切です。
司法試験の回数制限に関してもっと詳しい記事はこちら
司法試験の回数制限|5回まで受験できる理由と撤廃議論を解説
-
 スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら
スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら -
 司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら
司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら -
 合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
司法試験の合格発表に関連するよくある質問(FAQ)
司法試験の合格発表に関して、受験生からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q. 司法試験の合格発表は何時に行われますか?
司法試験の合格発表は、短答式試験、最終合格ともに午後4時に行われます。この時刻に法務省ホームページに合格者受験番号一覧が掲載され、各試験地の法務局または地方法務局にも掲示板で合格者受験番号が掲示されます。発表直後はウェブサイトへのアクセスが集中するため、時間に余裕を持って確認することをおすすめします。
Q. 司法試験の短答式試験で自己採点は必要ですか?
司法試験の短答式試験では自己採点が非常に重要です。試験終了後に法務省ホームページで正解が公表されるため、自分の解答と照らし合わせて得点を計算できます。自己採点で合格の可能性が高いと判断できれば、合格発表を待たずに論文式試験の振り返りや次のステップの準備を始められます。逆に合格が難しいと判断した場合は、早期に次年度の対策を開始できます。
Q. 司法試験の合格者氏名は公表されますか?
司法試験の合格者氏名は官報に掲載される形で公表されます。法務省ホームページでは受験番号のみが公表され、氏名は掲載されません。官報には合格者の氏名が受験地ごとに五十音順で掲載されますが、受験番号や出身法科大学院などの情報は含まれません。官報への掲載は、法曹という公的な職務に就くための資格試験であることから、一定の公開性が求められているためです。
Q. 司法試験の成績通知書はいつ届きますか?
司法試験の成績通知書は、合格発表から約2週間後に郵送されます。短答式試験の成績通知書は6月下旬、最終合格の成績通知書兼合格通知書は9月下旬に届くのが通常です。成績通知書には、各科目の得点、総合得点、成績順位、合格最低点などが記載されており、自分の実力を客観的に把握できる重要な書類です。特に最終合格の成績通知書は、就職活動で提出を求められることがあるため、大切に保管しましょう。
Q. 司法試験合格後はすぐに司法修習が始まりますか?
司法試験の最終合格発表は9月中旬ですが、司法修習の開始は12月上旬です。合格発表から司法修習開始までの約3ヶ月間に、司法修習生採用選考(10月上旬)、修習地発表(10月下旬)、事前課題の配布(11月上旬)などのイベントがあります。この期間に多くの合格者は就職活動を行い、修習地が遠方の場合は引越しの準備も進めます。計画的にスケジュールを管理することが重要です。
Q. 司法試験に不合格の場合、何回まで再受験できますか?
司法試験は、法科大学院修了または予備試験合格から5年以内に5回まで受験できます。この受験回数制限を超えると、再度法科大学院を修了するか予備試験に合格しない限り、司法試験を受験することはできません。不合格だった場合は、残りの受験回数を確認し、再挑戦するか別の進路を選ぶか、冷静に判断することが大切です。司法試験の回数制限では、5回制限の詳細と撤廃議論について詳しく解説しています。
まとめ:司法試験の合格発表日程と結果確認の完全ガイド
本記事では、司法試験の合格発表日程と確認方法について詳しく解説しました。重要なポイントを改めて確認しましょう。
- 合格発表の日程と時刻:短答式試験の合格発表は6月上旬、最終合格発表は9月中旬に行われ、いずれも午後4時に法務省ホームページで公開されます。発表日と時刻を正確に把握し、複数の確認方法を準備しておくことが大切です。
- 結果確認の方法:法務省ホームページでの受験番号確認、試験地の掲示板での確認、官報での氏名確認など、複数の方法で結果を確認できます。それぞれの方法の特徴を理解し、自分に合った方法を選びましょう。
- 合格後のスケジュール:合格発表から司法修習開始までの約3ヶ月間には、司法修習生採用選考、修習地発表、就職活動など、重要なイベントが続きます。事前にスケジュールを把握し、計画的に準備を進めることが成功への鍵となります。
司法試験の合格発表に向けて準備ができたら、次は合格後のキャリアについても考えてみましょう。司法試験の合格率推移と司法試験の合格者データを参考に、法曹としてのキャリアを具体的にイメージすることをおすすめします。
本記事を通じて、司法試験の合格発表日程と確認方法、そして合格後の流れを理解いただけたはずです。これらの情報を活用して、司法試験合格という目標の実現に向けて着実に前進しましょう。
-
 スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら
スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら -
 司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら
司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら -
 合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
司法試験の関連記事

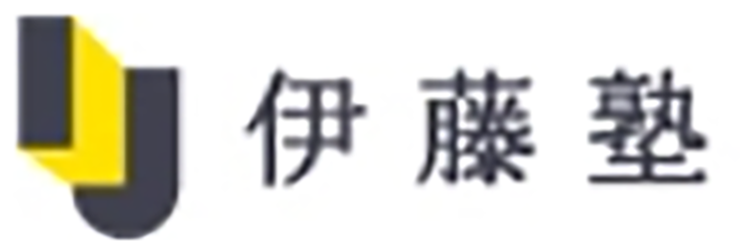


コメント