司法試験の受験資格について知りたいあなたへ。「司法試験を受けるにはどうすればいいのか」「法科大学院と予備試験のどちらを選ぶべきか」という疑問は、それぞれのルートの特徴を理解することで解決できます。
本記事では、司法試験の受験資格を得る2つのルート、それぞれの特徴と期間、費用面での違いについて、実際のデータを交えて詳しく解説します。この情報をもとに、司法試験合格に向けて、自分に最適なルートを選択しましょう。
- 司法試験の受験資格を得る2つのルート(法科大学院・予備試験)
- それぞれのルートの期間・費用・合格率の違い
- 自分の状況に合った受験資格取得ルートの選び方
- 受験資格の有効期限と回数制限の詳細
- 受験資格取得ルートは2つ:司法試験を受験するには、法科大学院修了か予備試験合格のいずれかが必要です。それぞれ期間や費用、難易度が大きく異なるため、自分の状況に合わせた選択が重要です。
- 有効期限は5年間で5回まで:受験資格取得後、5年間で最大5回まで司法試験を受験できます。この期間を超えると受験資格が失効し、再度法科大学院修了か予備試験合格が必要になります。
- 予備試験ルートは学歴不問:予備試験には受験資格がなく、中卒・高卒でも挑戦可能です。一方、法科大学院ルートは大学卒業が必要ですが、在学中受験制度により最短5年での合格を目指せます。
-
 スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら
スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら -
 司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら
司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら -
 合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
司法試験の受験資格とは
司法試験の受験資格とは、司法試験を受験するために必要な条件のことです。現在の制度では、法科大学院を修了するか予備試験に合格することで受験資格を得られます。この制度は2006年に導入され、法曹養成の質を確保するために設けられています。
司法試験は弁護士、裁判官、検察官といった法曹三者になるための国家試験であり、その受験資格を得ることが第一歩となります。受験資格を取得すると、5年間で最大5回まで司法試験に挑戦できます。
司法試験を受験するための2つのルート
司法試験の受験資格を得る方法は、法科大学院ルートと予備試験ルートの2つがあります。
法科大学院ルートは、法科大学院(ロースクール)で専門的な法律教育を受けて修了することで受験資格を得る方法です。未修者コースは3年間、既修者コースは2年間の課程を修了する必要があります。2023年からは在学中受験制度も導入され、修了前でも一定の条件を満たせば受験可能になりました。
予備試験ルートは、予備試験(司法試験予備試験)に合格することで受験資格を得る方法です。予備試験は法科大学院修了と同等の学識および能力を有するかを判定する試験で、合格者は法科大学院を経由せずに司法試験を受験できます。年齢や学歴による制限がないため、中卒・高卒の方でも挑戦できます。
司法試験の受験資格が必要な理由
司法試験の受験資格制度が設けられている理由は、法曹として必要な基礎的な知識と能力を担保するためです。弁護士や裁判官、検察官は人々の権利や自由に深く関わる職業であり、高度な法的知識と実務能力が求められます。
2006年の新司法試験導入以前は、旧司法試験に受験資格の制限がありませんでした。しかし、体系的な法律教育を受けずに試験対策だけで合格を目指す受験生が多く、法曹養成の質が課題となっていました。そこで法科大学院制度を中核とする新しい法曹養成制度が導入され、受験資格要件が設けられました。
予備試験制度は、経済的事情や既に社会で実務経験を積んでいる方など、法科大学院に通うことが困難な人にも門戸を開くために設けられています。これにより、多様なバックグラウンドを持つ人材が法曹を目指せる仕組みとなっています。
受験資格の有効期限と回数制限
司法試験の受験資格には、5年間で5回までという制限があります。これは法科大学院修了または予備試験合格から5年以内に最大5回まで受験できるという意味です。
具体的には、法科大学院を2024年3月に修了した場合、2029年までに実施される司法試験のうち5回まで受験できます。予備試験に2024年に合格した場合も同様に、2029年までに5回の受験機会があります。
この制限は、受験生が無制限に受験を繰り返すことを防ぎ、一定期間内での合格を促すために設けられています。2023年度のデータでは、司法試験全体の合格率は45.3%で、多くの受験生が5回以内に合格を果たしています(法務省発表データ)。
もし5年間で5回の受験をすべて使い切っても合格できなかった場合、受験資格は失効します。その後再び司法試験を受験するには、法科大学院を再度修了するか、予備試験に再度合格する必要があります。この点については、司法試験の回数制限で詳しく解説しています。
司法試験の回数制限に関してもっと詳しい記事はこちら
司法試験の回数制限|5回まで受験できる理由と撤廃議論を解説
司法試験の受験資格①法科大学院ルート
法科大学院ルートは、法科大学院(ロースクール)で体系的な法律教育を受けて受験資格を得る方法です。2004年に法科大学院制度が開始され、理論と実務を架橋した教育により、質の高い法曹を養成することを目的としています。
法科大学院には既修者コース(2年間)と未修者コース(3年間)があり、法学部出身か否かや既存の法律知識のレベルに応じて選択できます。全国に約30の法科大学院があり、各大学で特色ある教育プログラムが提供されています。
法科大学院修了による受験資格
法科大学院を修了すると、司法試験の受験資格が付与されます。修了の条件は、所定の単位を取得し、必要な課程を履修することです。既修者コースでは2年間で約60単位、未修者コースでは3年間で約90単位の取得が一般的です。
法科大学院では、憲法、民法、刑法などの基本科目から、実務基礎科目、選択科目まで幅広く学びます。少人数制のゼミ形式の授業や、判例研究、模擬裁判などの実践的な教育も特徴です。
修了時には厳格な成績評価が行われ、一定の成績基準を満たす必要があります。成績が不十分な場合は進級や修了ができないこともあるため、在学中は継続的な学習が求められます。法科大学院修了により得られる受験資格は、修了日から5年間有効です。
法科大学院の既修者コースと未修者コース
法科大学院には、既修者コースと未修者コースの2つのコースがあります。
既修者コースは、法学部出身者や既に法律の基礎知識を有する人を対象とした2年制のコースです。入学試験では法律科目の試験が課され、一定の法律知識が前提とされます。1年次の基礎科目が免除されるため、より発展的な内容や実務的な科目に重点を置いた学習ができます。
未修者コースは、法学部以外の出身者や法律初学者を対象とした3年制のコースです。1年次は憲法、民法、刑法などの基礎科目をゼロから学び、2年次以降で既修者コースと合流して発展的な科目を学びます。入学試験では法律科目の試験がなく、適性試験や小論文、面接などで選考されます。
コース選択のポイントは、自身の法律知識レベルと学習期間、費用のバランスです。法学部出身者でも基礎から丁寧に学びたい場合は未修者コースを選択することもできますし、法学部以外の出身でも独学で法律を学んでいる場合は既修者コース受験を目指すことも可能です。
在学中受験制度(2023年~)
2023年から導入された在学中受験制度は、法科大学院在学中に司法試験を受験できる制度です。一定の成績要件を満たし、学長の認定を受けた学生が対象となります。
従来は法科大学院を修了してから司法試験を受験する必要がありましたが、在学中受験制度により最終学年で受験が可能になりました。これにより、修了年度に合格すれば、すぐに司法修習に進むことができ、法曹になるまでの期間を短縮できます。
在学中受験の条件は、法科大学院によって異なりますが、一般的には以下のような要件があります。最終学年に在籍していること、一定以上のGPA(成績評価平均)を維持していること、必要な単位を取得していること、学長による認定を受けることなどです。
在学中受験で不合格だった場合でも、修了後に再受験できます。ただし、受験回数は在学中受験も含めて5年間で5回までという制限があるため、計画的な受験が重要です。在学中受験制度により、法科大学院ルートの時間的メリットが向上しています。
法曹コース(法学部3年+法科大学院2年)
法曹コースは、法学部3年間と法科大学院2年間を組み合わせた最短5年で司法試験受験資格を得られる制度です。2020年度から導入され、法曹志望者の経済的・時間的負担を軽減することを目的としています。
法曹コースに在籍する学部生は、3年次終了時に法科大学院の既修者コース入試を受験し、合格すれば4年目から法科大学院に進学できます。学部4年次を飛ばして進学するため、従来の法学部4年+法科大学院2年の計6年間から1年短縮されます。
法曹コースの特徴は、学部と法科大学院が連携したカリキュラムです。学部在学中から法科大学院の授業を一部履修できたり、法科大学院教員による指導を受けられたりします。また、法曹コース生を対象とした特別選抜入試を実施する法科大学院もあります。
ただし、法曹コースを選択しても必ずしも5年で法曹になれるわけではありません。法科大学院入試に合格する必要があり、さらに在学中受験制度を利用して司法試験に合格する必要があります。それでも、時間と費用を削減できる有効な選択肢として、法学部生の間で注目されています。
司法試験と法科大学院に関してもっと詳しい記事はこちら
司法試験と法科大学院(ロースクール)|受験資格と選び方を解説
-
 スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら
スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら -
 司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら
司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら -
 合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
司法試験の受験資格②予備試験ルート
予備試験ルートは、予備試験に合格することで司法試験の受験資格を得る方法です。正式には「司法試験予備試験」といい、法科大学院修了者と同等の学識および能力を有するかを判定する試験として位置づけられています。
予備試験ルートは、法科大学院に通う時間や費用の負担が困難な方、既に社会人として働いている方、あるいは若いうちから法曹を目指したい方にとって有効な選択肢です。年齢や学歴の制限がないため、多様なバックグラウンドを持つ人が挑戦できます。
予備試験合格による受験資格
予備試験に合格すると、法科大学院修了者と同じく司法試験の受験資格が得られます。合格発表は通常11月頃に行われ、翌年の司法試験から受験可能になります。例えば、2024年に予備試験に合格した場合、2025年の司法試験から受験できます。
予備試験合格による受験資格も、法科大学院ルートと同様に5年間で5回までという制限があります。合格年から起算して5年以内に司法試験に合格する必要があります。
予備試験合格者の司法試験合格率は非常に高く、2023年度は93.5%に達しています(法務省発表データ)。これは法科大学院修了者全体の合格率45.3%を大きく上回る数字です。予備試験に合格できるだけの実力があれば、司法試験合格の可能性も高いといえます。
予備試験の試験内容と難易度
予備試験は短答式試験、論文式試験、口述試験の3段階で構成されています。
短答式試験は5月に実施され、憲法、民法、刑法の3科目に加えて、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法、商法の一般教養科目が出題されます。合計で約7時間の試験で、マークシート方式により解答します。
論文式試験は7月に実施され、短答式試験合格者のみが受験できます。出題科目は、必須科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)と一般教養科目です。記述式で、法的思考力や論述力が問われます。
口述試験は10月に実施され、論文式試験合格者のみが受験できます。民事法、刑事法の2科目について、口頭で質疑応答形式により試験が行われます。法的知識だけでなく、コミュニケーション能力や臨機応変な対応力も評価されます。
予備試験の難易度は極めて高く、2023年度の最終合格率は約4.2%でした。受験者数は約13,000人で、最終合格者は約500人程度です。短答式試験の合格率が約20%、論文式試験の合格率が約20%、口述試験の合格率が約90%という数字からも、各段階での競争の激しさがうかがえます。
予備試験には受験資格が不要
予備試験の大きな特徴は、受験資格に制限がないことです。年齢、学歴、国籍、職業などによる制限は一切なく、誰でも受験できます。
この制度により、中卒や高卒の方でも司法試験を目指すことができます。実際に、高校在学中や大学1年生で予備試験に合格する人もおり、20歳前後で司法試験に合格する若手法曹も誕生しています。
また、社会人として働きながら予備試験に挑戦する人も多くいます。会社員、公務員、他の資格を持つ専門職など、さまざまなバックグラウンドを持つ受験生が予備試験を通じて法曹を目指しています。既に社会経験を積んだ人材が法曹になることで、多様な視点や専門知識を法律実務に活かせるというメリットもあります。
受験資格がないからこそ、予備試験は真の実力勝負の場といえます。法律知識や思考力、論述力があれば、学歴や経歴に関係なく合格を目指せる公平な制度として機能しています。
予備試験ルートのメリット
予備試験ルートには、法科大学院ルートと比較していくつかのメリットがあります。
最大のメリットは時間と費用の節約です。法科大学院は2-3年間通う必要があり、学費も年間100-150万円程度かかります。一方、予備試験は独学でも挑戦でき、予備校を利用しても法科大学院より安価に済むことが多いです。
2つ目のメリットは、早期合格の可能性です。大学生が在学中に予備試験に合格し、卒業後すぐに司法試験に合格すれば、20代前半で法曹になることができます。法科大学院ルートでは最短でも20代半ばになるため、若いうちからキャリアをスタートできる点が魅力です。
3つ目のメリットは、高い司法試験合格率です。前述のとおり、予備試験合格者の司法試験合格率は90%以上と非常に高く、予備試験に合格できれば司法試験合格の可能性も高まります。
ただし、予備試験自体の難易度が極めて高く、合格率は4%程度です。多くの受験生が数年かけて挑戦し、途中で断念する人も少なくありません。予備試験ルートを選択する場合は、長期的な覚悟と計画的な学習が不可欠です。司法試験の勉強法では、効果的な学習方法を詳しく解説しています。
司法試験の法科大学院ルートと予備試験ルートの比較
法科大学院ルートと予備試験ルートには、それぞれ特徴があり、自分の状況や目標に合わせて選択する必要があります。ここでは、合格率、費用、期間、メリット・デメリットの観点から両ルートを比較します。
どちらのルートを選ぶべきかは、時間、費用、学習スタイル、現在の法律知識レベル、年齢など、さまざまな要素を考慮して決める必要があります。以下の比較データを参考に、自分に最適なルートを見極めましょう。
合格率の比較
司法試験の合格率は、予備試験ルートと法科大学院ルートで大きく異なります。
2023年度のデータでは、予備試験合格者の司法試験合格率は93.5%と極めて高い数値を示しています。一方、法科大学院修了者全体の合格率は45.3%で、予備試験ルートの半分以下です(法務省発表データ)。
ただし、この数字だけで予備試験ルートが優れていると判断することはできません。予備試験自体の合格率が約4.2%と非常に低く、司法試験を受験できる段階に到達すること自体が極めて困難だからです。
法科大学院ルートでは、在学中に体系的な法律教育を受けられるため、一定の合格率を維持できています。特に上位の法科大学院では司法試験合格率が70-80%を超えるところもあり、質の高い教育環境が整っています。
総合的に見ると、予備試験に合格できる実力があれば司法試験合格の可能性は極めて高いですが、予備試験合格までのハードルが非常に高いといえます。法科大学院ルートは、着実に学習を進めれば一定の合格可能性を確保できるルートです。司法試験の合格率では、さらに詳細なデータ分析を行っています。
費用の比較
法科大学院ルートと予備試験ルートでは、必要な費用に大きな差があります。
法科大学院ルートの場合、学費が主な費用です。国立の法科大学院では年間約80万円、私立では年間100-150万円が一般的です。既修者コース(2年間)なら200-300万円、未修者コース(3年間)なら300-450万円程度が必要です。これに加えて、教科書代、生活費、予備校の単科講座費用などがかかります。
予備試験ルートの場合、独学であれば教科書代と受験料のみで済むため、数十万円程度で抑えられます。予備校の予備試験対策講座を受講する場合でも、100-200万円程度が一般的です。法科大学院の学費と比較すると、大幅にコストを削減できます。
ただし、予備試験に合格するまでの年数も考慮する必要があります。多くの受験生が2-5年かけて予備試験に挑戦するため、その期間の予備校費用や生活費を含めると、トータルコストは増加します。また、働きながら勉強する場合、機会費用(勉強に充てる時間を仕事に使った場合の収入)も考慮すべきです。
経済的な観点では予備試験ルートが有利ですが、法科大学院では奨学金制度も充実しています。給付型奨学金や授業料減免制度を利用できれば、経済的負担を軽減できます。自身の経済状況と利用できる制度を総合的に検討することが重要です。
期間の比較
法曹になるまでの期間も、ルート選択の重要な要素です。
法科大学院ルートの場合、既修者コース2年間または未修者コース3年間の在学期間が必要です。在学中受験制度を利用すれば、最終学年で司法試験を受験できるため、修了と同時に合格すれば最短2-3年で司法試験に合格できます。法曹コースを利用すれば、法学部3年+法科大学院2年の計5年で受験資格を得られます。
予備試験ルートの場合、合格までの期間は人により大きく異なります。大学在学中に1-2年で合格する人もいれば、社会人として働きながら5年以上かけて合格する人もいます。2023年度のデータでは、予備試験合格者の平均年齢は26.1歳で、多くの受験生が数年かけて合格しています。
最短ルートで比較すると、予備試験ルートの方が早く法曹になれる可能性があります。大学1-2年生で予備試験に合格し、翌年の司法試験に合格すれば、20代前半で法曹になることができます。一方、法科大学院ルートでは最短でも20代半ばになります。
ただし、予備試験の難易度を考えると、多くの受験生にとって法科大学院ルートの方が確実に一定期間で受験資格を得られる選択肢といえます。時間をかけてでも着実に進みたい人には法科大学院ルート、早期合格を目指して挑戦したい人には予備試験ルートが向いています。
それぞれのメリット・デメリット
法科大学院ルートと予備試験ルートには、それぞれ長所と短所があります。
法科大学院ルートのメリット
- 体系的な法律教育を受けられる
- 少人数制のゼミや実務教育で実践力が身につく
- 司法試験の合格率が一定水準で安定している
- 法曹ネットワークを構築できる
- 奨学金制度が充実している
法科大学院ルートのデメリット
- 2-3年の在学期間が必要
- 学費が高額(200-450万円程度)
- 入学試験に合格する必要がある
- 進級・修了の成績要件がある
予備試験ルートのメリット
- 費用を大幅に削減できる
- 期間の制約がなく、自分のペースで学習できる
- 若いうちから法曹を目指せる
- 合格後の司法試験合格率が極めて高い
- 受験資格に制限がない
予備試験ルートのデメリット
- 予備試験の合格率が約4%と極めて低い
- 独学では学習方法や進捗管理が難しい
- 体系的な教育を受けられない
- 合格までに数年かかることが多い
- モチベーション維持が困難
どちらのルートを選ぶべきかは、自分の状況、学習スタイル、目標によって異なります。法学部生で着実に学びたい人は法科大学院ルート、費用を抑えたい社会人や早期合格を目指す人は予備試験ルートを検討するとよいでしょう。
司法試験の合格率に関してもっと詳しい記事はこちら
司法試験の合格率推移|法科大学院別・予備試験組の傾向分析
司法試験の受験資格に年齢制限・学歴制限はあるか
司法試験の受験資格には、年齢や学歴による制限はありません。法科大学院を修了するか予備試験に合格すれば、何歳でも、どのような学歴でも司法試験を受験できます。
この制度により、若い世代から高齢者まで、さまざまな年齢層の人が法曹を目指すことができます。また、学歴に関わらず、実力次第で法曹になる道が開かれています。多様なバックグラウンドを持つ法曹が誕生することで、社会のさまざまなニーズに対応できる法律サービスが提供されています。
司法試験に年齢制限はない
司法試験には年齢による上限・下限の制限がありません。法科大学院を修了した人、または予備試験に合格した人であれば、年齢に関係なく受験できます。
実際に、10代後半から70代まで、幅広い年齢層の受験生が司法試験に挑戦しています。若い受験生は長いキャリアを見据えて早期に法曹を目指し、高齢の受験生は豊富な社会経験を法律実務に活かすことを目指しています。
年齢制限がないことで、人生の様々な段階で法曹を目指すことができます。大学卒業後すぐに法科大学院に進学する人もいれば、一度社会人として働いた後、30代や40代で法曹を志す人もいます。また、定年退職後にセカンドキャリアとして法曹を目指す人もいます。
年齢による制限がない一方で、司法試験の回数制限(5年間で5回まで)は適用されます。受験資格取得から5年以内に合格する必要があるため、年齢に関わらず計画的な学習が重要です。
最年少・最高齢合格者の記録
司法試験の合格者には、驚くほど若い人や高齢の人もいます。
最年少合格記録は、予備試験を経由したルートで達成されています。近年では、18歳や19歳で司法試験に合格する人が登場しています。これらの合格者は、高校生や大学1-2年生のうちに予備試験に合格し、翌年の司法試験に合格したケースです。予備試験に受験資格がないため、若いうちから挑戦できることがこの記録を可能にしています。
一方、最高齢合格者は60代後半から70代の方の記録があります。これらの合格者の多くは、社会人として長いキャリアを積んだ後、法曹を志して予備試験や法科大学院に挑戦した方々です。豊富な社会経験と法律知識を組み合わせて、高齢でも合格を果たしています。
これらの記録は、司法試験が年齢に関係なく、実力次第で合格できる試験であることを示しています。若さや経験年数ではなく、法律知識と思考力が評価される公平な試験といえます。
司法試験の平均合格年齢
司法試験合格者の平均年齢は、ルートによって異なります。
2023年度のデータでは、予備試験ルートの合格者平均年齢は約26歳、法科大学院ルートの合格者平均年齢は約28歳です(法務省発表データ)。全体の平均年齢は27-28歳程度で推移しています。
予備試験ルートの合格者が若い傾向にあるのは、大学在学中に予備試験に合格し、卒業後すぐに司法試験に合格する人が多いためです。一方、法科大学院ルートでは、学部4年+法科大学院2-3年の期間が必要なため、合格年齢が若干高くなります。
ただし、平均年齢はあくまで目安であり、個人差が大きいのが実情です。20代前半で合格する人もいれば、40代、50代で合格する人もいます。年齢に関わらず、自分のペースで学習を進めることが大切です。
社会人として働きながら法曹を目指す場合、合格年齢は30代以降になることが一般的です。司法試験の勉強時間では、働きながらの学習計画について詳しく解説しています。
学歴による制限も基本的にない
司法試験の受験資格自体には学歴制限がありません。ただし、受験資格を得るための2つのルートで、学歴要件が異なります。
予備試験ルートには一切の学歴制限がなく、中卒、高卒、大卒など、どのような学歴でも受験できます。予備試験に合格すれば、学歴に関係なく司法試験を受験できます。
法科大学院ルートの場合、法科大学院に入学するためには原則として大学卒業(学士の学位取得)が必要です。未修者コースでは法学部である必要はなく、文学部や理学部、工学部など、どの学部出身でも入学できます。既修者コースは法律知識が前提となるため、法学部出身者が多いですが、独学で法律を学んだ他学部出身者でも受験可能です。
つまり、予備試験ルートを選べば、学歴に関係なく司法試験を目指せます。法科大学院ルートを選ぶ場合のみ、大学卒業が必要になります。自分の学歴と状況に応じて、適切なルートを選択することが重要です。
司法試験は中卒・高卒でも受験できるか
司法試験は、予備試験ルートを選択すれば、中卒・高卒でも受験可能です。予備試験には受験資格がないため、学歴に関係なく挑戦できます。ただし、法科大学院ルートを選ぶ場合は大学卒業が必要です。
中卒・高卒から法曹を目指す場合、予備試験の合格が必須となります。予備試験の難易度は極めて高いですが、実際に高校在学中や高卒後すぐに予備試験に合格している人もおり、学歴がハンディキャップにならない試験といえます。
予備試験ルートなら中卒・高卒でも可能
予備試験には年齢、学歴、国籍、職業による制限が一切ありません。そのため、中卒・高卒の方でも予備試験を受験でき、合格すれば司法試験の受験資格を得られます。
実際に、高校在学中に予備試験に合格する人も毎年数名います。これらの合格者は、中学生や高校生のうちから法律学習を始め、予備校の講座や独学で着実に実力をつけています。高い学習意欲と計画的な勉強により、若くして予備試験合格を果たしています。
高卒で予備試験に挑戦する場合、大学に進学せずに予備試験に専念する方法もあります。この場合、予備校に通いながら集中的に勉強することで、短期間での合格を目指せます。大学進学の費用や時間を節約できる点がメリットです。
ただし、予備試験の合格率は約4%と極めて低く、合格までに数年かかることも珍しくありません。中卒・高卒から法曹を目指す場合は、長期的な覚悟と強い意志が必要です。また、仮に予備試験に合格できなかった場合のキャリアプランも考えておくことが重要です。
法科大学院ルートは大学卒業が必要
法科大学院に入学するためには、原則として大学を卒業している必要があります。これは法科大学院が専門職大学院として、学士の学位を有する者を入学対象としているためです。
中卒・高卒の方が法科大学院ルートで法曹を目指す場合、まず大学に進学して卒業する必要があります。法学部に進学して法律の基礎を学ぶこともできますし、他の学部に進学した後に未修者コースで法律を学ぶこともできます。
大学進学から法科大学院修了までには、最短で学部4年+法科大学院2年の計6年が必要です。法曹コースを利用すれば学部3年+法科大学院2年の計5年に短縮できますが、いずれにしても相当な期間が必要です。
一方で、大学で法律以外の専門分野を学び、その知識を法律実務に活かすこともできます。例えば、理系学部で工学や医学を学んだ後、法科大学院で知的財産法や医事法を専攻すれば、専門性の高い法曹を目指せます。
中卒・高卒から法曹を目指す場合、早期に法曹になりたいなら予備試験ルート、体系的な教育を受けたいなら大学進学後に法科大学院ルートを選ぶとよいでしょう。
高校生・大学生の予備試験受験
高校生や大学生の間に予備試験に挑戦する人が増えています。これは予備試験に受験資格がないため、学生のうちから挑戦できるためです。
高校生が予備試験を受験する場合、授業と両立しながら勉強することになります。多くの場合、予備校のオンライン講座や通信講座を利用して学習します。高校の勉強との両立は容易ではありませんが、時間管理と効率的な学習により、合格を果たす高校生もいます。
大学生の場合、特に法学部生の間で予備試験受験が人気です。大学1-2年生のうちに予備試験に合格し、在学中に司法試験に合格すれば、卒業後すぐに司法修習に進むことができます。これにより、同級生より早く法曹としてのキャリアをスタートできます。
大学生が予備試験を受験するメリットは、時間の有効活用ができることです。大学の授業で法律の基礎を学びながら、予備試験の勉強を並行して進められます。また、万が一予備試験に合格できなくても、法科大学院進学という選択肢が残されています。
ただし、予備試験の勉強は大学の授業とは異なる側面があり、相当な学習時間が必要です。司法試験の勉強時間では、効率的な学習計画の立て方を解説しています。大学生活と予備試験勉強のバランスを取りながら、計画的に進めることが重要です。
司法試験の受験資格はどちらのルートを選ぶべきか
司法試験の受験資格取得ルートは、自分の状況、目標、学習スタイルに応じて選択する必要があります。法科大学院ルートと予備試験ルートには、それぞれ向いている人のタイプがあります。
ここでは、大学生、社会人、法学部生、非法学部生といった立場別に、どちらのルートが適しているかを解説します。また、時間と費用の観点からの選択基準も提示します。自分の状況を客観的に分析し、最適なルートを選びましょう。
大学生におすすめのルート
大学生の場合、法学部生か非法学部生かによって推奨ルートが異なります。
法学部生の場合、法科大学院ルートと予備試験ルート、どちらも選択肢になります。大学の授業で法律の基礎を学びながら、並行して予備試験の勉強をすることが可能です。予備試験に合格できれば時間と費用を大幅に節約できますが、合格できなかった場合でも法科大学院進学という選択肢が残ります。
法曹コースに在籍している法学部生は、法科大学院ルートを軸に考えつつ、余裕があれば予備試験にも挑戦するのが効率的です。法科大学院の特別選抜入試を利用できるため、確実に受験資格を得られる道を確保しながら、予備試験合格を目指すことができます。
非法学部生の場合、法科大学院の未修者コースが確実な選択肢です。法律初学者でも3年間で体系的に学べるため、着実に実力をつけられます。ただし、独学で法律を学ぶ意欲と時間があれば、予備試験に挑戦することも可能です。
いずれの場合も、大学生は時間を比較的自由に使えるため、効率的な学習計画を立てることが重要です。司法試験予備校の選び方では、学生向けの講座選択について詳しく解説しています。
社会人におすすめのルート
社会人の場合、時間と費用の制約を考えると、予備試験ルートが現実的な選択肢になることが多いです。
働きながら法科大学院に通うことは、時間的に非常に困難です。法科大学院は平日昼間に授業があることが多く、仕事との両立が難しいのが実情です。一部の法科大学院では夜間コースや週末コースを設けていますが、数は限られています。
予備試験ルートであれば、働きながらでも自分のペースで勉強できます。通勤時間や休日を活用して学習し、予備校のオンライン講座や通信講座を利用すれば、効率的に学習を進められます。仕事を辞めずに法曹を目指せる点が大きなメリットです。
ただし、働きながらの予備試験合格は容易ではありません。1日2-3時間の学習時間を確保し、3-5年の長期計画で臨む覚悟が必要です。仕事の繁忙期や転勤、結婚・出産などのライフイベントも考慮しながら、柔軟に学習計画を調整することが重要です。
社会人が法曹を目指す場合、キャリアの中断や転職のリスクも考慮する必要があります。予備試験に何年挑戦しても合格できない場合、法曹への道を断念する可能性もあります。リスクとリターンを慎重に検討し、家族や職場の理解を得た上で挑戦することをおすすめします。
法学部生と非法学部生での違い
法学部生と非法学部生では、既存の法律知識のレベルが異なるため、適したルートが変わります。
法学部生は、大学の授業で憲法、民法、刑法などの基本科目を学んでいるため、予備試験や法科大学院入試に対応しやすい立場にあります。既に法律の基礎知識があるため、既修者コース受験や予備試験短答式試験の対策がしやすいです。
法学部生におすすめのルートは、法科大学院の既修者コースまたは予備試験です。既修者コースであれば2年間で修了でき、時間と費用を節約できます。予備試験を目指す場合も、大学の授業と並行して効率的に学習を進められます。
非法学部生は、法律初学者として学習をゼロから始める必要があります。基礎から体系的に学べる法科大学院の未修者コースが、最も確実な選択肢です。3年間かけて丁寧に学ぶことで、しっかりとした法律知識を身につけられます。
非法学部生が予備試験を目指す場合、独学での学習が中心となります。予備校の初学者向け講座を受講し、基礎から応用までを段階的に学ぶ必要があります。法学部生と比べて学習期間が長くなる傾向がありますが、強い意志と計画的な学習により合格を果たす非法学部生も多くいます。
時間・費用面での選択基準
時間と費用は、ルート選択の重要な要素です。
時間を優先する場合
早く法曹になりたい場合は、予備試験ルートが有利です。大学在学中に予備試験に合格し、翌年の司法試験に合格すれば、20代前半で法曹になれます。ただし、予備試験の難易度が高いため、合格までに数年かかることも覚悟する必要があります。
確実に一定期間で受験資格を得たい場合は、法科大学院ルートが安全です。既修者コースなら2年、未修者コースなら3年で受験資格を得られます。法曹コースを利用すれば、学部から通算で5年に短縮できます。
費用を優先する場合
費用を抑えたい場合は、予備試験ルートが圧倒的に有利です。独学なら数十万円、予備校を利用しても100-200万円程度で済みます。法科大学院の学費200-450万円と比較すると、大幅にコストを削減できます。
ただし、予備試験に合格するまでの年数が長引くと、その間の予備校費用や生活費、機会費用も考慮する必要があります。また、法科大学院には奨学金制度も充実しているため、経済的支援を受けられる可能性もあります。
バランスを重視する場合
時間と費用のバランスを重視する場合、法学部生なら法科大学院の既修者コース、非法学部生なら未修者コースを軸に考え、余裕があれば予備試験にも挑戦するのが現実的です。法科大学院という確実な道を確保しながら、予備試験で早期合格を目指すハイブリッド戦略といえます。
社会人の場合は、働きながら予備試験に挑戦し、合格が難しいと判断した段階で法科大学院進学を検討するという方法もあります。自分の状況と目標を定期的に見直しながら、柔軟にルートを選択することが重要です。
司法試験の受験資格取得から合格までの流れ
司法試験の受験資格を取得した後、実際に司法試験を受験し、合格後に司法修習を経て法曹になるまでの流れを解説します。受験資格取得はゴールではなく、法曹への道のりの第一歩です。
ここでは、出願手続きから合格発表、そして司法修習までの具体的なプロセスを説明します。それぞれの段階で必要な準備や注意点を理解し、スムーズに進められるようにしましょう。
受験資格取得後の出願手続き
司法試験の受験資格を取得したら、司法試験の出願手続きを行います。出願は例年11月頃に行われ、翌年5月の試験に向けて準備を進めます。
出願には、受験願書の提出、受験手数料の納付、受験資格を証明する書類(法科大学院修了証明書または予備試験合格証明書)の提出が必要です。出願はオンラインと郵送のいずれかで行うことができます。
出願時には、選択科目の選択も行います。論文式試験では、選択科目として倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法(公法系)、国際関係法(私法系)の中から1科目を選択します。自分の得意分野や将来の専門分野を考慮して選択しましょう。
出願締切は厳格に守られるため、期限に余裕を持って手続きを完了することが重要です。出願書類に不備があると受験できない可能性もあるため、必要書類を早めに準備し、確認を怠らないようにしましょう。
出願が受理されると、受験票が送付されます。受験票には受験番号や試験会場の情報が記載されているため、大切に保管してください。司法試験の日程では、出願から試験までの詳細なスケジュールを解説しています。
司法試験の受験から合格発表まで
司法試験は例年5月に実施されます。短答式試験と論文式試験が行われ、合計で4日間の日程で実施されます。
短答式試験は憲法、民法、刑法の3科目で、1日で実施されます。マークシート方式で、午前と午後に分けて行われます。短答式試験には足切り点が設定されており、一定の得点を取らないと論文式試験の採点対象になりません。
論文式試験は3日間にわたって実施されます。必須科目として公法系科目(憲法・行政法)、民事系科目(民法・商法・民事訴訟法)、刑事系科目(刑法・刑事訴訟法)が出題されます。さらに、選択科目も論文式で出題されます。すべて記述式で、法的思考力と論述力が問われます。
試験終了後、約3ヶ月半の採点期間を経て、9月上旬に合格発表が行われます。合格発表は法務省のウェブサイトに合格者の受験番号が掲載され、合格者には合格証書が郵送されます。
2023年度の司法試験合格率は45.3%で、受験者約3,900人のうち約1,780人が合格しました(法務省発表データ)。合格最低点は例年、総合得点の50-55%程度に設定されています。
試験の難易度や採点基準については、司法試験の短答式試験対策で詳しく解説しています。短答式試験と論文式試験、それぞれに適した対策を行うことが合格への鍵です。
合格後の司法修習
司法試験に合格したら、すぐに法曹として働けるわけではありません。合格後は司法修習を受ける必要があります。
司法修習は、最高裁判所が実施する約1年間の実務研修プログラムです。合格発表の約3ヶ月後、12月頃から司法修習が開始されます。修習生は全国の裁判所、検察庁、弁護士事務所で実務研修を受け、法曹としての実践的なスキルを学びます。
司法修習の期間は約1年間で、前期・実務修習・後期の3段階で構成されています。前期では司法研修所(埼玉県和光市)で集合研修を受け、実務修習では全国各地の裁判所、検察庁、弁護士事務所で実務を学び、後期では再び司法研修所で集合研修を受けます。
司法修習修了時には、司法修習生考試(通称「二回試験」)が実施されます。この試験に合格すると、司法修習を修了し、法曹資格を取得できます。二回試験の合格率は例年98%以上と高く、司法修習をしっかりと受けていればほぼ全員が合格します。
司法修習修了後は、弁護士、裁判官、検察官のいずれかの道に進みます。多くの修習生は弁護士を選択し、法律事務所に就職します。裁判官や検察官になるには、別途採用試験や選考を受ける必要があります。
司法修習期間中は、国から給付金(修習給付金)が支給されるため、経済的な心配なく修習に専念できます。こうして約1年間の司法修習を経て、晴れて法曹としてのキャリアをスタートさせることができます。
司法試験の日程に関してもっと詳しい記事はこちら
司法試験の日程|出願から合格発表までのスケジュール完全ガイド
司法試験の受験資格を失効した場合の対処法
司法試験の受験資格には5年間で5回までという制限があり、この期間内に合格できなかった場合、受験資格は失効します。受験資格が失効した後も法曹を目指したい場合の対処法を解説します。
受験資格の失効は、多くの受験生にとって重大な岐路となります。再挑戦するか、別の道を選ぶか、慎重に判断する必要があります。ここでは、失効後の選択肢と、再度受験資格を取得する方法について説明します。
5年間で合格できなかった場合
5年間で5回の受験機会をすべて使い切っても司法試験に合格できなかった場合、受験資格は失効します。この時点で、法曹への道は一旦閉ざされることになります。
受験資格が失効する受験生は一定数存在します。2023年度のデータでは、司法試験全体の合格率は45.3%で、5回の受験で合格できない人も少なくありません。特に法科大学院ルートの受験生の中には、複数回受験しても合格に至らないケースがあります。
受験資格失効のリスクがあるからこそ、計画的な学習と効果的な試験対策が重要です。1回目の受験で不合格だった場合、原因を分析し、2回目以降の対策を練り直す必要があります。短答式試験の足切りで不合格だった場合と、論文式試験で点数が伸びなかった場合では、必要な対策が異なります。
5回目の受験で不合格となる前に、法曹以外のキャリアパスも検討しておくことが賢明です。法律知識を活かせる職業は弁護士以外にも多くあります。企業の法務部門、行政機関、法律系の資格試験(司法書士、行政書士など)への転換も選択肢となります。
受験回数を重ねるごとに合格の可能性が低下する傾向があるため、3-4回目の受験段階で客観的に自分の実力を見極めることも必要です。家族や指導者と相談しながら、冷静に判断することをおすすめします。
再度受験資格を取得する方法
受験資格が失効した後も、再度受験資格を取得することは可能です。方法は大きく分けて2つあります。
1つ目は、法科大学院を再度受験して入学し、修了する方法です。既に法科大学院を修了している場合でも、再度入学することができます。既修者コースに入学すれば2年間で修了でき、再び受験資格を得られます。ただし、再度学費が必要になるため、経済的負担が大きいことが課題です。
2つ目は、予備試験に再度合格する方法です。予備試験に合格すれば、法科大学院を経由せずに受験資格を得られます。既に一度は司法試験を受験した経験があるため、法律知識はある程度維持されているはずです。予備試験対策に集中すれば、合格の可能性はあります。
どちらの方法を選ぶかは、時間、費用、年齢などの要素を総合的に判断する必要があります。法科大学院ルートは確実に受験資格を得られますが、2-3年の時間と学費が必要です。予備試験ルートは費用を抑えられますが、合格率が約4%と非常に低いため、再度数年かかる可能性もあります。
再挑戦する場合は、前回なぜ合格できなかったのかを徹底的に分析することが重要です。学習方法、試験対策、時間配分など、改善すべき点を明確にしてから再スタートしましょう。司法試験の勉強法では、効果的な学習方法を詳しく解説しています。
受験回数制限の考え方
受験回数制限の5年間で5回という制度には、賛否両論があります。制度の趣旨と、受験生が持つべき心構えについて説明します。
受験回数制限が設けられている理由は、受験生が無制限に受験を繰り返すことを防ぎ、一定期間内での合格を促すためです。また、法科大学院で学んだ知識が時代遅れにならないよう、一定期間内での合格を求める意図もあります。
一方で、この制限に対しては批判もあります。5回で合格できない人にも再挑戦の機会を与えるべきだという意見や、回数制限を撤廃すべきだという議論もあります。実際に、回数制限の見直しを求める動きも存在します。
受験生としては、現行の制度を前提に、限られた受験機会を最大限に活かすことが重要です。5回という制限があるからこそ、1回1回の受験を真剣に取り組み、毎回の受験で学びを得ることが大切です。
受験回数を重ねるにつれて精神的な負担も大きくなります。4回目、5回目の受験では、「最後のチャンス」というプレッシャーと向き合う必要があります。メンタルケアも含めて、総合的なサポート体制を整えることをおすすめします。
受験回数制限の詳細については、司法試験の回数制限で詳しく解説しています。制度の背景や撤廃議論についても触れているので、ぜひ参考にしてください。
司法試験の受験資格に関連するよくある質問(FAQ)
司法試験の受験資格について、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。受験資格取得を検討している方が抱く疑問に、具体的にお答えします。
Q. 司法試験の受験資格を得るには何年かかりますか?
司法試験の受験資格を得るまでの期間は、選択するルートによって異なります。
法科大学院ルートの場合、既修者コースなら2年間、未修者コースなら3年間が必要です。大学卒業が前提なので、大学4年間も含めると、法学部既修者コースで最短6年、未修者コースで7年かかります。法曹コースを利用すれば、法学部3年+法科大学院2年の計5年に短縮できます。
予備試験ルートの場合、合格までの期間は個人差が大きいです。最短では1年程度で合格する人もいますが、多くの受験生が2-5年かけて合格しています。2023年度の予備試験合格者の平均年齢は約26歳で、大学在学中から社会人まで幅広い年齢層が挑戦しています。
どちらのルートを選ぶかは、自分の状況と目標に応じて決めることが重要です。確実に一定期間で受験資格を得たいなら法科大学院ルート、時間と費用を節約したいなら予備試験ルートを検討しましょう。
Q. 司法試験の受験資格に年齢制限はありますか?
司法試験の受験資格に年齢制限はありません。法科大学院を修了するか予備試験に合格すれば、何歳でも司法試験を受験できます。
実際に、10代後半から70代まで、幅広い年齢層の受験生が司法試験に挑戦しています。最年少合格者は18-19歳、最高齢合格者は60-70代という記録があり、年齢に関係なく実力次第で合格できることを示しています。
ただし、受験資格取得から5年間で5回までという回数制限は適用されます。年齢に関わらず、この期間内に合格する必要があるため、計画的な学習が重要です。社会人として働きながら挑戦する場合、司法試験の勉強時間を参考に、効率的な学習計画を立てることをおすすめします。
Q. 司法試験は高卒でも受験できますか?
はい、司法試験は高卒でも受験できます。ただし、予備試験ルートを選択する必要があります。
予備試験には年齢、学歴、国籍、職業による制限が一切ないため、高卒の方でも受験できます。予備試験に合格すれば、法科大学院を経由せずに司法試験の受験資格を得られます。実際に、高校在学中や高卒後すぐに予備試験に合格している人もいます。
一方、法科大学院ルートを選ぶ場合は、法科大学院に入学するために大学卒業が必要です。高卒の方が法科大学院ルートで法曹を目指す場合、まず大学に進学して卒業する必要があります。
高卒から法曹を目指す場合、予備試験の難易度が極めて高いことを理解し、長期的な覚悟を持って挑戦することが重要です。予備校の講座を活用し、体系的に学習を進めることをおすすめします。
Q. 司法試験の受験資格の有効期限は何年ですか?
司法試験の受験資格の有効期限は5年間です。法科大学院修了または予備試験合格から5年以内に、最大5回まで司法試験を受験できます。
具体的には、法科大学院を2024年3月に修了した場合、2029年までに実施される司法試験のうち5回まで受験できます。予備試験に2024年に合格した場合も同様に、2029年までに5回の受験機会があります。
この5年間で合格できなかった場合、受験資格は失効します。その後再び司法試験を受験するには、法科大学院を再度修了するか、予備試験に再度合格する必要があります。
有効期限があるからこそ、計画的に受験することが重要です。1回目で不合格だった場合、次回に向けて効果的な対策を講じる必要があります。司法試験の勉強法では、計画的な学習方法を解説しています。
Q. 司法試験は何回まで受験できますか?
司法試験は、受験資格取得から5年間で最大5回まで受験できます。この制限は、法科大学院修了者と予備試験合格者の両方に適用されます。
5回という制限には、在学中受験も含まれます。例えば、法科大学院の最終学年で在学中受験制度を利用して受験した場合、その回数も5回のうちの1回としてカウントされます。
5回の受験機会をすべて使い切っても合格できなかった場合、受験資格は失効します。その後も法曹を目指したい場合は、法科大学院を再度修了するか、予備試験に再度合格する必要があります。
受験回数制限については、撤廃を求める議論もあります。詳しくは司法試験の回数制限で解説していますので、制度の背景や今後の動向に興味がある方は参考にしてください。
Q. 司法試験の予備試験と法科大学院、どちらがおすすめですか?
予備試験と法科大学院、どちらがおすすめかは、あなたの状況、目標、学習スタイルによって異なります。
予備試験ルートがおすすめの人は、費用を抑えたい人、早期に法曹を目指したい人、働きながら法曹を目指す社会人、学歴に関係なく挑戦したい人です。予備試験は費用が安く、合格後の司法試験合格率も高いですが、予備試験自体の合格率が約4%と極めて低い点に注意が必要です。
法科大学院ルートがおすすめの人は、体系的な法律教育を受けたい人、確実に受験資格を得たい人、法律初学者、法曹ネットワークを構築したい人です。法科大学院では少人数制の授業や実務教育を受けられ、着実に実力をつけられます。学費はかかりますが、奨学金制度も充実しています。
ハイブリッド戦略として、法科大学院進学を視野に入れつつ、大学在学中に予備試験にも挑戦する方法もあります。予備試験に合格できれば理想的ですが、合格できなくても法科大学院進学という選択肢が残ります。
自分の状況を客観的に分析し、時間、費用、学習スタイルの観点から最適なルートを選びましょう。司法試験予備校の選び方も参考にすることで、より具体的な学習計画を立てられます。
Q. 司法試験の受験資格を失効したらどうなりますか?
司法試験の受験資格を失効した場合、その時点で司法試験を受験する権利を失います。5年間で5回の受験機会をすべて使い切っても合格できなかった場合に、受験資格は失効します。
受験資格が失効した後も法曹を目指したい場合は、再度受験資格を取得する必要があります。方法は2つあります。1つ目は、法科大学院を再度受験して入学し、修了する方法です。既修者コースであれば2年間で修了できますが、再度学費が必要になります。2つ目は、予備試験に再度合格する方法です。予備試験に合格すれば、再び受験資格を得られます。
受験資格失効のリスクがあるため、限られた受験機会を最大限に活かすことが重要です。1回1回の受験を真剣に取り組み、不合格だった場合は原因を分析して次回に活かすことが大切です。
また、5回目の受験で不合格となる前に、法曹以外のキャリアパスも検討しておくことをおすすめします。法律知識を活かせる職業は弁護士以外にも多くあり、企業の法務部門や司法書士などの選択肢もあります。冷静に自分の実力と状況を見極め、最善の選択をすることが重要です。
-
 スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら
スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら -
 司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら
司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら -
 合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
まとめ:司法試験の受験資格取得ルートを理解して合格を目指そう
本記事では、司法試験の受験資格について詳しく解説しました。重要なポイントを改めて確認しましょう。
- 受験資格取得ルートは2つ:司法試験を受験するには、法科大学院修了か予備試験合格のいずれかが必要です。法科大学院ルートは体系的な教育を受けられ、確実に受験資格を得られます。予備試験ルートは費用を抑えられ、学歴に関係なく挑戦できますが、合格率が約4%と極めて低いことが課題です。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合ったルートを選択することが重要です。
- 有効期限と回数制限を理解する:受験資格取得後、5年間で最大5回まで司法試験を受験できます。この期間を超えると受験資格が失効し、再度法科大学院修了か予備試験合格が必要になります。限られた受験機会を最大限に活かすため、計画的な学習と効果的な試験対策が不可欠です。
- 年齢・学歴制限はない:司法試験の受験資格に年齢制限はなく、予備試験ルートを選べば学歴も不問です。中卒・高卒の方でも予備試験に合格すれば司法試験を受験でき、実際に若い年齢で合格している人もいます。一方、法科大学院ルートは大学卒業が必要ですが、在学中受験制度や法曹コースにより最短5年での合格を目指せます。
司法試験の受験資格を理解できたら、次は具体的な学習計画を立てましょう。司法試験の勉強時間と司法試験の勉強法を参考に、効率的な学習スケジュールを組むことをおすすめします。また、独学か予備校かで迷っている方は、司法試験予備校の選び方も参考にしてください。
本記事を通じて、司法試験の受験資格とそれぞれのルートの特徴を理解いただけたはずです。自分の状況と目標を明確にし、最適なルートを選択して、司法試験合格に向けて一歩を踏み出しましょう。
-
 スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら
スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら -
 司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら
司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら -
 合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
司法試験の関連記事

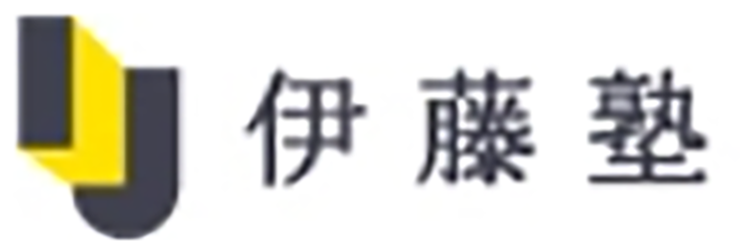


コメント