司法試験の受験を検討しているあなたへ。「何回まで受験できるのか」「5回落ちたらどうなるのか」という疑問は、司法試験の回数制限を正しく理解することで解決できます。
本記事では、司法試験の5年間で5回までという回数制限の仕組み、計算方法、歴史的な変遷、そして回数制限が設けられた理由について、最新のデータを交えて詳しく解説します。この情報をもとに、司法試験合格に向けて、効率的な学習計画を立てましょう。
- 司法試験の回数制限の仕組みと計算方法
- 回数制限の歴史的変遷と撤廃議論の現状
- 5回落ちた場合の具体的な対処法
- 受験回数別の合格率と一発合格を目指すべき理由
- 司法試験は5年間で5回まで受験可能:2015年から緩和された現行制度では、受験資格を得た年から5年以内に最大5回まで受験できます。予備試験には回数制限がないため、5回の受験機会を使い切った後も、予備試験合格により再チャレンジが可能です。
- 1回目の受験が最も合格率が高い:司法試験合格者の約70%が1回目の受験で合格しており、受験回数を重ねるほど合格率は低下する傾向にあります。早期合格こそが、法曹への最短ルートとなります。
- 回数制限撤廃の議論が続いている:日本弁護士連合会を中心に回数制限撤廃を求める声がありますが、司法浪人問題や法科大学院教育の効果を考慮し、現在も5年間で5回の制限が維持されています。
-
 スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら
スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら -
 司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら
司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら -
 合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
司法試験の回数制限とは
司法試験の回数制限は、受験資格を得てから何回まで試験を受けられるかを定めた制度です。この制度を正しく理解することは、計画的な受験戦略を立てる上で欠かせません。ここでは、現行の回数制限の内容と起算点について詳しく解説します。
司法試験は5年間で5回まで受験可能
現在の司法試験は、受験資格を得た年から5年以内に最大5回まで受験できる制度となっています。これは2015年に緩和された制度で、それ以前は「5年間で3回まで」という、いわゆる「三振制度」が適用されていました。
具体的には、法科大学院を修了した年、または予備試験に合格した年を起算点として、その年から5年間のうちに5回まで受験することができます。例えば、2024年に法科大学院を修了した場合、2024年から2028年までの5年間に、最大5回の受験機会があることになります。
この5回という回数は、短答式試験と論文式試験を両方受験した場合に1回とカウントされます。短答式試験のみを受験して論文式試験を欠席した場合でも、1回の受験としてカウントされるため注意しましょう。また、受験申込をした後に受験を取りやめた場合でも、受験回数にはカウントされません。
予備試験には回数制限がない
司法試験本試験には5年間で5回という回数制限がありますが、司法試験の受験資格を得るための予備試験には回数制限が設けられていません。つまり、予備試験は何度でも受験することが可能です。
この仕組みにより、司法試験で5回の受験機会を使い切ってしまった場合でも、予備試験に合格すれば新たな受験資格を得ることができます。予備試験に合格すると、その合格年から新たに5年間で5回の受験機会が与えられるため、実質的に再チャレンジが可能な制度設計となっています。
ただし、予備試験は司法試験本試験よりも合格率が低く、2023年度の合格率は約4.0%と非常に狭き門です。司法試験本試験の合格率が約45%であることと比較すると、予備試験ルートでの再チャレンジは容易ではないことが分かります。
司法試験の回数制限の起算点
司法試験の回数制限における起算点は、受験資格を得た年によって異なります。これを正しく理解することで、自分がいつまでに何回受験できるかを正確に把握できます。
法科大学院ルートの場合、法科大学院を修了した年が起算点となります。例えば、2024年3月に法科大学院を修了した場合、2024年から2028年までの5年間が受験期間となります。なお、在学中受験資格を利用して修了前に受験した場合も、修了見込みの年が起算点となります。
予備試験ルートの場合、予備試験に合格した年が起算点です。予備試験に合格すると翌年から司法試験本試験を受験できますが、5年間の起算は合格した年から始まります。例えば、2023年に予備試験に合格した場合、2023年から2027年までの5年間が受験期間となり、2024年から2028年まで最大5回受験できることになります。
受験資格を複数持っている場合は、それぞれの受験資格ごとに起算点が設定されます。ただし、後述するように、受験資格を切り替えた場合の取り扱いには特別なルールがあるため注意しましょう。
司法試験とはの基本的な制度について、さらに詳しく知りたい方は専門記事をご覧ください。
司法試験の回数制限の計算方法
司法試験の回数制限を正しく計算することは、受験計画を立てる上で非常に大切です。ここでは、予備試験ルート、法科大学院ルート、在学中受験資格の場合の具体的な計算例を示し、受験資格を切り替えた場合のルールについても解説します。
予備試験ルートの場合の計算例
予備試験ルートで司法試験を受験する場合、予備試験に合格した年が起算点となります。具体的な計算例を見てみましょう。
2023年に予備試験に合格したAさんの場合、2023年から2027年までの5年間が受験期間となります。この期間内に最大5回まで司法試験を受験できます。実際の受験スケジュールとしては、2024年(1回目)、2025年(2回目)、2026年(3回目)、2027年(4回目)、2028年(5回目)という形になります。
予備試験合格者の多くは翌年に初めて司法試験を受験するため、合格した年には受験回数を消費しないのが一般的です。ただし、制度上は合格した年から受験期間が始まるため、例えば2023年の予備試験に合格し、2023年の司法試験に間に合う場合は、その年から受験することも可能です(実際には日程的に困難ですが)。
予備試験ルートの特徴として、仮に5回の受験機会を使い切った場合でも、再度予備試験に合格すれば新たに5回の受験資格が得られる点が挙げられます。予備試験には回数制限がないため、理論上は何度でも再チャレンジが可能です。
法科大学院ルートの場合の計算例
法科大学院ルートで司法試験を受験する場合、法科大学院を修了した年が起算点となります。具体例で確認しましょう。
2024年3月に法科大学院を修了したBさんの場合、2024年から2028年までの5年間が受験期間です。この期間内に最大5回受験できるため、2024年(1回目)、2025年(2回目)、2026年(3回目)、2027年(4回目)、2028年(5回目)という受験スケジュールになります。
法科大学院修了者の多くは、修了した年の5月に行われる司法試験を受験します。そのため、修了年に1回目の受験を行うのが通常のパターンです。修了後すぐに受験できるよう、在学中から計画的に学習を進めることが求められます。
法科大学院には標準修業年限3年の未修者コースと、2年の既修者コースがあります。どちらのコースを選択しても、修了した年が起算点となる点は同じです。また、法科大学院を修了した年に司法試験を受験しなかった場合でも、受験期間は修了年から開始されるため、早めに受験を開始することが推奨されます。
在学中受験資格の場合の計算方法
2023年から導入された在学中受験資格制度では、法科大学院の最終学年に在学している学生が、修了見込みの状態で司法試験を受験できるようになりました。この場合の計算方法について説明します。
在学中受験資格を利用して受験した場合でも、起算点は修了見込みの年(実際に修了する年)となります。例えば、2024年3月に修了見込みで2024年の司法試験を受験したCさんの場合、2024年から2028年までの5年間が受験期間です。
在学中受験資格を利用して受験した場合、その受験は修了年の受験回数としてカウントされます。つまり、2024年3月修了見込みで2024年の試験を受験した場合、2024年の受験が1回目となります。その後、2024年3月に無事修了できれば、残り4回の受験機会が2025年から2028年まで続きます。
注意すべきは、修了見込みで受験したものの、実際には修了要件を満たせず修了できなかった場合です。この場合、在学中受験資格での受験は無効となり、受験回数にカウントされません。ただし、翌年以降に改めて修了し、新たな受験資格を得ることになるため、計画的な単位取得が求められます。
他の受験資格への切り替えの制限
司法試験では、法科大学院修了による受験資格と予備試験合格による受験資格の両方を持つことが可能です。しかし、受験資格を切り替える際には注意すべき制限があります。
最も重要なルールは、一度ある受験資格で司法試験を受験した後に、別の受験資格に切り替えることはできないという点です。例えば、法科大学院修了の受験資格で1回目の試験を受験した後、予備試験に合格したとしても、法科大学院修了資格での残りの受験回数を使い切るまでは予備試験合格の受験資格に切り替えることができません。
ただし、法科大学院修了の受験資格で5回の受験機会を全て使い切った後に予備試験に合格した場合は、新たな受験資格として予備試験合格による受験資格を使用できます。この場合、予備試験合格年から新たに5年間で5回の受験機会が与えられます。
複数の受験資格を持つ場合は、どの受験資格を使用するかを慎重に検討しましょう。一般的には、より有利な条件(例えば、起算点が新しい)の受験資格を選択することが推奨されます。受験申込時に使用する受験資格を選択することになるため、初回受験前に十分な計画を立てましょう。
司法試験の回数制限の歴史と変遷
司法試験の回数制限は、法曹養成制度の改革とともに変化してきました。現在の5年間で5回という制限に至るまでの歴史を知ることで、この制度の背景と意義をより深く理解できます。
旧司法試験には回数制限がなかった
2006年まで実施されていた旧司法試験には、受験回数の制限が一切ありませんでした。受験生は何度でも司法試験にチャレンジすることができ、10回以上、場合によっては20回以上受験する人も珍しくありませんでした。
この無制限の受験制度は、一見すると受験生に優しい制度のように思えますが、実際には深刻な「司法浪人問題」を生み出していました。多くの受験生が何年も、時には10年以上も司法試験の勉強に専念し、合格できないまま年齢を重ねるケースが続出しました。このような受験生は社会経験を積む機会を失い、仮に合格できなかった場合の進路変更が極めて困難になるという問題がありました。
また、旧司法試験では合格率が約3%と非常に低く、合格までの平均受験回数は4~5回程度でした。合格者の中には7回目、8回目での合格という人も珍しくなく、法曹になるまでの期間が長期化していました。この状況は、法曹志望者の減少や優秀な人材の他分野への流出を招く一因となっていました。
旧司法試験の受験回数無制限という制度は、受験生に複数回のチャンスを与えるという点では利点がありましたが、一方で受験生の人生設計や社会全体の人材活用という観点からは課題が多い制度でした。
2006年~2014年:5年間で3回まで(三振制度)
2006年に新司法試験(現在の司法試験)が導入されたとき、初めて受験回数の制限が設けられました。これが「5年間で3回まで」という、いわゆる「三振制度」です。野球用語から「三振」と呼ばれるようになり、3回受験して合格できなかった状態を「三振」と表現するようになりました。
この制度では、法科大学院を修了した年、または予備試験に合格した年から5年以内に3回まで受験できるとされました。例えば、2010年に法科大学院を修了した場合、2010年から2014年までの5年間に3回まで受験できることになります。
三振制度の導入により、受験生は限られた回数で合格を目指さなければならなくなりました。これは司法浪人の長期化を防ぐという目的では一定の効果がありましたが、一方で新たな問題も生じました。「受け控え」と呼ばれる現象です。
受け控えとは、受験生が「準備不足で不合格になるくらいなら、今年は受験を見送り、来年に備えよう」と考えて受験を先延ばしにする行動のことです。3回という少ない受験機会を有効に使おうとする受験生心理から生まれた現象で、結果的に法科大学院修了後すぐに受験しない人が増加しました。また、3回で合格できなかった場合の救済措置が限られていたため、「三振」した受験生の進路問題も深刻化しました。
2015年~現在:5年間で5回までに緩和
2015年に司法試験法が改正され、受験回数の制限が「5年間で3回まで」から「5年間で5回まで」に緩和されました。この改正により、受験生により多くのチャンス が与えられることになり、三振制度の問題点の一部が解消されました。
5回への緩和により、受験生は5年間のうちに最大5回まで受験できるようになりました。これは実質的に、5年間連続で毎年受験できることを意味します。例えば、2024年に法科大学院を修了した場合、2024年から2028年まで毎年受験することが可能です。
この緩和措置により、「受け控え」の問題はある程度改善されました。受験機会が3回から5回に増えたことで、受験生は修了直後から積極的に受験する傾向が強まりました。実際、2015年以降の受験率(修了者・合格者のうち実際に受験した人の割合)は改善しています。
現在の5年間で5回という制度は、受験生に十分なチャンスを与えつつ、司法浪人の長期化を防ぐというバランスを取った制度として機能しています。ただし、5回の受験機会を使い切った場合の救済措置については、引き続き議論が続いています。
回数制限が変更された理由
司法試験の回数制限が2015年に3回から5回に緩和された背景には、いくつかの大きな理由があります。これらの理由を理解することで、現在の制度の意義がより明確になります。
最大の理由は、三振制度による「受け控え」問題の深刻化でした。3回という制限があまりに厳しかったため、多くの受験生が慎重になりすぎて受験を先延ばしにし、結果的に受験率が低下していました。法科大学院修了後すぐに受験しない人が増えることは、法科大学院教育の効果が薄れるという問題にもつながっていました。
また、3回で不合格となった「三振者」の進路問題も深刻でした。法科大学院で多額の学費と時間を投資したにもかかわらず、3回の受験で合格できずに法曹の道を諦めざるを得ない人が増加し、社会問題化していました。5回への緩和により、より多くの人に合格のチャンスを与えることができるようになりました。
さらに、法科大学院の志願者減少も大きな要因でした。厳しい回数制限は、法科大学院を目指す人々にとって大きなリスクと受け止められ、法科大学院全体の志願者数が減少していました。制度を緩和することで、法曹を目指す人材を確保し、法科大学院制度を維持する必要がありました。
加えて、諸外国の司法試験制度との比較も考慮されました。多くの国では日本よりも柔軟な受験制度を採用しており、日本の制度が国際的に見て厳しすぎるという指摘がありました。5回への緩和により、国際的な標準により近づいたと言えます。
-
 スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら
スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら -
 司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら
司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら -
 合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
司法試験に回数制限が設けられた理由
司法試験に回数制限が導入された背景には、旧司法試験時代の様々な問題を解決する目的がありました。ここでは、回数制限が設けられた主な4つの理由について詳しく解説します。
司法浪人問題への対応
回数制限が設けられた最も重要な理由の一つが、深刻化していた「司法浪人問題」への対応です。旧司法試験では受験回数に制限がなかったため、何年も、時には10年以上も司法試験の勉強だけに専念する受験生が多数存在していました。
司法浪人の長期化は、受験生個人にとって深刻な問題を引き起こしていました。20代の貴重な時期をすべて受験勉強に費やし、社会経験や職業経験を積む機会を失ってしまうケースが多くありました。また、長期間の受験生活により経済的な負担も大きく、家族への依存や借金を抱える人も少なくありませんでした。
さらに、長期間受験を続けた結果、最終的に合格できなかった場合の進路変更が極めて困難という問題がありました。30代、40代になってから一般企業への就職を目指しても、社会経験がないため採用されにくく、人生の選択肢が大きく制限されてしまいます。
回数制限を設けることで、受験生に早期の進路決定を促し、不合格の場合でも早い段階で方向転換できるようにすることが目指されました。5年間で5回という制限は、十分なチャレンジの機会を与えつつ、受験生活の長期化を防ぐバランスを取った設定となっています。
早期の進路変更を促すため
回数制限のもう一つの大きな目的は、法曹に向いていない、あるいは合格が困難と判断される受験生に対して、早期に別の進路を選択する機会を提供することでした。これは受験生の人生設計という観点から非常に大切な考え方です。
司法試験は難関資格であり、誰もが合格できるわけではありません。適性や努力の方向性によっては、どれだけ時間をかけても合格が難しいケースもあります。回数制限がない場合、受験生は「もう少し頑張れば合格できるかもしれない」という期待から、延々と受験を続けてしまう恐れがあります。
20代、30代という人生の大切な時期を無限に受験勉強に費やすことは、キャリア形成の観点から必ずしも賢明な選択とは言えません。5年間で5回という明確な期限を設けることで、受験生は「この期限内に合格できなければ別の道を選ぶ」という明確な判断基準を持つことができます。
実際、司法試験に合格できなかった場合でも、法科大学院で学んだ法律知識は企業法務、行政、コンサルティングなど様々な分野で活かすことができます。早期に進路変更を行えば、これらの分野でキャリアを積む時間が十分にあります。回数制限は、受験生が柔軟に進路選択できるようにするための制度的な後押しとなっています。
また、法曹以外の道を選択した法科大学院修了者が社会で活躍することは、法的思考力を持つ人材が社会の様々な場面で必要とされている現代において、大きな意義があります。回数制限は、このような多様なキャリアパスを促進する側面も持っています。
法科大学院教育の効果を高めるため
回数制限は、法科大学院教育の効果を最大化するという目的も持っています。法科大学院制度は、理論と実務を架橋した法曹養成教育を提供することを目的として2004年に導入されました。
法科大学院での教育効果は、修了直後が最も高いと考えられています。在学中に学んだ知識や思考方法、実務科目で培ったスキルは、修了後すぐに司法試験で活用することで最大の効果を発揮します。しかし、修了後に長期間経過すると、これらの教育効果が薄れていく可能性があります。
回数制限を設けることで、受験生は修了後できるだけ早く受験しようという動機づけが生まれます。以前の「受け控え」問題のように、準備不足を理由に何年も受験を先延ばしにすることが難しくなり、法科大学院教育の成果を新鮮なうちに試験で発揮することが促されます。
また、法科大学院側にとっても、回数制限は教育内容の改善につながります。修了生が5年以内、5回以内に合格することを前提とした教育プログラムを設計することで、より実践的で効果的なカリキュラムの開発が進められています。多くの法科大学院では、修了後も継続的な学習支援を提供し、限られた受験機会の中で合格できるようサポート体制を整えています。
さらに、回数制限により法科大学院の教育成果が明確に測定できるようになりました。修了後5年以内の累積合格率という指標が、各法科大学院の教育の質を評価する重要な基準となっており、これが法科大学院間の競争を促し、全体的な教育水準の向上につながっています。
「受け控え」の防止
「受け控え」とは、受験生が準備不足を理由に受験を先延ばしにする現象のことです。回数制限の導入、特に2015年の5回への緩和は、この受け控え問題の解消を重要な目的の一つとしていました。
三振制度(5年間で3回まで)の時代には、受け控えが深刻な問題となっていました。受験生は「3回しかチャンスがないのだから、確実に合格できる準備が整うまで受験すべきではない」と考え、法科大学院修了後1年目、2年目の受験を見送るケースが多発しました。しかし、この判断が必ずしも良い結果につながらないことが、データから明らかになっています。
実際の司法試験の合格率のデータを見ると、1回目の受験が最も合格率が高く、受験回数を重ねるごとに合格率は低下する傾向にあります。修了後すぐに受験せず、1年間準備を重ねても、その間にモチベーションの低下や生活環境の変化などにより、必ずしも成績が向上するとは限りません。
5回への緩和により、受験生の心理的プレッシャーが軽減され、修了直後から積極的に受験する傾向が強まりました。「5回もチャンスがあるのだから、まずは1回受けてみて、自分の実力や試験の雰囲気を確認しよう」という前向きな姿勢が生まれやすくなったのです。
法務省の統計によると、2015年以降、法科大学院修了後すぐに受験する人の割合が増加しています。これは回数制限の緩和が受け控え防止に一定の効果を上げていることを示しています。早期に受験することで、法科大学院で学んだ知識が新鮮なうちに試験に臨むことができ、結果的に合格率の向上にもつながっています。
司法試験で5回落ちた場合の対処法
5年間で5回の受験機会を全て使い切った場合、いわゆる「五振(ごしん)」となります。しかし、これで法曹への道が完全に閉ざされるわけではありません。ここでは、5回不合格となった場合の具体的な対処法について解説します。
五振(ごしん)とは
「五振(ごしん)」とは、5年間で5回の受験機会を全て使い切り、不合格となった状態を指す言葉です。野球用語の「三振」に由来する「三振」という言葉が、5回への緩和後は「五振」と呼ばれるようになりました。
五振になると、現在保有している受験資格では司法試験を受験できなくなります。例えば、2024年に法科大学院を修了し、2024年から2028年までの5回すべて不合格だった場合、その法科大学院修了による受験資格では、2029年以降は受験できません。
しかし、五振となっても法曹を目指す道が完全に閉ざされるわけではありません。新たな受験資格を取得すれば、再び司法試験にチャレンジすることが可能です。具体的には、再度法科大学院を修了するか、予備試験に合格することで、新しい受験資格を得ることができます。
五振者の数は年々増加しています。5回への緩和により、以前の三振制度よりも多くの人が最後まで受験を続けられるようになりましたが、それでも合格できない人は一定数存在します。法務省の統計によると、毎年数百人規模で五振となる受験生が発生しており、その後の進路選択が重要な課題となっています。
再度法科大学院を修了する
五振後に再び法曹を目指す方法の一つは、法科大学院に再入学し、修了することです。法科大学院を修了すれば、新たな受験資格を取得でき、その修了年から再び5年間で5回の受験機会が与えられます。
法科大学院への再入学には、既修者コースと未修者コースの2つの選択肢があります。既修者コースは2年制で、既に法律知識を持っている人を対象としています。五振者は既に法科大学院を修了しているため、既修者コースへの入学が一般的です。一方、未修者コースは3年制で、法律を基礎から学び直したい場合に選択できます。
再入学する法科大学院の選択も重要です。前回と同じ法科大学院を選ぶこともできますが、異なる教育方針やカリキュラムを持つ法科大学院を選択することで、新たな視点や学習方法を得られる可能性があります。各法科大学院の合格実績や教育内容、学費、奨学金制度などを総合的に検討しましょう。
ただし、法科大学院への再入学には時間と費用がかかります。既修者コースでも2年間、未修者コースでは3年間が必要で、学費も数百万円規模になります。また、その後の5回の受験期間を含めると、最初の挑戦から10年以上が経過する可能性もあります。経済的な負担や年齢、キャリアへの影響を慎重に考慮する必要があります。
予備試験に合格する
五振後のもう一つの選択肢は、予備試験に合格することです。予備試験には受験回数の制限がないため、何度でもチャレンジすることができます。予備試験に合格すれば、法科大学院修了と同等の受験資格が得られ、合格年から新たに5年間で5回の受験機会が与えられます。
予備試験ルートの最大の利点は、法科大学院への再入学と比べて時間と費用を節約できる点です。法科大学院への再入学には2~3年の時間と数百万円の学費が必要ですが、予備試験は独学でも挑戦でき、学費がかかりません。予備校を利用する場合でも、法科大学院の学費よりは安価に済むことが多いです。
しかし、予備試験は司法試験本試験よりもはるかに難関です。2023年度の予備試験合格率は約4.0%で、司法試験本試験の合格率45.3%と比較すると、その難易度の高さが分かります。司法試験で5回不合格だった人が、さらに難関の予備試験に合格することは容易ではありません。
予備試験に挑戦する場合は、司法試験の勉強時間を参考に、効率的な学習計画を立てることが不可欠です。予備試験は短答式試験、論文式試験、口述試験の3段階で構成されており、幅広い法律知識と論述力が求められます。司法試験で不合格となった原因を分析し、学習方法を根本的に見直すことが成功への鍵となります。
また、予備試験に挑戦する期間は、経済的な基盤を確保することも大切です。働きながら予備試験の勉強をする、あるいはアルバイトをしながら勉強時間を確保するなど、長期戦に耐えられる生活設計が必要です。
法曹以外のキャリアを選択する
五振となった場合、法曹以外のキャリアを選択することも重要な選択肢の一つです。法科大学院で学んだ法律知識や論理的思考力は、法曹以外の多くの分野でも高く評価されます。
企業法務は、法科大学院修了者にとって有力なキャリアパスです。企業の法務部門では、契約書のレビュー、コンプライアンス対応、訴訟管理など、法律知識を活かせる業務が多数あります。特に大企業や外資系企業では、法科大学院修了者を積極的に採用しているケースがあります。
司法書士や行政書士などの関連資格を取得する道もあります。これらの資格は司法試験ほど難関ではなく、法科大学院で学んだ知識を活かして比較的短期間で合格を目指せます。司法書士は不動産登記や商業登記、行政書士は許認可申請や契約書作成など、法律関連の専門職として活躍できます。
公務員として法律知識を活かす道もあります。国家公務員や地方公務員の中には、法律関連の業務を扱う部署が多数あります。法制執務、行政法務、議会対応など、法科大学院での学びを直接活かせる職務があります。
コンサルティングファームや金融機関、不動産業界なども、法律知識を持つ人材を必要としています。企業のM&Aアドバイザリー、コンプライアンスコンサルタント、不動産投資のリーガルチェックなど、法律の専門知識が求められる職種は多岐にわたります。
法曹以外のキャリアを選択する場合、できるだけ早期に決断し、行動を開始することが肝心です。30代前半までであれば、未経験の分野への転職も比較的容易ですが、年齢を重ねるほどキャリアチェンジは困難になります。五振となったことを前向きに捉え、法律知識を活かせる新たなキャリアを積極的に探しましょう。
司法試験の受験回数別の合格者データ
司法試験の合格率や合格者数は受験回数によって大きく異なります。ここでは、受験回数別のデータを詳しく分析し、早期合格の重要性について解説します。
1回目の受験が最も合格率が高い
司法試験の合格率は、1回目の受験が最も高く、受験回数を重ねるごとに低下する傾向が明確に見られます。これは統計的に一貫して確認されている事実であり、受験戦略を考える上で非常に重要なポイントです。
2023年度のデータを見ると、1回目の受験者の合格率は約55~60%程度と推定されています(法務省公表データより)。これは全体の合格率45.3%を大きく上回る数字です。一方、2回目の受験者の合格率は約35~40%、3回目は約25~30%と、受験回数が増えるごとに合格率は段階的に低下していきます。
この傾向の理由は複数あります。第一に、1回目の受験者は法科大学院を修了したばかりで、学習内容が最も新鮮な状態にあります。在学中に学んだ知識や演習の経験が色あせる前に試験に臨めるため、高い合格率につながっています。
第二に、1回目の受験者には優秀な受験生が多く含まれています。法科大学院での成績が良好で、十分な準備ができている人ほど、修了直後から積極的に受験する傾向があります。一方、複数回受験している人の中には、基礎力が不足している、あるいは学習方法に問題がある人も含まれている可能性があります。
第三に、受験回数を重ねるごとにモチベーションの維持が難しくなります。1回目の受験では高いモチベーションを持って臨めますが、不合格が続くと精神的な負担が大きくなり、学習効率が低下する傾向があります。
このデータから導き出される教訓は明確です。法科大学院修了後、できるだけ早く、特に1回目の受験で合格することを目指すべきです。「もう少し準備してから」と受験を先延ばしにするよりも、修了直後の知識が新鮮な状態で挑戦する方が、合格の可能性が高いのです。
司法試験合格者の平均受験回数
司法試験合格者の平均受験回数は、近年約1.5~1.8回程度で推移しています。これは、合格者の大多数が1回目または2回目の受験で合格していることを意味します。
詳しく見ると、合格者の約70%が1回目の受験で合格しており、約20%が2回目、残りの約10%が3回目以降の受験で合格しています。つまり、合格者の約90%が2回以内に合格しているという計算になります。
予備試験ルートと法科大学院ルートで平均受験回数に若干の違いがあります。予備試験合格者の多くは1回目の受験で司法試験に合格する傾向が強く、平均受験回数は1.3~1.5回程度とされています。一方、法科大学院修了者の平均受験回数は1.6~1.9回程度とやや高めです。
この差は、予備試験合格者の学力水準が高いことを反映しています。予備試験自体が非常に難関であり、予備試験に合格できるレベルの実力があれば、司法試験本試験も比較的スムーズに合格できる傾向にあります。
平均受験回数のデータからも、早期合格の重要性が確認できます。3回目、4回目、5回目の受験で合格する人は全体の少数派であり、受験回数を重ねるほど合格が困難になることが統計的に示されています。
受験生にとって大切なのは、この統計データを自分の受験戦略に活かすことです。「平均1.5回で合格している」という事実は、「1回目で合格できなくても2回目には合格したい」という現実的な目標設定の根拠となります。逆に、3回目以降の受験となった場合は、学習方法の抜本的な見直しが必要というシグナルとも言えます。
受験回数別の合格者数と割合
司法試験の受験回数別の合格者数と割合を詳しく見ることで、各回における合格の難易度をより具体的に理解できます。2023年度のデータ(法務省発表)を基に分析してみましょう。
2023年度の司法試験では、合格者1,781名のうち、約1,250名(約70%)が1回目の受験で合格しています。これは圧倒的に大きな割合であり、初回受験での合格が最も現実的な合格パターンであることを示しています。
2回目の受験での合格者は約360名(約20%)でした。1回目で不合格となったものの、2回目の挑戦で合格を果たした人々です。2回目の受験者全体の合格率は約35~40%と推定され、1回目よりは低いものの、依然として合格の可能性は十分にあると言えます。
3回目の受験での合格者は約110名(約6%)、4回目は約40名(約2%)、5回目は約20名(約1%)という分布になっています。受験回数が増えるごとに合格者数が大幅に減少していることが分かります。
この数字を別の角度から見ると、3回目以降の受験で合格する人は全体の約10%に過ぎません。つまり、合格者の90%が2回以内に合格しているという事実です。これは、3回目以降の受験では合格の可能性が著しく低下することを意味しています。
受験回数別の合格者割合を表にまとめると、以下のようになります。
| 受験回数 | 合格者数(推定) | 合格者全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 1回目 | 約1,250名 | 約70% |
| 2回目 | 約360名 | 約20% |
| 3回目 | 約110名 | 約6% |
| 4回目 | 約40名 | 約2% |
| 5回目 | 約20名 | 約1% |
このデータから明確に言えるのは、できるだけ早い段階、特に1回目または2回目の受験で合格することが重要だということです。受験を重ねるほど合格が難しくなるため、初回から全力で臨む姿勢が求められます。
受験回数を重ねるほど合格が難しくなる理由
受験回数を重ねるごとに合格率が低下する現象には、いくつかの明確な理由があります。これらを理解することで、なぜ早期合格が重要なのかがより深く理解できます。
最大の理由は、知識の鮮度の低下です。法科大学院を修了直後は、在学中に学んだ知識や論述方法が最も新鮮な状態にあります。しかし、修了後1年、2年と時間が経過するにつれて、これらの知識は徐々に色あせていきます。特に、法律の世界は判例や法改正により常に変化しているため、最新の知識を維持することが重要です。
第二の理由は、モチベーションと精神的負担の問題です。1回目の受験では、法科大学院での苦労が報われるという強い動機づけがあり、高いモチベーションで試験に臨めます。しかし、不合格が続くと、「また不合格かもしれない」という不安や、周囲からのプレッシャーにより、精神的な負担が増大します。このストレスは学習効率を低下させ、試験本番でのパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。
第三に、生活環境の変化も大きな要因です。法科大学院在学中や修了直後は、勉強に専念できる環境にある人が多いですが、時間が経つにつれて経済的な理由からアルバイトや就職をせざるを得なくなったり、家庭の事情で勉強時間が削られたりするケースが増えます。専念できる時間が減少すれば、当然ながら合格の可能性も低下します。
第四の理由として、学習方法の固定化があります。1回目、2回目の受験で不合格となった場合、その学習方法や対策に問題がある可能性が高いにもかかわらず、同じアプローチを繰り返してしまう受験生が多くいます。学習方法を根本的に見直さない限り、受験回数を重ねても結果が改善しない可能性があります。
最後に、競争環境の変化も影響します。毎年、新たに法科大学院を修了する人や予備試験に合格する人が受験生として参入してきます。彼らは最新の教育を受け、最新の知識を持って試験に臨みます。複数回受験している人は、こうした新しい受験生との競争にも直面することになります。
これらの理由から、できるだけ早期に、特に1回目または2回目の受験で合格することが極めて重要です。3回目以降の受験となった場合は、単に勉強時間を増やすだけでなく、学習方法の抜本的な見直し、メンタルケア、生活環境の整備など、総合的なアプローチが必要となります。
司法試験の合格率に関する詳細なデータと分析については、専門記事をご覧ください。
司法試験の一発合格者の割合
司法試験において一発合格(1回目の受験で合格すること)は、多くの受験生が目指す理想的な結果です。ここでは、一発合格者の実態と、予備試験ルートと法科大学院ルートでの違いについて詳しく解説します。
一発合格者は全体の約70%
司法試験合格者のうち、一発合格者(1回目の受験で合格した人)が占める割合は約70%です。これは非常に高い割合であり、司法試験において一発合格が決して珍しいことではないことを示しています。
2023年度の司法試験では、合格者1,781名のうち約1,250名が1回目の受験で合格しました。これは合格者全体の約70%に相当します。この割合は近年ほぼ一定しており、毎年7割前後の合格者が一発合格を果たしていることが確認されています。
この高い一発合格率には、いくつかの要因があります。第一に、法科大学院教育の質が向上し、修了時点で司法試験に合格できる実力を身につけている学生が増えていることが挙げられます。多くの法科大学院では、司法試験を意識したカリキュラムや演習を提供しており、修了生が初回受験で合格できる水準に達しています。
第二に、予備試験合格者の多くが初回受験で司法試験に合格していることも、全体の一発合格率を押し上げています。予備試験は司法試験よりも難関であり、予備試験に合格できる実力があれば、司法試験本試験も一発で合格できる可能性が高いのです。
第三に、受験生の意識の変化も影響しています。5年間で5回という制限が設けられたことで、受験生は「できるだけ早く合格する」という意識を持つようになり、初回から全力で試験に臨む傾向が強まっています。
一発合格率70%という数字は、受験生にとって心強いデータです。適切な準備をすれば、初回受験で合格することは十分に実現可能な目標だということを示しています。逆に言えば、2回目以降の受験となる人は少数派であり、できる限り初回合格を目指すべきだという指標でもあります。
予備試験ルートと法科大学院ルートでの違い
一発合格率は、予備試験ルートと法科大学院ルートで大きく異なります。この違いを理解することで、各ルートの特性をより深く把握できます。
予備試験ルートの一発合格率は、約85~90%と非常に高い水準にあります。2023年度のデータでは、予備試験合格者のうち約85%が初回の司法試験で合格しています。予備試験合格者は、予備試験という高い壁を乗り越えた時点で、司法試験に合格できる十分な実力を備えていることが多いため、このような高い一発合格率となっています。
一方、法科大学院ルートの一発合格率は約60~65%とやや低めです。予備試験ルートと比較すると20~25ポイントほど低い数字ですが、それでも合格者の過半数以上が一発合格を果たしていることには変わりありません。
この違いの主な理由は、選抜の厳しさにあります。予備試験は合格率約4%という超難関試験であり、この試験に合格できる人は、既に司法試験に合格できるだけの高い学力を持っています。予備試験の試験範囲は司法試験とほぼ同じであり、予備試験に合格した時点で、司法試験の合格に必要な知識とスキルをほぼ習得していると言えます。
一方、法科大学院ルートでは、入学時点での学力差が大きく、また在学中の学習成果にも個人差があります。優秀な成績で修了した人は一発合格する可能性が高いですが、単位取得に苦労した人や、修了時点でまだ実力が不十分な人も含まれています。
ただし、これは法科大学院ルートが劣っているという意味ではありません。法科大学院では、理論と実務を架橋した総合的な法曹教育が提供されており、単に試験に合格するだけでなく、法曹として必要な幅広い知識と思考力を養成することを目的としています。一発合格率がやや低いとしても、2回目、3回目の受験で合格する人も多く、累積合格率で見れば十分に高い水準を保っています。
予備試験ルートと法科大学院ルート、どちらを選択するかは、個人の状況や目標によって異なります。予備試験ルートは時間と費用を節約できる一方、予備試験自体が非常に難関です。法科大学院ルートは体系的な教育を受けられる一方、時間と学費がかかります。それぞれのメリットとデメリットを理解した上で、自分に合ったルートを選択しましょう。
一発合格を目指すべき理由
司法試験において、一発合格を目指すべき理由は複数あります。統計データと実態の両面から、なぜ初回合格が重要なのかを確認しましょう。
第一の理由は、既に述べたように、1回目の受験が最も合格率が高いという統計的事実です。受験回数を重ねるごとに合格率は低下するため、最も合格しやすい初回の機会を最大限に活かすべきです。法科大学院で学んだ知識が最も新鮮な状態で試験に臨めるのは、修了直後の初回受験だけです。
第二に、キャリア形成の観点からも一発合格は有利です。司法試験合格後は司法修習を経て法曹としてのキャリアがスタートしますが、早期に合格すればそれだけ早く実務経験を積み始めることができます。20代のうちに法曹資格を取得できれば、30代、40代でのキャリアアップの可能性が広がります。
第三の理由は、経済的な負担の軽減です。2回目以降の受験となると、予備校の再受講や学習教材の更新など、追加の費用がかかります。また、受験勉強を続けるために収入を得る機会を失うという機会費用も発生します。一発合格すれば、これらのコストを回避できます。
第四に、精神的な負担も考慮すべき要因です。司法試験は年に1回しか実施されないため、不合格となると1年間待たなければなりません。この1年間は精神的に非常に厳しく、モチベーションの維持が困難になります。一発合格すれば、このような精神的負担を経験せずに済みます。
第五の理由として、法科大学院での学習成果を最大限に活かせる点があります。法科大学院のカリキュラムは、修了後すぐに司法試験を受験することを前提に設計されています。在学中に学んだ判例や理論、演習での経験は、修了直後が最も効果的に活用できます。
一発合格を目指すための具体的な戦略としては、法科大学院在学中から計画的に準備を進めることが求められます。単位を取得するだけでなく、司法試験の過去問演習や模試への参加を通じて、実戦的な力を養っておく必要があります。また、修了後は専念できる環境を整え、十分な司法試験の勉強時間を確保することも大切です。
一発合格は決して不可能な目標ではありません。合格者の70%が達成している現実的な目標であり、適切な準備と努力により十分に実現可能です。「1回目で合格する」という強い意志を持ち、そのための万全の準備を整えましょう。
司法試験の回数制限撤廃の議論
司法試験の回数制限については、その導入以来、撤廃すべきかどうかの議論が続いています。ここでは、弁護士会による撤廃要求の背景、賛成意見と反対意見、そして現在の議論の状況について詳しく解説します。
弁護士会による撤廃要求
日本弁護士連合会(日弁連)は、司法試験の回数制限撤廃を継続的に要求しています。この要求の背景には、回数制限が受験生の人権や機会均等の観点から問題があるという考えがあります。
日弁連の主張の核心は、法曹を目指す意欲と能力のある人に対して、回数制限という形で道を閉ざすべきではないという点にあります。回数制限により、5回の受験で合格できなかった人は、法科大学院への再入学や予備試験合格という高いハードルを越えない限り、法曹への道が実質的に閉ざされてしまいます。
特に問題視されているのは、経済的な格差が受験機会の格差につながる点です。法科大学院への再入学には数百万円の学費が必要であり、経済的に余裕のない受験生にとっては現実的な選択肢ではありません。予備試験は費用面では有利ですが、合格率が約4%と極めて低く、こちらも容易な道ではありません。
日弁連は、旧司法試験のように回数制限を撤廃し、意欲と能力のある人には何度でもチャレンジの機会を与えるべきだと主張しています。諸外国の多くでは、日本ほど厳格な回数制限を設けていない例も多く、国際的な比較からも日本の制度は厳しすぎるという指摘があります。
また、日弁連は法科大学院制度の問題点も指摘しています。法科大学院での教育の質に格差があり、一部の法科大学院では合格率が極端に低い状況が続いています。このような法科大学院を修了した学生に対して、5回という制限を課すことは公平性を欠くのではないかという問題提起もなされています。
回数制限撤廃への賛成意見
回数制限撤廃を支持する意見には、いくつかの重要な論点があります。これらの意見は、受験生の権利、教育機会の平等、多様な人材の確保という観点から展開されています。
賛成派の最も強い論拠は、受験機会の平等性です。法曹を目指す熱意と能力のある人に対して、回数という形式的な基準で道を閉ざすことは、憲法が保障する職業選択の自由を不当に制限する可能性があります。実際に合格する能力があるにもかかわらず、様々な事情(病気、家庭の事情、経済的困難など)により5回以内に合格できなかった人もいるはずです。
第二の論点は、人材の多様性確保にあります。回数制限により若い時期に合格できた人だけが法曹になれる制度では、法曹界の人材が画一化する恐れがあります。様々な人生経験を経て、30代、40代で法曹を目指す人にもチャンスを与えることで、より多様なバックグラウンドを持つ法曹が生まれ、社会のニーズに応えられる可能性があります。
第三に、教育投資の回収という観点からの意見もあります。法科大学院での教育には、学生本人だけでなく、国からの補助金という形で公的資金も投入されています。多額の投資をして法律教育を受けた人材が、回数制限により法曹になれないまま終わるのは、社会的な損失だという主張です。
第四の論点は、諸外国との比較です。アメリカの多くの州では司法試験の受験回数に制限がないか、あっても日本より緩やかな制限となっています。ヨーロッパ諸国でも、日本のような厳格な回数制限を設けている国は少数です。国際的な標準と比較して、日本の制度は過度に厳しいという指摘です。
また、回数制限撤廃により、受け控えの問題が完全に解消されるという指摘もあります。回数に制限がなければ、受験生は「今年は準備不足だから来年にしよう」と考える必要がなくなり、準備ができた時点で積極的に受験するようになると期待されます。
回数制限維持への反対意見
一方、回数制限の維持を支持する意見も根強く存在します。これらの意見は、主に司法浪人問題の再発防止、法科大学院教育の効果、受験生本人の利益という観点から展開されています。
反対派の最も重要な論拠は、旧司法試験時代の司法浪人問題の教訓です。回数制限がなかった旧司法試験では、10年以上も受験を続ける人が多数存在し、その間に社会経験を積む機会を失い、合格できなかった場合の進路変更が極めて困難になるという深刻な問題がありました。回数制限を撤廃すれば、同じ問題が再発する恐れがあります。
第二の論点は、受験生本人の利益保護です。回数制限は一見すると受験生に不利な制度に思えますが、実際には受験生を無限の受験競争から守る側面があります。明確な期限があることで、受験生は「この期間内に合格できなければ別の道を選ぶ」という判断基準を持つことができ、人生の早い段階で進路変更が可能になります。
第三に、法科大学院教育の効果を維持する観点からの意見があります。法科大学院での教育効果は修了後の年数とともに低下します。回数制限を撤廃すれば、修了後10年、20年経ってから受験する人も現れる可能性があり、その時点では法科大学院教育の成果がほとんど残っていない可能性があります。これは法科大学院制度の意義を損なうことになります。
第四の論点として、試験制度の公平性維持があります。回数制限を撤廃すれば、何度も受験している人と初めて受験する人が同じ試験を受けることになります。何度も受験している人は試験問題の傾向を熟知しており、テクニック面で有利になる可能性があります。これは試験の公平性を損なう恐れがあります。
また、現在の5年間で5回という制度は、以前の3回から緩和されたものであり、十分なチャンスを提供しているという指摘もあります。5回の受験機会があれば、ほとんどの合格可能な受験生は合格できるはずであり、これ以上の緩和は必要ないという主張です。
さらに、予備試験という救済ルートが存在することも、回数制限維持の論拠とされています。5回の受験で合格できなかった場合でも、予備試験に合格すれば新たな受験資格が得られるため、完全に道が閉ざされるわけではありません。本当に法曹を目指す意欲のある人には、このルートが用意されているという考え方です。
現在の議論の状況
司法試験の回数制限撤廃をめぐる議論は、現在も継続しています。しかし、近年の状況を見ると、撤廃の可能性は低いと考えられます。
法務省や文部科学省などの政府機関は、現行の5年間で5回という制度を維持する方針を示しています。2015年に3回から5回に緩和したばかりであり、この制度改正の効果を見極めるべきだというのが政府の立場です。実際、5回への緩和により受け控え問題はある程度改善されており、制度としては一定の成果を上げていると評価されています。
法科大学院協会などの教育機関側も、現行制度の維持を支持する傾向にあります。法科大学院での教育効果を最大限に発揮するためには、修了後できるだけ早期に受験することが望ましく、回数制限はそのインセンティブとして機能しているという認識です。
一方、日弁連は撤廃要求を続けていますが、具体的な制度改正の動きには至っていません。回数制限撤廃には、旧司法試験時代の問題の再発というリスクがあり、広範な支持を得るには至っていないのが現状です。
今後の議論の焦点は、回数制限の完全撤廃よりも、5回の受験機会を使い切った後の救済措置の充実に移る可能性があります。例えば、予備試験の合格率を若干引き上げる、法科大学院への再入学の経済的負担を軽減するための奨学金制度を拡充するなど、より現実的な改善策が検討される可能性があります。
また、法科大学院教育の質の向上も大きなテーマです。すべての法科大学院が高い合格率を維持できるよう、教育内容やカリキュラムの改善が進められています。根本的には、5回の受験機会の中で大多数の受験生が合格できるような教育体制を整えることが、最も重要な課題と言えるでしょう。
当面は現行の5年間で5回という制度が継続される見込みですが、将来的には社会情勢の変化や法曹養成制度全体の見直しの中で、再度議論される可能性もあります。受験生としては、現行制度を前提として、5回の機会を最大限に活かす戦略を立てることが現実的な対応と言えるでしょう。
司法試験の回数制限に関連するよくある質問(FAQ)
司法試験の回数制限について、受験生から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。これらのFAQを通じて、回数制限の詳細をより深く理解しましょう。
Q. 司法試験は何回まで受験できますか?
司法試験は、受験資格を得た年から5年以内に最大5回まで受験できます。これは2015年から適用されている現行制度で、それ以前は「5年間で3回まで」という制限でした。
具体的には、法科大学院を修了した年、または予備試験に合格した年を起算点として、その年を含む5年間のうちに5回まで受験することができます。例えば、2024年に法科大学院を修了した場合、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年の5年間に、最大5回受験できることになります。
短答式試験と論文式試験の両方を受験した場合に1回とカウントされます。短答式試験のみを受験して論文式試験を欠席した場合でも、1回の受験としてカウントされるため注意しましょう。ただし、受験申込後に受験を取りやめた場合は、受験回数にカウントされません。
予備試験には回数制限がないため、5回の受験機会を使い切った後でも、予備試験に合格すれば新たに5回の受験資格を得ることができます。また、再度法科大学院を修了することでも、新たな受験資格を得ることが可能です。
Q. 司法試験の回数制限の起算日はいつですか?
司法試験の回数制限における起算日は、受験資格を得た年の1月1日です。正確には「年」単位で計算されるため、具体的な月日ではなく、受験資格を得た「年」がポイントとなります。
法科大学院ルートの場合、法科大学院を修了した年が起算点となります。多くの法科大学院は3月に修了式を行いますが、起算点は修了した年の1月1日とみなされます。例えば、2024年3月に法科大学院を修了した場合、2024年から2028年までの5年間が受験期間となります。
予備試験ルートの場合、予備試験に合格した年が起算点です。予備試験の最終合格発表は通常11月頃に行われますが、合格した年の1月1日が起算点となります。例えば、2023年11月に予備試験に合格した場合、2023年から2027年までの5年間が受験期間です。
在学中受験資格を利用した場合も、修了見込みの年(実際に修了する年)が起算点となります。2024年3月修了見込みで2024年の司法試験を受験した場合、2024年から2028年までの5年間が受験期間です。
受験期間の終了は、起算点から5年目の12月31日までです。例えば、2024年が起算点の場合、2028年12月31日まで が受験期間となり、実際の受験は2028年5月の試験まで可能です。
Q. 司法試験で5回落ちたらどうなりますか?
司法試験で5回不合格となった場合、いわゆる「五振(ごしん)」の状態となり、現在保有している受験資格では司法試験を受験できなくなります。しかし、法曹への道が完全に閉ざされるわけではなく、いくつかの選択肢があります。
第一の選択肢は、再度法科大学院に入学して修了することです。法科大学院を修了すれば新たな受験資格を得られ、修了年から再び5年間で5回の受験機会が与えられます。既修者コース(2年制)または未修者コース(3年制)のいずれかを選択できます。
第二の選択肢は、予備試験に合格することです。予備試験には受験回数の制限がないため、何度でもチャレンジできます。予備試験に合格すれば、合格年から新たに5年間で5回の受験資格が得られます。ただし、予備試験の合格率は約4%と非常に低く、司法試験で5回不合格だった人が予備試験に合格することは容易ではありません。
第三の選択肢は、法曹以外のキャリアを選択することです。法科大学院で学んだ法律知識は、企業法務、司法書士、行政書士、公務員、コンサルティングなど、様々な分野で活かすことができます。早期に進路変更することで、これらの分野でキャリアを積む時間が確保できます。
五振となった場合、どの選択肢を選ぶかは、年齢、経済状況、法曹への熱意などを総合的に考慮して判断することになります。法科大学院への再入学や予備試験挑戦には時間と費用がかかるため、慎重な検討が求められます。30代以降であれば、法曹以外のキャリアを選択することも十分に合理的な選択肢となります。
Q. 司法試験の「三振」とは何ですか?
「三振」とは、2006年から2014年まで適用されていた「5年間で3回まで」という回数制限のもとで、3回の受験機会を使い切って不合格となった状態を指す言葉です。野球用語の「三振」(3ストライクでアウト)に由来しています。
旧制度では、法科大学院を修了した年または予備試験に合格した年から5年以内に3回まで受験できるという制限がありました。この3回の受験で合格できなかった人を「三振」または「三振者」と呼びました。三振制度は、受験回数が少なすぎることから「受け控え」などの問題を引き起こし、2015年に5回に緩和されました。
現在は5回に緩和されているため、厳密には「三振」という用語は過去の制度を指す言葉となっています。現行制度では5回の受験機会があるため、5回使い切った状態を「五振(ごしん)」と呼ぶこともありますが、「三振」ほど一般的な用語ではありません。
ただし、現在でも「三振」という言葉は、回数制限により受験機会を使い切ることを指す比喩的な表現として使われることがあります。「三振しないように頑張る」といった表現で、受験回数を使い切らずに合格することを目指すという意味で使われます。
三振制度時代の教訓から、現在の5回という制限は、受験生により多くのチャンスを与えつつ、司法浪人の長期化を防ぐというバランスを取った設計となっています。制度の歴史を理解することで、現行制度の意義をより深く理解できます。
Q. 司法試験の予備試験に回数制限はありますか?
司法試験の予備試験には回数制限がありません。つまり、予備試験は何度でも受験することが可能です。これは司法試験本試験の5年間で5回という制限とは大きく異なる点です。
予備試験に回数制限がないことは、司法試験で5回の受験機会を使い切った人にとって重要な救済ルートとなっています。予備試験に合格すれば、法科大学院を修了しなくても司法試験の受験資格を得られ、さらに合格年から新たに5年間で5回の受験機会が与えられます。
ただし、予備試験は非常に難関です。2023年度の予備試験合格率は約4.0%で、司法試験本試験の合格率45.3%と比較すると、その難易度の高さが分かります。予備試験は短答式試験、論文式試験、口述試験の3段階で構成されており、各段階で高い学力が要求されます。
予備試験に回数制限がない理由は、予備試験が「法科大学院を修了した者と同等以上の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうか」を判定する試験であり、その能力を有する者には年齢や受験回数に関わらず受験資格を認めるべきという考えに基づいています。
予備試験に回数制限がないことは、社会人や経済的に法科大学院に通えない人にとって、法曹を目指す重要な道となっています。仕事をしながら、あるいは独学で予備試験の合格を目指し、何年もかけて挑戦し続ける人も少なくありません。回数制限がないからこそ、様々なバックグラウンドを持つ人に法曹への門戸が開かれていると言えます。
Q. 司法試験の平均受験回数は何回ですか?
司法試験合格者の平均受験回数は、近年約1.5~1.8回程度で推移しています。これは、合格者の大多数が1回目または2回目の受験で合格していることを意味します。
より詳しく見ると、合格者の約70%が1回目の受験で合格しており、約20%が2回目、残りの約10%が3回目以降の受験で合格しています。つまり、合格者の約90%が2回以内に合格しているという計算になります。
予備試験ルートと法科大学院ルートで平均受験回数に若干の違いがあります。予備試験合格者の平均受験回数は1.3~1.5回程度とやや低めで、多くの予備試験合格者が1回目の受験で司法試験に合格しています。一方、法科大学院修了者の平均受験回数は1.6~1.9回程度とやや高めです。
この平均受験回数のデータから分かることは、司法試験において早期合格が標準的なパターンであるということです。3回目、4回目、5回目の受験で合格する人は少数派であり、受験回数を重ねるほど合格が困難になる傾向があります。
平均受験回数が1.5~1.8回という数字は、受験生にとって一つの目標値となります。「2回以内に合格する」ことを目標に設定することは、統計的に見て十分に現実的な目標です。逆に、3回目以降の受験となった場合は、学習方法の見直しや専門家のアドバイスを求めるなど、何らかの対策を講じるべきシグナルと捉えることができます。
なお、この平均受験回数は「合格者」の平均であり、不合格者を含めた全受験者の平均ではない点に注意が必要です。5回受験して不合格となった人は統計に含まれないため、実際の全受験者の平均受験回数はこれよりやや高くなる可能性があります。
Q. 司法試験の回数制限が撤廃される可能性はありますか?
現時点では、司法試験の回数制限が近い将来に撤廃される可能性は低いと考えられます。ただし、将来的には法曹養成制度全体の見直しの中で、再度議論される可能性はあります。
日本弁護士連合会(日弁連)は回数制限の撤廃を継続的に要求していますが、政府(法務省、文部科学省)は現行の5年間で5回という制度を維持する方針を示しています。2015年に3回から5回に緩和したばかりであり、この制度改正の効果を見極めるべきだというのが政府の立場です。
回数制限を維持する主な理由は、旧司法試験時代の司法浪人問題の教訓です。回数制限がなかった旧司法試験では、10年以上も受験を続ける人が多数存在し、社会経験を積む機会を失い、進路変更が困難になるという深刻な問題がありました。政府はこの問題の再発を懸念しています。
また、現行の5年間で5回という制度は、受験生に十分なチャンスを提供しつつ、受験生活の長期化を防ぐバランスの取れた制度として評価されています。さらに、予備試験という救済ルートが存在することも、完全な撤廃が必要ないという論拠となっています。
ただし、将来的には状況が変化する可能性もあります。法科大学院の志願者減少が続く、5回で不合格となる「五振者」の進路問題が深刻化する、諸外国との制度比較から国際標準に合わせる必要性が高まるなどの状況変化があれば、制度見直しの議論が再燃する可能性があります。
当面は現行制度が継続される見込みですが、受験生としては、制度改正の可能性に期待するよりも、現行の5年間で5回という制度を前提として、その中で合格を目指す戦略を立てることが現実的です。特に、1回目または2回目の受験での合格を目指すことが、最も確実な道と言えるでしょう。
まとめ:司法試験の回数制限を理解して効率的に合格を目指そう
本記事では、司法試験の回数制限について、制度の仕組み、計算方法、歴史、そして回数制限が設けられた理由について詳しく解説しました。重要なポイントを改めて確認しましょう。
- 司法試験は5年間で5回まで受験可能:現行制度では、受験資格を得た年から5年以内に最大5回まで受験できます。予備試験には回数制限がないため、5回の受験機会を使い切った後も、予備試験合格により新たな受験資格を得ることが可能です。法科大学院を修了した年、または予備試験に合格した年が起算点となり、その年から5年間が受験期間となります。
- 1回目の受験が最も合格率が高い:司法試験合格者の約70%が1回目の受験で合格しており、受験回数を重ねるほど合格率は低下します。法科大学院で学んだ知識が最も新鮮な状態で試験に臨める初回受験が、合格の最大のチャンスです。2回以内に合格することを目標とし、できる限り早期合格を目指すべきです。
- 回数制限には明確な理由がある:司法試験に回数制限が設けられたのは、旧司法試験時代の司法浪人問題への対応、早期の進路変更を促すため、法科大学院教育の効果を高めるため、そして受け控えの防止という4つの理由があります。5年間で5回という制限は、受験生に十分なチャンスを与えつつ、受験生活の長期化を防ぐバランスを取った設計となっています。
司法試験の回数制限を正しく理解できたら、次は効率的な学習計画を立てて実践しましょう。司法試験の受験資格や司法試験の合格率の詳細情報を参考に、自分に最適な受験戦略を構築することをおすすめします。
本記事を通じて、司法試験の回数制限の仕組みと、早期合格の重要性を理解いただけたはずです。これらの情報を活用して、司法試験合格という目標の実現に向けて計画的に取り組んでいきましょう。限られた受験機会を最大限に活かし、1回目または2回目の受験での合格を目指して、着実に準備を進めてください。
-
 スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら
スマホ完結型の効率学習で司法試験対策
もっと見る今月のキャンペーン スタディングの司法試験講座はこちら -
 司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら
司法試験といえば伊藤塾。圧倒的合格実績
もっと見る今月のキャンペーン 伊藤塾の司法試験講座はこちら -
 合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
合格実績と返金制度が魅力の司法試験講座
もっと見る今月のキャンペーン アガルートの司法試験講座はこちら
司法試験の関連記事

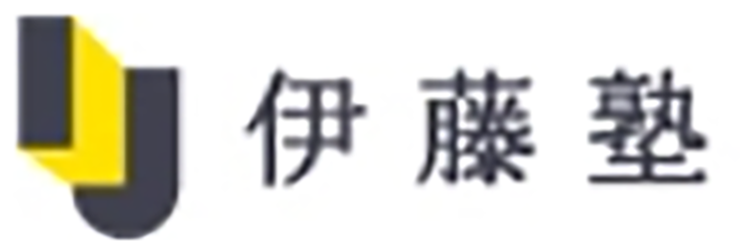


コメント